- はじめに―私が大切にしている4つのこと
- 1 通常の学級で苦手さのある子の学びを支える視点
- 1 教室環境の視覚化
- 2 活動環境の構造化
- 3 教材や体験の共有と目標に応じた関わり
- 4 発想の柔軟性
- 5 結果への前向きな受け止め
- 6 自身のマネジメント
- COLUMN ● 同僚性
- 2 通常の学級での学びを支えるツール&アイデア
- 生活
- 1 学校生活の予定を確認し振り返りができる 日課表
- 2 時間を意識し進んで学習に取り組める 作業学習シート
- 3 下校後にすることがわかり,自ら取り組める 帰ったらすることカード
- 4 家庭との連携と環境調整で身に付ける 持ち物管理の習慣
- 5 授業準備も片付けもすぐにできる ジッパーケース
- 安心
- 1 何をすべきかわかり,進んで学習に取り組める 板書の使い方
- 2 自分の状態に気付き,対処方法を考えられる ポスター・シート
- 3 指導・支援を通して安心して学習に取り組める 座席配置の工夫
- 4 見やすい環境の中で授業に集中できる 情報の提示の考え方
- 5 落ち着いて授業に参加できる 話し方の配慮
- 関わり
- 1 友達関係を深める・広げる 集団編制の考え方
- 2 肯定的に関わり合い,主体性を引き出す 活動の進め方
- 3 全員がグループ活動に参加できる マニュアル・役割分担表
- 4 「わかりません」「教えて」「NO」が言える 学級づくり
- 5 相手の反応が見てわかる 自分の思いをわかりやすく伝えられる リアクションボード
- 環境
- 1 過ごしやすい服装選びをサポートする 気温と服装シート
- 2 感じ方を視覚化し,調整に繋げる 暑さの視覚化シート
- 3 空間を広げ,教材が使いやすくなる デスクレスト
- 4 筆箱の中身がわかり管理しやすくなる クリアタイプのペンケース
- 5 自ら授業準備に取り組める 授業準備予告シート
- 姿勢・動き
- 1 目指したい姿勢がわかる 姿勢を示すシート
- 2 立ち位置がわかり,主体的な活動参加に繋がる 足型マーク
- 3 着席して授業に参加できる時間を増やす 椅子周りのツール
- 4 落ち着いて学習に取り組める時間を増やす 支援の視点
- 5 力加減を意識できるようになる 事前と事後の関わり方
- 聞く
- 1 子どもの聞く姿勢を整える 話し始めの工夫
- 2 指示や説明を伝わりやすくする 教師の話型
- 3 共通のイメージをもつことをサポートする 視覚的な手立て
- 4 自ら聞く姿勢を整える 静かにボード
- 5 聞くことの支援が広がる 教師の役割分担
- 読む
- 1 文章に書かれていることを整理できる 5Wシート
- 2 安心して読む課題に取り組める 音読記録シート
- 3 書き手・登場人物の感情を考えることをサポートする 感情カード
- 4 読むことへの負担を減らす 道具や表示の工夫
- 5 読みやすさをカスタマイズできる デジタル教科書
- 見る
- 1 「ここを見て」の“ここ”が伝わる 提示の工夫
- 2 聞いて,見て,取り組める 1枚スライド
- 3 見て課題に取り組む経験を重ねる 児童生徒への寄り添い方
- 4 今取り組むべき活動が見てわかる シンボルの活用
- 5 できる「見る」を見つけ,支援に繋げる 実態把握のポイント
- 考える
- 1 考え,伝える経験を積み重ねる 発問の型の工夫
- 2 自分なりの考えをもつことに繋げる 選択肢の提示
- 3 安心して考えることに取り組める 学級づくり
- 4 伝える視点を示し,話の具体を引き出す 5Wシート
- 5 考える活動に見通しがもてる 流れの視覚化
- 伝える
- 1 自分の考えを伝えやすくなる アンサーボード
- 2 相手の「いいね」を視覚化できる タックシール
- 3 話し合い活動を深め,まとめる 発表用ツールの活用
- 4 安心して発表することに取り組める 発表方法の選択肢
- 5 安心して伝え合うことができる グループ活動でのルール・マナー
- 書く
- 1 書くことへの負担感・抵抗感を減らす 支援の視点
- 2 全体と個人の両方の支援を可能にする 道具の活用
- 3 「できた」を積み重ねる 個別目標の設定
- 4 自ら字形を意識して書くようになる 訂正の伝え方
- 5 書くことに前向きに取り組める 漢字ノートのフィードバック
- 計算する
- 1 できるための道筋を見つける 実態把握と手立ての検討
- 2 苦手意識を大きくさせない 早期支援やフォロー
- 3 計算方法が見てわかる ワークシートの工夫
- 4 「できた」「わかった」を積み重ねる 段階別の課題設定や提示の工夫
- 5 安心して計算問題に取り組むことに繋げる 机間巡視・机間指導の考え方
はじめに―私が大切にしている4つのこと
1 了解性
私は2017年度から専任の特別支援教育コーディネーターとして,近隣の幼稚園や小学校を対象にコンサルテーションや研究会の協力などに取り組んでいます。特別支援教育コーディネーターとして初めての業務を迎える日は,かなりの緊張感や不安感がありました。そんな中でも上司や先輩教師の姿勢からコーディネーターとして必要な見方や考え方を学び,今日を迎えることができたことに感謝しています。
ある時,その上司からインクルーシブ教育システムの推進には「クラスの了解性を高めることが大切である」という話を聞きました。私なりに解釈すると児童生徒一人一人がお互いの考えを尊重し,相互理解を深めること(=了解性)により,教室には多様性が育まれていくというものです。そのために教師は児童生徒の実態に応じた環境調整や前向きな活動機会の確保が求められているのではないかと思います。
2 私もOK,あなたもOK
特別支援教育では教育的ニーズを有する児童生徒への指導や支援を進める際,実態把握をもとにした「目標」とそのために必要な「手立て」を考えます。そして児童生徒の姿から目標と手立てを振り返り,「達成(~できた)」と評価した場合は,次の目標を設定するというように段階的に教育的支援を展開します。なお達成できなかったと判断される場合は,目標や手立てが教育的ニーズに合致していなかったと考え,目標や手立ての改善に繋げます。
1つの方法に縛られない柔軟性のある発想は,多様性を保障し,お互いの前向きな姿に触れ合う機会にもなります。まさに「私もOK,あなたもOK」という発想に通じる部分があるのではないかと思います。このような視点がクラス内の了解性を育み,豊かな人間関係の形成に繋がると言えます。
3 コラボレーション
本書は特別支援教育について,特に私のコンサルテーションの経験をもとにまとめたものです。紹介している考え方や手立ては絶対的なものではありません。大事にしてほしいことは,目の前の児童生徒にとってどのような手立てが考えられるか,そして実践後に効果を確かめることです。各学校教育が培ってきた文化や視点があると思います。そこに少し特別支援教育の発想を付け加えるだけで,指導や支援の選択肢は広がっていくはずです。
小学校教育や特別支援教育というように,学校種ごとに教育観などが分けられる部分もありますが,「AかBどちらか一方」ではなく,ぜひ「AとBのコラボレーション」の視点を大切にしてほしいと思います。児童生徒に応じて,各学校種が培ってきた実践のよいところ・強みを組み合わせたり創造したりしながら指導や支援に生かしてほしいと思います。
4 普段の実践を振り返ること
多様な実態が見られる学級でも,自然と児童生徒が認め合ったり関わり合ったりする様子が見られているクラスがたくさんあり,そこには担任の先生の思いや願いをもとにした様々な工夫があります。先生と話をしてみると,決して特別支援教育の視点を学級運営や授業づくりに反映しようと狙って取り組んだものばかりではありません。後から「これって特別支援教育の視点に似ている」と気付くことも多くあります。ぜひ本書を読み進める中で,普段の実践のよいところ,特に児童生徒の「できた」「わかった」に繋がったポイントはどこだったのかという視点で自身の実践を振り返ってください。
2024年12月 /佐藤 義竹
-
 明治図書
明治図書














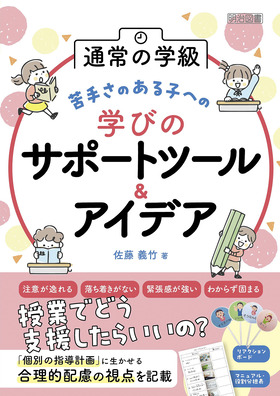
 PDF
PDF

