- はじめに
- 1章 ほめるための心構え
- 10割ほめる
- 常に「ほめる」体質になる
- 2章 ほめ方の基礎基本
- あいづち言葉を使う
- ほめ言葉と指示語をセットにする
- 非言語をほめる
- 非言語の身体動作でほめる
- 「決めつけ」を止める
- 口ぐせを肯定的なものにする
- 3章 場面別ほめる技術
- 授業全般
- 授業でほめる
- ほめるポイントと教師の考え方
- 学び合うテンションをあげる
- 対話・話し合い
- 意味のある対話・話し合いにする
- 対話・話し合いを成立させる
- 対話活動を育てる
- 聞く
- ほめる聞き方をする
- 聞く力のほめ方
- 聞く力を育てるほめ言葉
- 聞き合いを促すほめ言葉
- 関係づくり
- 学級全体をほめる
- 学び合う気持ちを育てる
- 菊池メソッド
- 「ほめ言葉のシャワー」でほめる
- 「成長ノート」でほめる
- 気になる子・気になる場面
- 「わかりません」をほめる
- 当たり前を本気でほめる
- 不安をなくすほめ言葉
- 失敗をほめる
- アクシデントをほめる
- 気になる子を変えるほめ言葉
- その他
- 子どもたちの作品をほめる
- ほめるトレーニング的取り組み
- おわりに
はじめに
数か月前のある日、自宅近くの行きつけの居酒屋で、
「もしかしたら、菊池先生じゃないですか?」
と50代の男性から声をかけられました。話を聞くと、40年前の教え子でした。
初任2、3年目の5、6年生の2年間担任したAくんでした。
彼は、こんな話をしてくれました。
「小学生のとき、先生が母親に、『Aくんはボールの魔術師みたいです』と僕のことをほめてくれたのです。その後、何度も母親はその言葉を僕に話してくれました。母親も喜んでいて、僕もうれしかったです。今でも時々思い出します」
彼は、プロテニス選手になっていました。
教師の一言の影響の大きさを改めて感じたときでした。
言われてうれしいことは、いつまでも覚えているものです。このことは、大人も子どもも一緒です。逆に、言われて嫌なこともいつまでも覚えているものです。大人も子どもも一緒です。
私は今、全国の学校を飛び回っています。ここ10年間続けています。
「10割ほめよう」と心に決めて、飛込授業を繰り返しています。
授業後の子どもたちからの感想に、
「こんなにほめられた1時間はありませんでした。私もみんなも笑顔になりました。幸せな1時間でした。ありがとうございました」「あっという間の時間でした。菊池先生は、どんなこともほめて認めてくれるので安心して授業に参加できました」「『一人ひとり違っていい』ということを話してくれて、ほめてくれて、自信をもって発表や話し合いができました。最高の授業でした」
などの言葉が並びます。ほめ過ぎではないかと思うこともありますが、素直に喜びながらほめ言葉の力を感じています。
また、参観された先生方からも、
「気になる子をリフレーミングしてプラスに価値づけてほめているところに驚きました。目から鱗の瞬間が何度もありました」「いつもは発言しない子たちも、意欲的に活躍していました。先生の言葉にはネガティブな言葉はひとつもありませんでした」
といった感想もたくさんいただくこともあり、ほめ言葉の効果を実感しています。
私は、ほめ言葉は、コミュニケーションの中心にあるものだと考えています。
そして、本書でも時々ふれているコミュニケーションの公式を次のように考えています。具体的にほめるときに意識していることでもあります。
コミュニケーションの公式=(内容+声+表情・態度)×相手軸
各項目を少し詳しく説明すると、以下のような内容になります。
〇内容……伝わりやすい構成、プラスの言葉(価値語、四字熟語、ことわざ、慣用句など)、具体的な表現(数字、固有名詞、会話文、5W1Hなど)、効果的な表現(比喩、擬態語、擬音語など)
〇声………ちょうどよい大きさ、高低、大小、強弱、緩急、間(ま)
〇表情……笑顔、視線(方向、時間など)、目の動き、口の形
〇態度……指や手や腕の動き、姿勢(向き、傾き、立ち方など)、首のうなずきやかしげ方、足の動きや開き方、立ち位置や身体全体の移動の仕方やその時間
〇相手軸…愛情、想像力、豊かな関わり合い、情報共同体としての心のふれあい、ほめる・認める・励ます・応援する・盛り上がる・感謝するなどの思い
当然、これらを意識したほめ言葉であるべきだと強く考えています。
本書は、月刊誌『授業力&学級経営力』(明治図書)の3年間の連載を中心にまとめたものです。全て実際の授業を通して私自身が学んだことです。
毎月のテーマ別で書いていたために、学年や実態等で、レベルの1、2、3の整合性等がずれているケースもあると思いますが、具体的な授業場面に合わせて臨機応変に活用していただけるとありがたいです。アレンジしながら先生方のオリジナルなほめ言葉が生まれることを願っています。
在職中から今までに出会った子どもたちにも感謝しています。ほめ言葉は、子ども、学級を変える力があると確信しています。
本書が、たくさんの先生方に活用され、たくさんの教室で実践され、たくさんの子どもたちの笑顔があふれることを願っています。
令和6年6月20日 菊池道場道場長 /菊池 省三














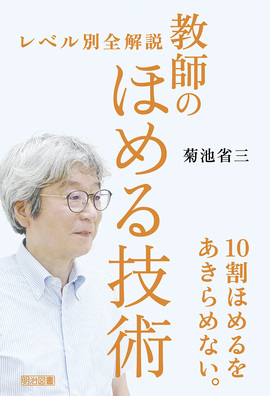
 PDF
PDF


それにしても、10割ほめるをあきらめない。すごい言葉と覚悟です。
褒めることを技術として示しつつ、もっと大切な想いについて学びました。