- はじめに
- CHAPTER1 Chromebookを活用した国語授業
- 1 国語科にChromebookを導入する
- 国語授業にタブレットは必要か
- 国語科とタブレットの相性
- Chromebookでできること
- これまでの学習活動をChromebookに置き換えよう
- 2 「話すこと・聞くこと」とChromebook
- ICTの発展と「話すこと・聞くこと」の授業
- Chromebookによる「話すこと・聞くこと」の授業のアップデート
- 話す内容が「ない」状態に応える
- 話し合いの過程で思考が「わからない」状態に応える
- 振り返る対象が「見えない」状態に応える
- 3 「書くこと」とChromebook
- 「書くこと」にChromebookを取り入れるとどうなる?
- 「書くこと」の学習活動をChromebookに置き換える
- 単元の構想に生かす
- 4 「読むこと」とChromebook
- 「読むこと」の授業とChromebook
- 「読むこと」の授業と〈検索〉
- 「読むこと」の授業と〈共有〉
- CHAPTER2 Chromebookを活用した授業の環境づくり
- 1 環境を整える
- 環境整備・第1段階/ハード面の整備
- 環境整備・第2段階/校内での児童・生徒と教師の習熟
- 環境整備・第3段階/授業に生かす
- 2 年間指導計画に組み入れる
- 系統性を考える
- 年間指導計画に組み入れる
- 年間指導計画を作成する
- CHAPTER3 Chromebookを活用した国語授業プラン16
- 1 「話すこと・聞くこと」の授業プラン
- ビデオ録画でスピーチをする 「たからものについてはなそう」(2年)
- Jamboardで振り返りながら,ペア・トークをする 「考えを整理しながら話し合おう」(3年)
- Jamboardで見える化をして,グループ・ディスカッションをする 「計画的に話し合おう」(5年)
- 2 「書くこと」の授業プラン
- Jamboardで共有し,ワークシートに観察記録文を書く 「見つけたことをつたえよう」(2年)
- ドキュメントで構成を考え,創作文を書く 「物語をつくろう」(4年)
- Jamboardで話し合い,ドキュメントで意見文を書く 「意見を伝える文章を書こう」(6年)
- 3 「読むこと」の授業プラン
- カメラ機能で音読を録画する 「お手紙」(2年)
- ドキュメントの音声入力で自分の考えを書く 「モチモチの木」(3年)
- ドキュメントで人物像をまとめる 「白いぼうし」(4年)
- ログラインをJamboardの付箋で整理し心情の変化を捉える 「大造じいさんとガン」(5年)
- ドキュメントで学習レポートをまとめ,交流する 「やまなし」(6年)
- Jamboardの付箋で形成的な評価を促す 「ビーバーの 大工事」(2年)
- ドキュメントを活用してレポートを作成する 「すがたを変える大豆」(3年)
- Jamboardで題名読みをし,文章構成を考える 「アップとルーズで伝える」(4年)
- ドキュメントとClassroomでフィードバックをする 「想像力のスイッチを入れよう」(5年)
- ドキュメントとスライドで自分の解釈を発表する 「『鳥獣戯画』を読む」(6年)
- *Google for Education,Chromebook,Googleドキュメント,Googleスプレッドシート,Googleスライド,Google Classroom,Google Jamboard ,Googleフォーム,およびGoogle Meetは Google LLC の商標です。
はじめに
PCの本来の使い道は,思考を助ける,あるいは思考から表現までのプロセスをつなげるものであり,そういった使い方をしようとするなら,常に1人1台の環境があること=パーソナルであることが,PC等を授業で効果的に使うための最低条件となりますが,そうなってはいませんでした。そんな状況が,2020年のコロナ禍によって一気に改善されたことは,誰もが認めるところでしょう。臨時休校によるオンライン授業などを経験したことで,1人1台の必要性が認知され,急速に1人1台のタブレット配備が喫緊の課題となって,日本中の学校,子供たちに行き渡ることになったのです。
このことは,配備する側にとっては一つのゴールかもしれませんが,配備された側にとってはスタートです。まずは,どこに置けばよいか,充電はどうするか,アップデートは誰がするかなど管理面について考えなければならなりません。それが済んだら,研修はどうするか,どの教科,領域で使うか,どういうアプリを使うか,子供たちが使いこなせるようにするにはどうするかなどの学習指導面についても考えなければならないのです。しかも,これまで,子供たちや教師が慣れ親しんできたWindowsのPCを使うわけではなく,タブレットを使うのです。著者も含め,多くの人がタブレットはPCの廉価版で,機能はPCに準じたものであると考えていたと思います。例えば,本書が取り上げたChromebookでいえば,OSはWindowsではなく,Google Chromeです。そういうOSを使わなければならないこと自体が青天の霹靂でしょう。まさに,ゼロからのスタートです。
教師のほとんどは「素人」であり,「素人」が「ド素人」=子供に教えるという状況です。そういう状況で,教師はどうするでしょうか。まずは子供たちの情報スキルを高めることに徹するのです。それも,総合的な学習の時間とか学級活動といった教科に食い込まないような時間を使うか,教科の時間を使ったとしても単元を詰めて生じた隙間時間を使って行われます。それはそれで子供たちの情報スキルは上がるので,無駄にはならないのですが,あくまで「タブレットを教える」レベルです。しかし,PCやタブレットが思考のための道具であることを踏まえると,考えるために使ってこそであり,「タブレットで教える」域を目指すことで,1人1台が生きるのです。
「タブレットで教える」を基本的なスタンスにすると,教科の授業にどう取り入れたらよいかを考えずにはいられなくなります。タブレットが道具であれば,練習ばかりでなく,実際に使いこなして初めて真価を発揮するし,これまで目指しても到達できなかった授業を実現できるかもしれません。
国語の授業は難しいですね。努力してもなかなか上達しないという方も多いでしょう。だからこそ,タブレットを積極的に取り入れるという新しいチャレンジによって国語の授業をレベルアップできるのではと考えました。基になる指導案は,これまでに著者や仲間たちが練り上げたものを取り上げ,そこにいかにタブレットを有効に取り入れるかを考えました。そして,その提案をより実践に役立つものにするために,本書ではChromebookに絞ることにしました。そして,活用する機能,アプリも特別な人にしか使えないものではなく,標準装備のアプリをフル活用することを目指しました。
本書をきっかけにし,学校現場でChromebookを通してより楽しく質の高い国語の授業が実践されることを願っています。
2021年9月 著者一同
注意とお願い
・本書で紹介しているアプリ等の仕様は2021年5月現在のものであり,今後変更になる可能性があります。
・本書で紹介しているアプリ等を使う場合は,各自治体や学校のガイドライン等に沿って使用してください。
・録音・録画したデータには個人情報等が含まれている可能性があるため,それらの保存先等は学校等の方針に沿って適切に取り扱ってください。
・本書で示した活動を実践したことにより生じたトラブル等について,本書の執筆者は一切の責任を負いません。
-
 明治図書
明治図書- 一人一台端末を活用した授業例についてわかりやすく解説されており大いに参考になりました。2023/1/2040代・小学校教員
- 大変参考になった。2022/5/3150代・小学校教員
- 勤務校ではiPadを使っていますが、Googleのアプリも使っています。考え方も含めて、国語科でのクロームブック活用のアイディアを得ることができました。読みながら、使っている様子を思い浮かべることができました。クロームブックはもちろん、iPadを活用している学校の先生も参考になる本だと思います。2022/3/2750代・小学校教員














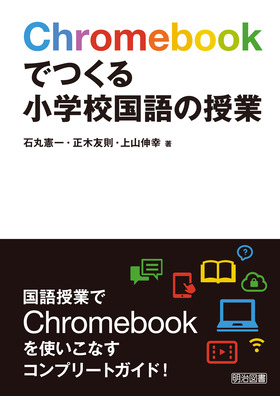
 PDF
PDF

