- はじめに
- 本書の構成と使い方
- Chapter1 動作感覚つくりの運動で楽しく飽きずに体力・運動能力をアップする
- 1 体育授業における動作感覚つくりの必要性
- 2 主運動につながる動作感覚つくりの運動〜体育授業への取り入れ方
- 3 動作感覚つくりの運動の効果
- 4 ライントレーニングの効果
- 5 運動機能の発達と脳神経系の関係
- Chapter2 動画でわかる動作感覚つくりの運動&授業化アイデア
- 器械運動系
- 1 マット運動につながる動作感覚つくりの運動
- 低学年におすすめのマット運動につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめのマット運動につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめのマット運動につながる動作感覚つくりの運動
- ――支持する動作につながるライントレーニング
- 2 鉄棒運動につながる動作感覚つくりの運動
- 低学年におすすめの鉄棒運動につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめの鉄棒運動につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめの鉄棒運動につながる動作感覚つくりの運動
- 3 跳び箱運動につながる動作感覚つくりの運動
- 低学年におすすめの跳び箱運動につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめの跳び箱運動につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめの跳び箱運動につながる動作感覚つくりの運動
- ――動きの切り替えを想定した助走から両足での踏切りにつながるライントレーニング
- 陸上運動系
- 4 短距離走・リレーにつながる動作感覚つくりの運動
- ――走る動作につながるライントレーニング
- 低学年におすすめの短距離走・リレーにつながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめの短距離走・リレーにつながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめの短距離走・リレーにつながる動作感覚つくりの運動
- 5 ハードル走につながる動作感覚つくりの運動
- ――ハードル走につながるライントレーニング
- 低学年におすすめのハードル走につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめのハードル走につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめのハードル走につながる動作感覚つくりの運動
- 6 走り幅跳び・走り高跳びにつながる動作感覚つくりの運動
- ――跳ぶ動作につながるライントレーニング
- 低学年におすすめの走り幅跳び・走り高跳びにつながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめの走り幅跳び・走り高跳びにつながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめの走り幅跳び・走り高跳びにつながる動作感覚つくりの運動
- 7 投の運動につながる動作感覚つくりの運動
- ――投げる動作につながるライントレーニング
- 低学年におすすめの投の運動につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめの投の運動につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめの投の運動につながる動作感覚つくりの運動
- ボール運動系
- 8 ゴール型(攻守が入り交じる)につながる動作感覚つくりの運動
- ――蹴る動作につながるライントレーニング
- 低学年におすすめの攻守が入り交じって行うゴール型につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめの攻守が入り交じって行うゴール型につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめの攻守が入り交じって行うゴール型につながる動作感覚つくりの運動
- 9 ゴール型(陣地を取り合う)につながる動作感覚つくりの運動
- ――方向転換する動作につながるライントレーニング
- 低学年におすすめの陣地を取り合うゴール型につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめの陣地を取り合うゴール型につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめの陣地を取り合うゴール型につながる動作感覚つくりの運動
- 10 ネット型につながる動作感覚つくりの運動
- ――補球動作につながるライントレーニング
- 低学年におすすめのネット型につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめのネット型につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめのネット型につながる動作感覚つくりの運動
- 11 ベースボール型につながる動作感覚つくりの運動
- ――打つ動作,打ち返す動作につながるライントレーニング
- 低学年におすすめのベースボール型につながる動作感覚つくりの運動
- 中学年におすすめのベースボール型につながる動作感覚つくりの運動
- 高学年におすすめのベースボール型につながる動作感覚つくりの運動
- おわりに
- 執筆者一覧
はじめに
私は,幼い頃から運動が苦手で,運動で誰かと競争することも好きではありませんでした。編著者の柳田先生の言葉を借りれば「運動に関わる神経系の機能が低い」子供だったと思います(p.21参照)。発育が早く身体は大きい方でしたので,身体を支えることができず,器械運動系,特に鉄棒運動は苦手でした。そのような私が初めて逆上がりをできるようになったのは,いわゆるゴールデンエイジ終わり頃の小学校6年生の秋でした。下校途中,校庭の隅にある鉄棒が目に入り,なんとなく逆上がりをしてみました。すると,まるで魔法にかかったようになぜかできてしまったのです。鉄棒に触るのも久しぶりだったので,どうしてできるようになったのか自分でも理解できませんでしたが,嬉しくて何度も繰り返したのを覚えています。
今振り返ってみると,体育授業の中で担任の先生に様々な動作感覚つくりをしていただいていたのだと思います。逆上がりができるようになったことをきっかけに,私は自ら運動に取り組むようになり,体育が好きな教科となりました。放課後には友達と一緒に野球をするようになり,中学校時代は野球部に所属しました。高等学校時代は,陸上競技部に所属しました。大学で体育を学ぼうと,教育学部保健体育科に進学しました。そこで仲間と様々な運動に取り組む中で,さらに多くの動作感覚が身に付きました。私の感受性期は比較的遅かったのだと思われます。しかし,高等学校時代から大学時代にはケガに悩まされました。編著者の佐藤先生の言葉を借りれば「動作感覚が失われている状態」であったことが原因かと思います(p.15参照)。幼い頃から動作感覚が身に付いていれば,大きなケガをせず,もう少し陸上競技を続けられたのかなとも思います。
現在,小学校現場に勤務していると小学校時代の私と似たような悩みをもつ子供たちに出会います。その子供たちにも私が経験したような運動の楽しさや喜びをもっと早い時期から味わってほしいと願い,本書を執筆しようと考えました。
そこで,小学校現場で実際に子供たちと接している先生方から生の声を発信するため,執筆には現役の小学校教諭の方々にお願いしました。さらに,理論的な裏付けのある動作感覚つくりの運動を紹介するために,東京理科大学教授の柳田信也先生,株式会社Sports Multiply代表取締役でアスレティックトレーナーの佐藤哲史先生に編集・執筆をお願いしました。このことにより,子供たちの実態に応じた運動機能の発達と脳神経の関係を踏まえ,ケガの防止にもつながる動作感覚つくりの運動を紹介できる体制が整いました。紙面では伝わりにくい部分については,QRコードを活用して動画で理解できるように工夫しています。是非,紙面とともに動画を御覧いただければ幸いです。
2023年8月 /森田 哲史
-
 明治図書
明治図書- 感覚を作るという視点がとても参考になりました。手軽にできる運動が多く、準備運動にも取り入れやすいです。2023/12/2240代・小学校教員














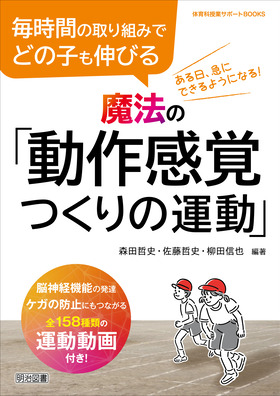
 PDF
PDF

