- はじめに
- 「起承転結型授業」まとめ
- CHAPTER1 全教科「ずっと使える」授業スキル 活用のポイント
- 0 授業における「起承転結」とは?
- POINT1 「起」の段階の授業スキルはスイッチを入れるために
- POINT2 「承」の段階の授業スキルは見通しを明確にするために
- POINT3 「転」の段階の授業スキルは思考を拡散・展開するために
- POINT4 「結」の段階の授業スキルは新しい考えに気づけるように
- CHAPTER2 図解で詳しくわかる 先生1年目からずっと使える授業スキル
- 発問のスキル
- 01 概要 子どもの学びに寄り添った発問テクニック
- 02 起の段階 子どもの学びスイッチを入れる確認発問
- 03 起の段階 子どもの学習参加意欲を高める全員参加発問
- 04 起の段階 子どもが本時の学びを自分事とする中心発問
- 05 承の段階 本時の学びを見通す見通し発問
- 06 結の段階 本時の学びを振り返る振り返り発問
- ペア対話のスキル
- 07 概要 ペア対話のメリット×成功ポイント
- 08 起・承の段階 「訊く」をベースとしたペア対話
- 09 転の段階 「聴く」視点を明確にする
- 指示のスキル
- 10 概要 雰囲気づくり×ルールづくり=指示が通りやすい風土醸成
- 11 承の段階 学習進行表で指示を視覚化する
- 子どもを動かすスキル
- 12 概要 子どもの動かし[型]=発問型×動き
- 13 起の段階 「想起・未来予想×隊形×動き」で多様な活動に
- 14 承の段階 子どもを動かして,「すること」を焦点化
- 15 結の段階 「わかった!できた!」を動きで実感
- 教師の演技力
- 16 概要 「役者」「芸者」になって授業を活性化させる
- 17 起の段階 子どもの学びをドラマティックにする
- 18 承の段階 子どもの自力解決を促進する
- 問い返しスキル
- 19 概要 「広げる!」「深める!」問い返し
- 20 転の段階 「発表者対教師」から,「発表者対子どもたち」へ
- 21 転の段階 問い返しで学びをさらに深める
- 説明スキル
- 22 概要 学びの土台と補足を担う説明スキル
- 23 起の段階 理解度を揃え,安心できる学びにつなぐ
- 24 結の段階 学びを実感させ,つかみ取らせる
- 励ますスキル
- 25 概要 子どもにも,教師視点でも,幅広い面で効果的
- 26 承の段階 励ます視点を明確にする
- 引き返すスキル
- 27 概要 子どもの気持ちに寄り添って引き返す
- 28 承の段階 感情とメリットで前向きに引き返す
- やる気を引き出すスキル
- 29 概要 やる気は技術で引き出せる
- 30 承の段階 学びの「原動力」を引き出す
- 反応するスキル
- 31 概要 個に応じた反応スキルを活用する
- 32 承・転の段階 子どもと授業を楽しむ「反応ことば」
- ジェスチャーのスキル
- 33 概要 ジェスチャーで重要事項を共有する
- 34 全段階 1時間1ジェスチャーを使う
- 子どもの注目を引きつけるスキル
- 35 概要 声を荒げずに引きつける
- 36 起・転の段階 「だれでも」「すぐに」「できる」を意識する
- 導入スキル
- 37 概要 持続可能な導入スキルを手に入れる
- 38 起の段階 導入スキル=「直感的×自分事」で考える
- ラベリングスキル
- 39 概要 「効果絶大」だからこそ慎重に使う
- 40 全段階 ラベリング言葉×教師の演技力
- ネームプレート活用スキル
- 41 概要 学習指導と生徒指導を一体化する
- 42 起の段階 子どもが学習に向かう意欲を高める
- 43 承の段階 見方・考え方,手法を自己決定させる
- 44 結の段階 本時の学びを振り返る
- 音楽活用のスキル
- 45 概要 音楽で子どもの気持ちに寄り添う
- 46 全段階 音楽は結婚式をイメージして使う
- つぶやき活用のスキル
- 47 概要 あいづち指導でつぶやきを引き出す
- 48 全段階 子どもたちの本音で授業をつくる
- ICTを活用するスキル
- 49 概要 ツールとしてICTを使い倒す
- 50 転の段階 ICTで協働を促進する
- 子どもが納得する学習計画をつくるスキル
- 51 概要 子どもたちの学びの道標をつくる
- 52 単元づくり全体 「自分たちの学習計画」にする
- 非言語スキル
- 53 概要 教師の言葉に「価値」をもたせる
- 54 承の段階 子どもたちとの共通非言語をつくる
- 心理学を生かすスキル
- 55 概要 自らの指導に心理学的背景をもたせる
- 56 全段階 即実践できる実用的な心理学を知る
- 時間を設定するスキル
- 57 概要 「時間意識」で子どもたちを育てる
- 58 全段階 「見通し」と「安心感」を時間で生み出す
- 振り返りのスキル
- 59 概要 学びを「実感」できる振り返りをつくる
- 60 結の段階 学びを自分自身と結びつけさせる
- おわりに
- 参考文献一覧
はじめに
『先生1年目からの授業づくり完全ガイド』が発刊されてから,まもなく1年が経とうとしています。前拙著は,授業づくりに悩む方や,自身の授業づくりの視点をアップデートしたいという先生方のために書かせていただきました。ありがたいことに,発売1か月足らずで重版となり,多くの方々に手に取っていただきました。「起承転結」を活用した授業づくりによって,教師と子どもが教材研究の視点を共有できるという,現場視点で役立つ情報を凝縮した内容となっています。
その続編にあたる本書は,前作の成果をさらに拡充・深化させた『指導技術』に特化した内容です。授業の「起承転結」という型を生かしながら,学習段階に適した具体的な指導技術を紹介しています。
本書で紹介される指導技術は,一般的には誰かが教えてくれるものではなく,優れた先生が現場での経験を通して「なんとなく」実践しているものです。それゆえ,言語化されず,無意識で身に付けていることが多いのです。
私の教員生活は順風満帆ではありませんでした。初任の頃は,離れた校舎で単学級を担任し,相談相手もなく,日々悩みながら授業をつくり,子どもたちと向き合っていました。当時は授業に時間をかけても,的外れなことも多く,未熟な指導で子どもたちを困らせていたこともあったと思います。
授業の導入では「子どもたちの興味を引くことが大事」と教わりましたが,どうすれば彼らの学習意欲を引き出せるかはわかりませんでした。淡々と授業を始め,子どもたちが休み時間モードから切り替わらないまま授業が進んでしまうこともありました。
授業の展開では「山場をつくる」ことが重要だと言われましたが,その「山場」をどのようにつくるのか,子どもたちをどのように導くのか,当時の私には不明でした。ただ,問題を出し,発表させ,まとめて終わるだけの授業が多く,教師の技術の見せどころが理解できていなかったのです。
授業の終末では,子どもたちの考えを「まとめる」といった表面的な作業に終始していました。あらかじめ教師が用意した「まとめ」を使い,それとなく掲示するだけでした。しかし,後になって振り返ると,この「まとめ」を子どもたちとともにつくり上げる過程が,教師としての面白さだと感じるようになりました。
初任の頃は,研究授業を通じて授業を参観する機会がありましたが,それはあくまで練りに練られた特別な授業です。日々の授業とは異なるため,その視点を直接,日常の実践に生かすのは難しいことでした。毎日の授業は「ライブ」そのもの。朝,お家の人と喧嘩して登校してきた子どもや,友だちとのトラブルに巻き込まれ,モヤモヤしたままの子ども,休み時間からの気持ちの切り替えを上手にできない子どもなど,様々な背景や思いをもつ子どもたちが教室に集まっています。そんな子どもたち一人ひとりに向き合い,学習意欲を引き出し,自力解決を促しながら,学びを深める言葉かけをし,「できた!」「わかった!」「友達と一緒だからできた!」といった自己効力感を日々の授業で感じさせることが必要です。
本書では,このような「ライブ感」のある授業で役立つ具体的な指導技術を紹介しています。各段階に応じた技術は,特定の教科に限らず,全教科に応用可能です。明日からでも実践できる技術が詰まっており,教師としての即戦力になること間違いありません。
例えば,「問い返しの技術」は,授業の中で欠かせないものです。授業が上手な先生は,必ずこの技術を使いこなしていますが,それを身に付けるには時間がかかります。しかし,まずは技術を知り,それを実践し,自分に合った形で取り入れることで,成長のスピードを大幅に高めることができます。「知らなければできない」ことは「知っていればできる」ということでもあります。毎日の授業はトライアンドエラーの連続であり,その積み重ねが,教師としての資質・能力を高めていくのです。
私は,SNSを通じて指導技術を発信しています。この発信は,日々の授業づくり・指導技術に悩んでいる先生方に向けて行っており,ありがたいことに,多くの方から共感をいただいています。現場で多忙を極める先生方にとって,授業づくりの時間が十分に取れない状況もあるかと思います。そんなとき,本書のような実践的な指導技術を集めた書籍が,きっと役立つでしょう。
本書は,見開き1ページで内容が構成されています。左ページは,図解でまとめています。図解部分は,汎用性高く実践することができるよう,抽象的な視点でつくっています。右ページには,その詳細を示しています。
すべての技術を取り入れる必要はありません。子どもの実態に合わせて,自分に合った技術を選び取っていただければと思います。そうすることで,「明日はこの発問を試してみよう」「この導入で仕掛けてみよう」と,前向きな気持ちで授業に臨めるはずです。その前向きな姿勢は,必ず子どもたちに伝わります。
本書の目的は,ライブ感ある日々の授業を充実させることです。指導技術を横断的に使いこなせるよう,多くの実践を掲載しています。現場での授業づくりに役立てていただければ幸いです。
2024年12月 /浦元 康
-
 明治図書
明治図書- 図解が分かりやすい2025/3/2040代・小学校教員
- どの年代の教師でも指導のスキルを確認するにはとてもいい書物だと思います。2025/3/750代・小学校教員














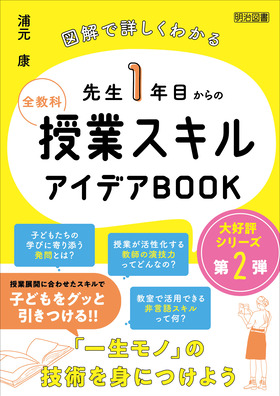
 PDF
PDF

