- はじめに
- 第1章 研究主任のマインドセット
- 01 理想を思い描く
- 02 コンセンサスを得る
- 03 決断と説明,両方を大切にする
- 04 必要な場合を見極めて,根回しをする
- 05 本人の意思は尊重しつつ,折衷案を探る
- 06 構えずに1対1で話せる場をつくる
- 07 管理職の先生方に味方になってもらう
- 08 順番と時期を見極めて,変えることを決める
- 09 勝負所かどうかを吟味する
- 10 「減らすこと」への意識をもつ
- 11 否定的な反応にフォーカスしない
- 12 普段の授業,関わりを大事にする
- 13 「だれが言うか」を考える
- 14 「教科が違う」の壁を壊す
- 15 研究授業という形にこだわり過ぎない
- コラム 研究大会後に熱く語った思い
- 第2章 研究主任の仕事,まずはこれから
- 16 4つのポイントを押さえて,スムーズに年間計画を立てる
- 17 3つのポイントを押さえて,伝わりやすい話をする
- 18 3つのポイントを押さえて,見てもらえる文書をつくる
- 19 2つのポイントを押さえて,考えてもらえる会議にする
- 20 3つのポイントを押さえて,職員図書を有効活用する
- 21 複数年で教育計画を見直す
- 22 無理が生じない形で研究紀要を作成する
- 23 他校の研究大会に参加する
- 24 授業以外に関する研修会を企画する
- コラム 初任者の言葉
- 第3章 研究の進め方
- 25 過去の研究を遡ることから,新しい研究の第一歩を踏み出す
- 26 サポート体制を考慮して研究部会を組織する
- 27 研究部会の目的と役割を明確化する
- 28 目の前の生徒の課題から研究テーマを検討する
- 29 研究テーマを具体的な行動レベルで示す
- 30 研究テーマに合った方法で成果を確認する
- 31 アンケートや報告にGoogleフォームを活用する
- 32 研究テーマを生徒にも周知する
- 33 研究内容や方法に選択肢をつくる
- コラム 失敗があってこそ
- 第4章 研究授業,研究大会の行い方
- 34 前年度からの声かけで,授業者への立候補を後押しする
- 35 様々なアプローチで授業者をサポートする
- 36 授業者のニーズに合わせて,協力者会を組織する
- 37 協力者会の充実度を高める
- 38 無駄を排し,書く意味のある指導案のひな型をつくる
- 39 事前の働きかけで,指導助言を充実させる
- 40 「この人がいい」と感じる人を講師として招く
- 41 相手意識をもって講師への依頼を行う
- 42 授業者自身が,授業の見方を示しておくようにする
- 43 発言がたくさん出るように,司会が協議会をデザインする
- 44 協議会の司会や方法の策を練る
- 45 研究通信を出す目的とタイミングを押さえる
- 46 研究通信を無理なく出し続ける工夫をする
- 47 おもてなしの気持ちを環境整備や「お土産」で表す
- 48 終わった瞬間にしかできないことをやる
- コラム 唯一手をつけなかったこと
- 第5章 日常的な取組の進め方
- 49 授業を見せ合い,ほめ合う文化をつくる
- 50 自分の授業を見に来てもらうためのお願いの仕方を工夫する
- 51 授業について話せる職員室にする
- 52 だれから巻き込むのか,作戦を練る
- 53 授業交流会を導入する
- 54 授業交流会の柔軟性を生かす
- 55 研究主任自身が熱意を見せる
- コラム 授業を考える時間を生むために
はじめに
「研究主任をお願いします」
校長先生からはじめてこう言われたとき,「自分には荷が重い」というのが正直な気持ちでした。
引き受けるしかないと思って引き受けましたが,「自分のことだけで精一杯なのに,学校全体の研究のことを考えることなんてできるのか?」「そもそも何をすればいいのかもわからないし,自信がない」など,次々にマイナスな感情が浮かんでくるような状態でした。
今,本書を手に取ってくださった方も,私と同じように「引き受けたけれどうまくやれるのか自信がない」「研究主任として何をどうしていいかわからない」と思っている方が多いのではないでしょうか。
その気持ち,わかります。
ですが,もし今の私が,研究主任を引き受けた当初の自分に声をかけられるなら,次の言葉を送ります。
「最初から研究主任らしい人はいないよ。研究主任をやることで研究主任らしくなっていくものだから大丈夫。研究主任だからこそ感じられる楽しさやうれしさもたくさんあるよ」
研究主任という役割をいただいてから,研究主任をしなければ気づけなかったこと,味わえなかっただろう充実感や達成感にたくさん出合ってきました。
もちろん,自分の思いが伝わらない無念さや,まわりの先生方とうまく協力できない悔しさも感じてきました。
しかし,それ以上に,「授業で生徒が…」とまわりの先生方から取組に対する生徒の反応を教えてもらったときのうれしさや,「授業に新しい工夫を取り入れてみるわ」とまわりの先生方の授業に対する熱の高まりを感じた瞬間の喜びは,非常に大きなものでした。
何より,その話をしてくださったときの先生方の表情がとても明るく,楽しそうであったことが強く印象に残っています。
そのような経験から,自分が研究主任としてまわりの先生方に働きかけることで,「よい授業がしたい」「教師という仕事はいい仕事だ」と思ってもらえれば,それが生徒の幸せにつながるのではないか,そのことに気づいた今は研究主任がとてもやりがいのある仕事だと思うようになりました。
以上のことを踏まえ,本書で伝えたいことは「研究主任の先生もまわりの先生も大切にした研究を進めていきましょう」ということです。
そのために,まず第1章で,研究主任が大切にしたいマインドセットについてまとめました。具体的な行動や判断の根本にあるマインドセットを理解しておいていただいた方が,その後の内容を理解しやすくなると思ったからです。
そして,第2章では,研究主任になったけれど何から始めたらよいかがわからない方のために,まずやるべきことをまとめました。
第3章と第4章では,研究主任の一番の仕事である研究の進め方,研究授業や研究大会の行い方について,研究テーマを決めるところから研究授業や研究大会の終わりまでの仕事をまとめています。
また,研究は特別なことばかりを考えがちですが,忘れてはならないこととして,第5章で日常的な取組についてもまとめました。
本書が,研究主任をされる先生のモチベーションを高めること,「研究主任をやってよかった」と感じることの助けとなることを願っています。そして,研究主任の先生の働きかけが,まわりの先生方や生徒の笑顔につながれば,私にとってそれ以上の喜びはありません。
2025年2月 /北村 凌
-
 明治図書
明治図書- 研究主任として大切なことがたくさん書かれていてとてもよかった。2025/4/240代・研究主任














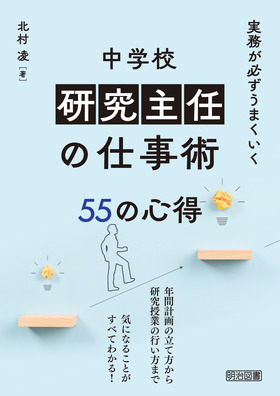
 PDF
PDF

