- はじめに
- 第1章 生徒指導主事としてのスタートダッシュ
- 01 年度はじめに,4つの基本的な役割を見直す
- 02 2種類の生徒指導の違いを認識する
- 03 生徒だけでなく,教員も安心できる企画を用意する
- 04 問題が起きたときの報告のシステムを構築する
- 05 年度はじめの職員会議に向けて周到な準備をする
- 06 3期/15か月サイクルで仕事を捉える
- 07 校長の懐刀としての役割を果たす
- 08 時代にチャンネルを合わせる
- 09 主な仕事のポイントを押さえ,効率化を図る
- 10 話す対象,人数の変化を意識する
- 11 同僚との協力関係を築く
- 12 問題行動調査のポイントを押さえる
- 第2章 悩まない生徒指導
- 13 共通理解を図り,共通行動を取る
- 14 「ブラック校則」の改善を図る
- 15 教職員全体で一貫した指導を行い,生徒の「納得」を重視する
- 16 「原則と例外」に迷わないために,2つの視点を押さえる
- 17 若さを武器に変える
- 18 スモールステップで理想の生徒像に迫る
- 19 指導が実を結ぶ時期にとらわれ過ぎない
- 20 生徒指導のビジョンを全教職員と共有する
- 21 長期休業中の注意事項を合言葉で伝える
- 22 男性的視点だけではなく,女性的視点も取り入れる
- 第3章 自信がもてる生徒指導
- 23 人生経験を補うために,まずやってみる
- 24 保護者対応を3つの場面に分けて,共通行動が取れるようにする
- 25 生徒と信頼関係を築くためのサポート,システム提案を行う
- 26 小学校と連携して,学力向上を図る
- 27 指導の線引きを生徒に示し,ポイントを押さえて叱る
- 28 生徒に期待する行動を端的に言語化する
- 29 特別活動と連携してアイスブレイクの活動を行う
- 30 攻めと守り,2つの生徒指導を使い分ける
- 31 生徒に声をかける時間帯を意識する
- 第4章 生徒が変わる生徒指導
- 32 怒鳴る指導を学校全体で脱却する
- 33 生徒の気持ちに寄り添う意識の共通理解を図る
- 34 生徒自身がネットトラブルを防ぐシステムを構築する
- 35 生徒会と連携して,生徒自身の力で荒れを改善させる
- 36 学校が荒れているときこそ,生徒本来のよさに目を向ける
- 37 教室や校内の一部のデザインを生徒に任せる
- 38 良好な人間関係を築くために,あそびを有効活用する
- 39 様々な生徒が活躍できるイベントを生徒に運営させる
- 40 ダメもとでたくさんの提案を行い,生徒や教員の意識を前向きにする
- 41 委員会活動の中に,生徒の活躍の場を意図的につくる
- 42 生徒と教員のフォロワーシップを高める
- 第5章 個別指導と集団指導
- 43 学級の中での生徒指導 自主性を尊重し生徒自身に考えさせる
- 44 学校全体での生徒指導 指導の媒体や場を工夫する
- 45 生徒指導だよりや保護者会の工夫で家庭の理解,協力を得る
- 46 教育相談部との連携を図る
- 47 目的や実態に応じて面談を使い分ける
- 48 ロールプレイングを取り入れた参加型の保護者会を行う
- 第6章 こんなことも生徒指導
- 49 毎日のことを丁寧に指導する
- 50 授業中と休み時間の立ち位置を意図的に変える
- 51 給食,清掃活動を通して,相手を気づかう力を育てる
- 52 学級会を通して,自己選択,自己決定の力を育てる
- 53 異学年集団での活動を積極的に取り入れる
- 54 家庭訪問の効果を最大限に発揮する
- 55 学校に通う200日ではなく,365日が生徒指導という意識をもつ
はじめに
「生徒指導主事を任せた」
教員になって6年目の終わりを迎えた3月,次年度の教員7年目の分掌において生徒指導主事(主任)を担当してもらいたいと,当時の生徒指導主事と管理職からお話がありました。
当時28歳,まだまだ学校全体を動かすには若過ぎる年齢での任命でした。
今振り返ると,教員としての力量を評価されたのではなく,荒れた学校だったので,野球部上がりで生徒指導向きっぽいという見た目だけで任命されたような気がします。
「何かあったら相談に乗るから」
「任せた」と言われた2週間後,こう言いつつも,当時の管理職は定年退職,生徒指導主事は次の学校へと去られていきました。
机の上に残されたのは,山のような資料の数々。当時の私には何が重要なのかなど何もわからず,不安な状態で生徒指導主事としての1年がスタートしました。教員6年目の1年間は,学年の生徒指導担当として週に1回の部会には出ていたものの,生徒指導主事の仕事の全容は見えていませんでした。それゆえ,「あれもやらなきゃ」「これもやらなきゃ」と悩み,遠回りをしながら仕事に取り組むことになりました。
「自分にしかできない生徒指導主事の仕事があるはずだ」
こう考え,時間の猶予がない春休みに,夜を徹して年度当初の職員会議で提案するための資料づくりに励みました。学校の道しるべとなる,そして自分自身が悩んだときに立ち戻るためのビジョンをつくり,教員7年目の4月の職員会議で様々なことを提案しました。
その提案はうまくいくわけもなく,提案だけで約2時間かかってしまいました。前年を踏襲した取組に加え,自分の思いだけが先走り,まわりの姿が見えていない残念な提案となってしまいました。当時の管理職からは「ビジョンは伝わった。しかし,内容がぼやけていた」と言われ,仕事への熱い思いとは裏腹に,空回りのスタートだったのを今でも鮮明に覚えています。
「生徒指導はマイナスをゼロにすることばかりではない」
当時,勤務校は荒れていて,何かにつけて火消しを行い,生徒指導というとマイナスなものをどうにかゼロに戻すことだと考えていました。しかし,あるとき,管理職から「生徒指導は決してマイナスをゼロにするばかりではない。生徒がプラスになる取組を意図的につくるべきだ」と指導を受けました。そこから,毎週行われる生徒指導部会で「どんな取組で生徒を伸ばしていくか」ということを考えるようになりました。
時間はかかりましたが,徐々に学校は落ち着きを取り戻し,非行に走る生徒や不登校の生徒は年々減り,学力が大きく伸びた学校として評価されるまでに変貌を遂げました。
現在,20代や30代など,若くして生徒指導主事になられる方も多いと思います。生徒指導主事の仕事は,生徒への対応だけでなく,保護者対応,地域対応,提案資料作成,報告業務など多岐にわたります。それゆえ,現場ではその業務をスムーズに遂行する実務力が求められます。
当時20代だった私が悩み,苦しんだ経験は,現在,多くの生徒指導主事が経験されている,あるいはこれから経験されることと思います。現在生徒指導の実務で悩んでおられる方々や,これから生徒指導主事として現場のキープレーヤーとなられる方々にとって,本書が一助となれたら幸いです。
2025年2月 /力久 晃一
-
 明治図書
明治図書- 生活指導主任になり、意識するポイントや心構えなどが実践的に紹介されていて参考になった。2025/3/230代・中学校管理職














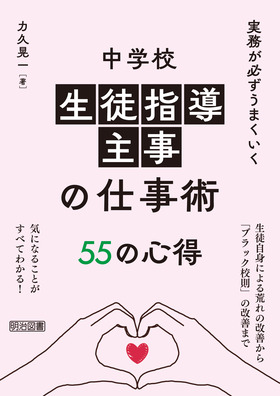
 PDF
PDF

