- はじめに
- 第1章 年度当初の方針を固める
- 01 「チーム数学科」としてのビジョンを示す
- 02 数学科共通の授業規律を決める
- 03 授業開きから,楽しみながら授業規律を浸透させる
- 04 評価方法(知識・技能)を共有する
- 05 評価方法(思考・判断・表現)を共有する
- 06 評価方法(主体的に学習に取り組む態度)を共有する
- 07 数学科内の分担を決める
- 08 成績処理の分担を決める
- 09 お互いに授業を見合う
- 10 お互いの「こだわり」を共有する
- 第2章 若手の授業技術を育てる
- 11 若手の努力を価値づける
- 12 「心構え」を育てる
- 13 「話し方」を育てる
- 14 「聴き方」を育てる
- 15 「身のこなし方」を育てる
- 16 「生徒同士の対話の促し方」を育てる
- 17 「板書の仕方」を育てる
- 18 「机間指導の仕方」を育てる
- 19 「今日のめあての立て方」を育てる
- 20 「班活動への入り方」を育てる
- 第3章 数学科主任自身の授業構想力を高める
- 21 単元の導入で意欲を喚起する
- 22 知識及び技能の授業で見方や考え方を働かせる
- 23 原理・原則を理解する授業に高める
- 24 見方や考え方を授業の目標・まとめにする
- 25 問題発見を中心とした授業を行う
- 26 統合・発展を目指す授業を行う
- 27 自分に適した自習の仕方を身につけさせる
- 28 授業中に自分なりのメモを書かせる
- 29 生徒に振り返りを促す
- 第4章 他教科との連携を図る
- 30 板書の約束事を共通理解する
- 31 宿題の出し方を教科を超えて決めておく
- 32 授業開始の望ましい状態を整える
- 33 他教科とのカリキュラム・マネジメントを図る
- 34 班活動は目的や効果に適したものを取り入れる
- 35 生徒の発表方法の長所と短所を理解して使い分ける
- 36 読み手が追実践できるように学習指導案を書く
- 37 全国学力・学習状況調査で汎用的な問題点を共有する
- 38 働き方改革を促す
- 第5章 地域の数学科研究を推進する
- 39 地域の数学科研究体制を組織する
- 40 近隣校との風通しのよい関係をつくる
- 41 授業研究のテーマを決める
- 42 授業前の学習指導案を検討する
- 43 研究授業で率先して記録を取る
- 44 協議会の司会を務めて議論を深める
- 45 成果と課題をまとめる
- 46 成果発表と現場への還元を行う
- 第6章 率先して新しいことにチャレンジする
- 47 個別最適な学びを実現する
- 48 生徒にレポートを作成させる
- 49 教科横断的な授業をつくる
- 50 反例を活用した探究的授業をつくる
- 51 統合的・発展的に考える授業をつくる
- 52 生徒が数学の「よさ」を価値づける
- 53 生徒が動的図形ソフトを活用して数学的探究を行う
- 54 Less is Moreを具体化する
- 55 生徒にすべてを委ねてみる
はじめに
私は自分の授業が嫌いでした。
自分なりに工夫したつもりでも,考えさせたい論点が伝わらず,生徒にとって魅力のない授業を繰り返しました。授業を基本から学びたいときに支えとなったのは,同僚の先輩方の教えであり,地域の数学科部会からの刺激であり,専門の先生方からの知見であり,研究仲間との切磋琢磨であり,本からの示唆でした。気づけば20年以上も試行錯誤を繰り返しています。
今は,若い先生方が増え,世間の目も厳しくなり,私の若いころよりもさらに不安を抱えながら授業を行っている先生が増えたのではないでしょうか。
そうであれば,若い先生方を支える先輩にこそ,できることがあるはずです。この若手育成の観点1つをとっても,数学科主任を担うベテラン・中堅教師の努力で貢献できる面はたくさんあります。
さて,あなたは数学科主任という立場に対してどんな力が必要だと思いますか。若手育成(第2章)だけでなく,数学科全体の方針を立てて教科経営をする力(第1章),自分自身の日常の授業を高める力(第3章),校内の他教科と連携する力(第4章),地域の研究を推進する力(第5章),新たな授業を開拓する力(第6章)などがその主たるものと考えます。
本書はこれら6つの力をイメージしながら,それぞれを章として55の心得をまとめたものであり,どの章からでも読み始めることができます。
第1章では,年度当初から高い見通しをもつために,どんなことに気配りをすればよいかを示しました。私自身,数学科主任の4月の動き方1つで,数学科全体・学校全体の1年間の意識が変わることを経験してきたからです。
第2章では,若手育成のコツを,特に話し方や聴き方などの授業実践力を中心に示しました。私が千葉大学教育学部附属中学校に勤務したころに,多くの実習生を指導した経験から実感していることをまとめたつもりです。
第3章では,数学科主任自身の日常的な授業を見直し,自分の土台をもう一度見つめ直す内容を示しました。この章は,数学科主任という立場でなくとも,授業力を高めたいという熱意ある数学科の先生方にも参考にしていただきたいと願い,私の実践に基づいてご紹介しました。
第4章では,校内の他教科との連携について示しました。学校全体の研究主任を務めた経験からも,生徒のために全教科で統一するべきこともあります。一方で,授業者の個性を尊重し,工夫の余地を残すことも大切です。
第5章では,地域の研究を推進するためのベテラン・中堅教員の貢献について考えてみました。多忙を極める業務の中で行う実践研究には,少ない時間で大きな成果が出せるようなサポートが求められます。
第6章では,新たな授業を開拓する取組を示しました。本章の内容は,筆者個人の問題意識に沿った内容ですので,一般的ではない内容も含まれているかと思います。しかしながら,数学教育を少しでも前進させようとする心意気だけはお伝えできるのではないかと考え,恐縮ながらご紹介させていただきました。
以上の内容が,読者の先生方の背中を後押しして,授業改善という試行錯誤を続ける同志たちをつなぎ,前に進める一助となることを願っています。
最後になりましたが,企画・出版に際して,明治図書の矢口郁雄氏には大変お世話になりました。また,これまで私に多くの学びをくださった地域の先生方,数学科の先生方,研究仲間の皆様,その他関係者の皆様に心より御礼を申し上げます。
2025年2月 /加藤 幸太
-
 明治図書
明治図書- 数学科主任としての業務内容がわかりやすかった。このような本を求めていた。2025/4/240代・学年主任














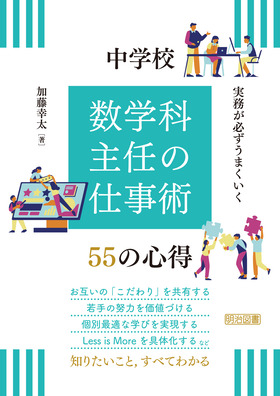
 PDF
PDF

