- はじめに
- 第1章 最も重要な仕事『授業』の準備
- 01 何よりも先に「理科部会」を開く
- 02 仲間の個性を知る機会をつくる
- 03 「チーム理科」で年間指導計画を練り上げる
- 04 単元計画と評価計画を同時に行う
- 05 「できる」を目指して計画を立てる
- 06 生徒になってほしい姿を丁寧に伝える
- 07 特別な教材「教科書」を読み込む
- 08 意図をもって副教材を選ぶ
- 09 デジタル教材を活用する目的を確認する
- 10 消耗品の種類と消耗ペースを把握する
- 11 伝えたいことを考えて生物教材を準備する
- 12 薬品の危険性を教師も生徒も理解する
- 13 今ある備品を大切に使う
- コラム 難しすぎず簡単すぎないから探究にもってこい! 使える課題Ⅰ
- 第2章 授業準備以外も「チーム理科」で行う
- 14 全員満点をとれるように指導してから定期テストをつくる
- 15 チームで教材研究に取り組む
- 16 チームで授業研究に取り組む
- 17 知恵と工夫を集結させて理科室を整備する
- コラム 難しすぎず簡単すぎないから探究にもってこい! 使える課題Ⅱ
- 第3章 理科の授業外でも生徒を力強く育てる
- 18 研究発表会―「ここまでできた」の経験をつくる
- 19 実技コンテスト・実験教室―理科を楽しみ、使う機会を設ける
- 20 地学実習①―周りの教師によさを伝える
- 21 地学実習②―実物ならではの感動を生徒に伝える
- 22 天体観測会―「見せたい」を大切に方法を探る
- 23 校外学習―「+理科」の要素を入れる
- 24 総合的・応用的探究活動―理科の授業での学びを生かす
- コラム 難しすぎず簡単すぎないから探究にもってこい! 使える課題Ⅲ
- 第4章 自分自身を成長させる若手指導
- 25 実習生指導①―まずは単元計画を作成する
- 26 実習生指導②―模擬授業で気付きを促す
- 27 実習生指導③―言葉の重みを意識させる
- 28 実習生指導④―対話を通して思いを伝えさせる
- 29 初任者指導―1年間の重みを意識して育てる
- 30 授業見学①―目的提示の仕方を意識させる
- 31 授業見学②―環境づくりの意図を考えさせる
- 32 授業見学③―評価の観点をもとに指導を見させる
- 33 指導案の作成①―授業の目標を明確化させる
- 34 指導案の作成②―単元計画・評価計画が肝と伝える
- 35 指導案の作成③―本時は単元計画の具体と伝える
- 36 「私ならこうやる」を惜しまず伝える
- コラム 難しすぎず簡単すぎないから探究にもってこい! 使える課題Ⅳ
- 第5章 「チーム学校」の繋がりで深め広げる授業
- 37 他教科連携で学びに化学変化を起こす
- 38 養護教諭との事前の連携で火傷を防ぐ
- 39 養護教諭との事前の連携でアレルギー反応を防ぐ
- 40 用務員の方への感謝の気持ちを忘れない
- 41 体験授業で「理科を学ぶのが好き」の気持ちを育てる
- 42 小中合同研修で小学校での学びを意識する
- コラム 難しすぎず簡単すぎないから探究にもってこい! 使える課題Ⅴ
- 第6章 指導と評価をし続ける教師へ
- 43 自由研究―指導と評価に時間をかける
- 44 調べ学習―「理科」の指導と評価をする
- 45 ワーク―提出する目的を粘り強く伝え続ける
- 46 ノート・ワークシート―成長する姿を評価する
- 47 主体的に学習に取り組む態度①―表面的な態度で評価しない
- 48 主体的に学習に取り組む態度②―生徒に学びを振り返らせる
- 49 思考・判断・表現①―探究活動の中で力を育てる
- 50 思考・判断・表現②―気付かせる実験を用意する
- 51 思考・判断・表現③―課題設定ができる力を育む
- 52 知識・技能―指導とテストを繰り返す
- 53 なぜ「1」や「2」がついてしまったのかを考える
- 54 生徒にとって意味があると胸を張って言える授業をする
- 55 卒業前最後の授業を「理科の修了式」にする
はじめに
「中学校理科教師」
私がこの職業に就いて20年以上になります。私はこの仕事が好きで好きでたまりません。その一番の理由は「『理科』の楽しさ・面白さを直接伝えることができ,伝えたことによる変化・成長を直接見て感じることができる」からです。「理科の楽しさを伝えたい」という思いは,教師となってから今まで変わることのない「教師として働く一番の目的」です。
授業を行うことによって「理科が楽しい」と言う生徒が増えたり,学ぶ姿勢に変化が見られたりしたときに,教師としての「喜び」「楽しさ」「やりがい」を感じるのは,私だけではないはずです。しかし,そう簡単に,何度も得られる感情ではないことを,私は人一倍知っているつもりです。
教師となって最初の5年間の授業は,理科を伝えること「だけ」に,次の5年間の授業は,理科の楽しさを伝えること「だけ」に時間を費やしていました。この最初の10年間,生徒に「理科の楽しさ」が「本当に」伝わっているか,生徒が「授業後に」成長しているかを見取ることができていませんでした。なんとなく理科を伝えた気でいた身勝手な教師だったわけです。
そんな私が,教師としての真の喜びを知り,仕事が好きでたまらなくなった理由は,この教師人生の中で起こった「いくつもの奇跡的な出会い」と「いくつもの衝撃的な言葉」に他なりません。
最初の出会いは,初任校での先輩理科教師です。見せていただいた魅力的な授業と惜しげもなく使わせてくれたワークシートは,今でも私の授業の根幹です。
最初の異動直後に出会った校長先生は,私を様々な研修会・研究会に連れて行ってくれ,その研究会で「出会いの連鎖」が次々と起こりました。
研究会での出会いの連鎖によって,私には多くの研究仲間がいます。定期的に開催している勉強会では,授業改善につながる知識や技能を得るだけでなく,「学び続ける教師」が発する言葉に元気をもらいます。
週に1度,私の授業を参観しに来てくれる副校長先生がいました。授業後の叱咤激励に何度も救われ,励まされました。「学校づくり」の中心が「授業づくり」であることを強く意識したのも,この副校長先生の言葉からです。
今まで職場を共にした理科の同僚の先生方には,もちろん感謝の気持ちでいっぱいです。年下で経験不足な私に理科主任を任せていただいたとき,厳しくも温かいご指導をたくさんいただきました。
理科関連の会議(教科書・書籍・作問等)へ参加させていただいた経験は,全て刺激的でした。特に『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』(令和2年文部科学省国立教育政策研究所)作成の会議への参加は,私の「教師観」を大きく変え,強固にしてくれました。本著で最も伝えたい「授業=指導=評価」について議論を重ねた貴重な機会でした。
そして何よりも奇跡的な出会いは,今まで教えてきた「生徒」一人ひとりとの出会いであり,何よりも衝撃的な言葉は,素直でまっすぐな心のもち主である「生徒」が発する言葉です。「中学校理科教師」にとって,「生徒」は,単に「理科を教える相手」なだけでなく,「教師である理由」であり「教師の目的」であり「教師の喜び」そのものです。その「生徒」が発する言葉(ときに心の叫び)に耳を傾け,その言葉に対して誠心誠意応えていくことこそが,教師として最も重要な仕事だと私は思っています。
今までの教師人生で出会えた全ての教師と生徒が私に与えてくれた「宝物のような言葉」を,私なりに「55の心得」としてまとめさせていただきました。この宝物をまとめる機会を与えてくださった明治図書の江﨑さん,本著を手にしていただいた「あなた」を含め,今までの全ての「出会い」と「言葉」にこの場を借りて感謝申し上げます。
「ありがとうございました」
2025年1月 /髙田 太樹
-
 明治図書
明治図書














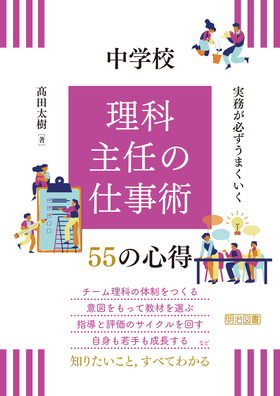
 PDF
PDF

