- はじめに
- 第1章 これからの学級づくり&授業づくり
- GIGAスクールとこれからの学級づくり&授業づくり
- 本質を押さえた1人1台端末の活用
- 端末使用におけるプラスとマイナス
- ―これから考えておかないといけないこと
- 特別な支援を要する子と1人1台端末の活用
- 第2章 成功するロケットスタート! 学級開き&授業開きplus GIGA
- 学級開きplus GIGA
- 出会いの演出
- 1~3年
- 4~6年
- 自己紹介
- 1~3年
- 4~6年
- 端末授与式
- 1~3年
- 4~6年
- 教室環境づくり
- 1~3年
- 4~6年
- 端末活用のルールづくり
- 1~3年
- 4~6年
- 端末活用の保護者へのお知らせ
- 1~3年
- 4~6年
- 授業開きplus GIGA
- 国語
- 低学年 子どもの読みを可視化し,言葉に立ち止まる詩の授業
- 中学年 詩の音読から始まる「ことば」の学習
- 高学年 人物像の「ずれ」を可視化して登場人物の変容を読み取ろう
- 算数
- 低学年 表とグラフを使って,友達のことをいっぱい知ろう!
- 中学年 「かけ算九九のおもしろさ」に迫る授業開き
- 高学年 「数の相対的な見方」を引き出す授業開き
- 社会
- 3・4年 アプリで充実!の授業開き
- 5・6年 まずは検索ツールで授業開き
- 理科
- 3・4年 観察について考えるワーク
- 5・6年 ミニ実験で理科の楽しさを再発見!
- 生活
- バーチャルからリアルへの架け橋としての1人1台端末活用
- 外国語活動・外国語
- いつでも聞いたり見たりできる外国語活動へ
- 特別の教科 道徳
- お互いの違いを知ることから始める
- 第3章 小学校の学級づくり&授業づくりのポイントplus GIGA
- 学級づくりのポイントplus GIGA
- 学級目標
- 朝の会・帰りの会
- 係活動
- 教室掲示
- ミニゲーム
- 長期休み(夏休み・冬休み)
- 学校行事のポイントplus GIGA
- 運動会・音楽会・学芸会
- 授業づくりのポイントplus GIGA
- 国語
- 低学年 子どもが主体的に学び始める読みの「可視化」
- 中学年 「共有する」ことから始まる,学びの広がり
- 高学年 主体的な「協働学習」を可能にする1人1台端末
- 算数
- 低学年 数の図鑑をつくろう(第1学年)
- 中学年 わり算の文章題指導はドット図で(第3学年)
- 高学年 文章の交流で思考や表現を更新させる(第5学年)
- 社会
- 3・4年 見学・まとめでICT活用
- 5・6年 場面によってICT端末の効果を使い分ける
- 理科
- 3・4年 カメラ機能を使おう!
- 5・6年 アウトプット型の授業デザインへ
- 生活
- 1人1台端末ありきで授業をつくる
- 音楽
- 「考える音楽科」を実現するためのICT活用
- 図画工作
- デジタルポートフォリオを作ろう
- 家庭
- 個別最適・効率的に学びを深める活用を
- 体育
- 視覚的に動作を捉える~体育のどこでもドアを目指して~
- 外国語活動・外国語
- これまでの授業にプラスしていく
- 特別の教科 道徳
- 「道徳」でこそ,考える端末活用
- 第4章 仕事を効率的に進めるポイントplus GIGA
- 整理整頓
- スケジュール管理
- 授業準備
- 成績処理
- 執筆者紹介
はじめに
全国一斉にタブレットが配布されて,GIGAスクール構想が急に始まった感があります。現場では,以前からタブレットを使って先進的に進めてきた学校,2021年の2学期になってようやく子どもに1人1台端末(タブレット等)が配られた学校等,様々です。
若手を中心に早くから1人1台端末を使って試験的に取り組んできた先生方もいれば,1人1台端末を目の前にして呆然と立ちすくむベテランもいます。デジタル・ディバイド(ICTにおける情報格差)が起こっているようです。
本来は,ゆっくりと1人1台端末を使った実践を行って,失敗をたくさん積み重ねて質を高めていくべきところですが,コロナ禍でオンライン授業などの必要性が出てきて,そういう悠長なことは言っていられないというのが,実際です。
文科省は,GIGAスクール構想について,
「これまでの教育実践の蓄積×ICT
=学習活動の一層の充実。主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」
という式を示しています。
つまり,これまでの教育実践をすべてかなぐり捨ててICT教育をしろと言っているわけではありません。
ベースは,これまでの教育実践の積み重ねなのだということです。
ICTの授業でよく見られる失敗ですが,機器やソフトをどう使うかが先に立ちすぎて,教材分析や授業づくりがおろそかになっているようです。その結果,ICTは使っているが,学びのない授業になってしまうのです。教科の目標に到達しない授業になるのです。
まずは,教材と目標があって,それについての授業を考えて,そのなかのこの部分についてはICTを活用すればいい,という発想でスタートするべきなのです。
ICT機器が先にあるのではありません。目標と子どもの実態があって,授業を仕組み,そこにICTが加わっていくということなのです。
これらを踏まえて,ICTの実践家のみなさんに,ICTを使ったロケットスタートの在り方や各教科における授業の工夫について,まとめていただきました。
この本が,現場で苦悩している先生方や,新しい教育への工夫について思考しておられる先生方への指針になることを願っています。
2022年1月 /多賀 一郎
-
 明治図書
明治図書- とても参考になった。2023/1/2830代教師














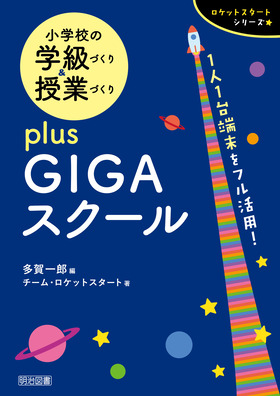
 PDF
PDF

