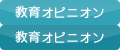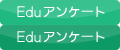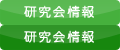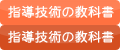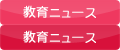- 著者インタビュー
- 国語
題名にもあるように「発問づくり」を意図しています。ですから、この教材にはこの発問をしなさいといったようなマニュアル本ではないということです。だからといって難しい理論が書かれているわけではありません。具体的な発問を示しながら、なぜその発問にいたったかという、まさに「作り方」の本です。内容としては、まず序章として国語科発問の基本的な部分を押さえます。そして、中心は低・中・高学年の文学、説明それぞれの代表的教材をもとにした具体的発問づくりの例です。国語科での発問の多くは、読むことの授業でなされることを考え、読みの教材で発達段階に合わせた典型的な例をあげて、「作り方」を示しました。例としてあげられた教材を授業するときはもちろんですが、この「作り方」は他の教材でも十分に応用がききます。
2種類の発問とは、A「読みの深まりや広がりに重点をおいた発問」、B「読む技能に重点をおいた発問」です。実際の授業においてこのようにはっきりと発問の目的を分けることはあまりないでしょうが、発問づくりを考えたとき、こうやって目前の子どもたちにつけたい力を明確にしておくことは必要です。また、そのことによって、実際の発問づくりがより幅広いものになります。Aは言葉による想像力という読むことならではの授業を意図しています。それに対してBは、言語事項の習得や技能的な面の学習を意図しています。端的にいうならば、Bはより基礎的な能力の育成を目指した授業向きということになるでしょうか。ですから、結果的にAとBを学習者の状況にあわせて組み合わせることによって、より充実した学習活動が構成できると考えています。
教室内の一人ひとりの子ども(学習者)に意味ある学習活動、言語活動を保障する授業を行うことでしょう。若い先生方に限ったことではありませんが…。意味のある学習活動とは、子どもらに言葉の力がついていく活動です。それはこうだという典型的な形があるわけではありません。極端な話、一見活発に討論が交わされているようで内実のないものもあるし、逆に、沈黙の時間が続いていても子どもの内面では活発な言語活動、思考が行われていたりするものです。あるいは一問一答が良くないなどと表面的なとらえで授業は語れないわけです。評価とのからみもありますが、形ではなく、内面的に子どもの言語活動を活発化するためには、とりわけ読むことの授業の中では、やはり発問をどうするかが大きなポイントになるでしょう。はじめに発問ありきではありませんが、こんな活動を行わせたいという授業構想のなかに発問づくりは位置づきます。
自分の言葉に自覚的になることでしょう。無意識のうちに自分の言葉を子どもたちに押しつけてはいないでしょうか。口調ひとつにとっても子どもは自然に真似てしまうものです。発音、発声、言葉遣い、速度などなど、ときに客観的に自省してみる必要があります。極論でいうなら教師の存在そのものが言語環境であり言語教材なのです。国語科だけのことではありません。すべての教科で言葉の教育は行われているのです。日本語で授業を行う教師は皆日本語の教師なのですね。ですから言葉に対する知識を持つことはもちろん言葉に対しての意欲や興味も教師は持つべきでしょう。
悲壮な顔ではなくにこやかに授業はしたいものです。言葉を学んでいくことは楽しいことなのだということを子どもたちに伝えてほしいですね。そのためには教師も言葉を楽しまなくてはなりません。発問づくりにしても、最初からうまくいくわけはありません。子どもってそんなに単純に思い通りに動きません。仮に子どもが思い通りに動いたとしたら、逆に疑うくらいでよいのです。表面的な活動ほど画一的になるのですから。多様な子どもたちに対応するためにこちらも多様性・柔軟性を持たなくてはなりません。逆説的になりますが、発問という授業の狭い一部分を充実させるためには、広い知見が求められるということです。教材をどれだけ深く読み込めるか、発問の対象たる子どもをどれだけとらえられるか。たいへんなことかもしれませんが、それが楽しくなってほしいものです。子どもと同じで、何かをつくりだすというのは、やっぱり楽しいことです。