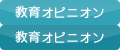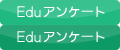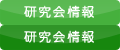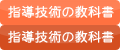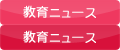- 著者インタビュー
- 学級経営
カウンセリングが教育の分野に導入されて久しいですが、その一部である「傾聴」「共感」のみが強調されてきた経緯があります。確かに、生徒がショックを受け、精神的に不安定になっているときはひたすら傾聴し、その気持ちに共感することが大前提です。私も生徒指導のスタートはそこが重要だと考えます。
しかし、ショック状態を脱した後もひたすら共感のみを続けていくと、生徒を依存状態に陥れたり、立ち上がる力を削いでしまったりする危険性があります。そういう意味で“カウンセリングは学校現場では役に立たない”“生徒を甘やかすばかりだ”などという的外れの批判を許すことになったのだと思います。
教師はカウンセラーではない、という点をしっかりと踏まえる必要があります。生徒も患者ではなく、少なくともある程度健康な状態で登校しています。危機的場面を脱した後は、「健康な人との会話」に戻さなければなりません。それが「対話」です。
「恐れ」を抱かないことです。
生徒は、自分に恐れを抱いてビクビク接している、接したくない、早く会話を終えたい…などと思っている教師の感情に敏感です。すると“自分はまともに相手にしてもらってない”と感じ、怒りをもつでしょう。こうなってしまうと、対話は生まれません。
確かに、危機的場面では教師であっても恐れを抱きます。それでもなお、今何をすることが必要か、生徒にどんな援助が必要かというプロとしての思考を働かせることです。そのような場面が苦手だと感じている方は、ロールプレイ(サイコドラマ)等で訓練し、自分をコントロールする力を付ける必要があると思います。
まず、様々な軋轢や摩擦はクラスの中にすでにあるということです。それを教師が見て見ぬふりをしたり、遠回しに伝えたりするのは危険です。生徒に“コイツ何もしてくれない”“そんな白々しい言い方をしてないで、ハッキリ言えよ”という失望や怒りの感情を抱かせるだけです。また、このようなかかわり方は、“本心をはっきり言ってはいけない”“見て見ぬふりをするのが大事”“知らぬが仏”といった誤った価値観を生徒に植え付けることにつながる、大変危険な要素もはらんでいます。
ぶつかってお互い苦しい思いをしたら、正直に伝え合う。教師も間違ったら謝り、誤解があったら解く。本書にもそんな場面がたくさん描かれていますが、このようにして信頼し合える安心な関係が築かれていくのだと思います。
本書のお話の中心人物である詩織先生は、およそ美しくない、カッコ悪い先生です。でも、生徒たちは詩織先生が大好きです。なぜなら、話すことや態度、表情が気持ちと一致していて「確かな存在」として感じられるからです。確かな存在の人から受け取る言葉によって、生徒たちは自分の存在の確かさも感じるのです。
カッコつけず、一人の生身の人間として生徒の前に立つと、学校生活は毎日ドラマチックなことが目白押しですよ!