- 特集 「読解表現力」を鍛える授業づくり
- 提言・なぜ「読解表現力」が育たないか
- 着実な言葉の力をつけるためにも
- /
- 「読解表現力」という学力の対象とするものは何か
- /
- 「読解表現力」を育てなかった三つの罪
- /
- 読解表現力育成を目指す説明的文章教材の学びの可能性
- /
- 「読解表現力強化プログラム」による学習づくり―(記述力の向上)
- /
- 活用力測定の国語B問題の考察
- 複合的条件設定のもとで〈読み取ったことを書く力〉を求めている
- /
- 条件に応じてまとめる力の育成
- /
- 自分の考えを論理的に表現するための方法
- /
- 「読解表現力」を鍛える授業づくり―小学校
- 「読解表現力」の基本は、正確な作品理解と解釈にあり
- /
- 能動的な読解が、能動的な表現を生む
- /
- 読後文指導で読解表現力をつける
- /
- クリティカル・リーディングの育成
- /
- 「結論」「証拠のありか」「証拠の文や言葉」「解釈」の四点セットで「読解表現力」を高める
- /
- 「比べ読み・重ね読み」で「読解表現力」を付ける
- /
- 「読解表現力」を鍛える授業づくり―中学校
- 「要約力」「問題発見力」「文章構成力」を鍛える
- /
- 「指名なし討論」で読解力も表現力も向上する
- /
- 向山型「分析批評の授業」で、繰り返し鍛える
- /
- 理解と表現の関連指導に着目して
- /
- 教科書教材「紙上討論」を活用する
- /
- PISA型授業を創る工夫
- 小学校/根拠の指摘と根拠の説明の指導を別にする
- /
- 小学校/きまりをみつけ、活用して表現活動に向かう
- /
- 小学校/クライマックスを明らかにすると、読むべき箇所が見えてくる
- /
- 中学校/比べて考えた上で判断する力
- /
- 中学校/学習集団の活用から考える
- /
- 「伝え合う力」を育てる教室づくり (第75回)
- /
- 「読書に親しむ」授業づくり (第75回)
- 「伝統的な言語文化」対応の読書指導
- /
- 書評
- 『新学習指導要領に沿ったPISA型読解力が必ず育つ10の鉄則』(有元秀文著)
- /
- 『読解力マスターカード』小学一年・二年(野口芳宏編著)
- /
- 国語教育人物誌 (第218回)
- 新潟県
- /
- /
- 富山県
- /
- /
- 石川県
- /
- /
- 福井県
- /
- 国語教育時評
- 「論説文の読解表現力」と「文学教材の読解表現力」の学習指導
- /
- 現場訪問 「学力向上の国語教育」最前線 (第135回)
- 「基礎・基本スキルの定着を図る授業創造」
- /
- 学習指導過程の発想の転換 (第3回)
- 実践1 学校に働く自動車がやってきた
- /
- ~短期の「0次」段階~
- 伝統的な言語文化を教える (第3回)
- 教師のための「文字検定問題」
- /
- 「活用型」学力をどう育てるか (第3回)
- インタビューで「活用型」学力を育てる
- /
- 思考力・判断力・表現力等の育成と授業改善 (第15回)
- 思考力・判断力・表現力等の育成と「授業改善」(2)
- /
- ~思考力・判断力・表現力等と基礎・基本の確実な習得~
- なぜPISA型の活用力が必要か (第3回)
- PISA型の弱点をどう克服するか
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…これまでの我が国の読解では表現を求められることが少なかったと言われています。読解と表現が別のものとして教えられていますから、読んだことについて書けと言われたら出来なくて当たり前だとPISA型読解力を分析されてきた有元秀文氏(国立教育政策研究所)は言います。
〇…有元氏は欧米人が読んだことについて意見を書かせる理由は、第一に、読んだことについて個人の解釈や意見は一人一人違っていなければならない。第二は、読んだことについて個人の解釈や意見を書かせなければ、本当に理解したかどうかわからない、というわけです。ですからPISAショックの最大の課題は、特に自由記述問題の無解答率の高さにあると有元氏は著書で明言されています。(『必ず「PISA型読解力」が育つ七つの授業改革』より)
〇…では日本人のコミュニケーション能力をどう高めるか、次の問題点があると有元氏は指摘しています。(1)自己主張が弱く表現が曖昧で、イエスとノーがはっきりしない、(2)根拠を挙げて論理的に自分の意見を言わない、(3)質問ができない、(4)批判ができない、(5)問題解決ができない、などをあげています。
〇…さらに有元氏は日本人の美徳と擁護しながらも日本人の発言の消極的なところを問題としています。そのためには「論理的な表現力」を鍛える必要ありとしています。論理的な表現力の基本は、第一に誰が聞いても納得するような理由と根拠を挙げて意見を書くこと、第二は意見がふらふらと変わらないで、終始一貫していること、第三は意見が飛躍せずに、論理的につながりよく展開すること、としています。(前著作より)
〇…本号は「読解表現力」を鍛えるために授業をどう変え、展開していくべきか、授業づくりの提案を特集として組みました。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















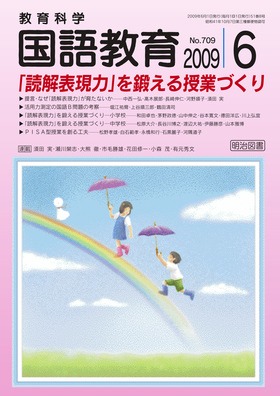
 PDF
PDF

