- 特集 読解授業の面白さを実感させる
- 提言・読解の授業を楽しくするコツ
- 収束的思考の読みを経て拡散的思考の読みへ
- /
- すぐれた発問による落差の解明
- /
- 対話的な読みとその交流を
- /
- 一人の「読解」、集団の「読解」
- /
- 対話的発見型の授業を
- /
- 文学的文章読解を面白くするコツ
- 散歩的読解のすすめ
- /
- 成功の鍵は入念な準備にある
- /
- 説明的文章読解を面白くするコツ
- 明確な理由をもって、発見的に考えることができる発問で授業する
- /
- 難解な文章をグループで読み進める
- /
- 詩や短文を教材にした読解の授業
- 俳句づくりから俳句鑑賞へつなぐ
- /
- イメージを交流し合い、創作を楽しむ
- /
- 読解の授業の「話し合いの場」づくり
- 「自分の考え」+「根拠」を書かせることが、話し合いの場づくりになる
- /
- 「話し合いの場」の五つのパターン
- /
- 話合いをすると読みの力は高まるのか
- /
- 読解の授業を面白くするコツ―小学校
- 学力形成の読解授業を目指す
- /
- 「分析批評」で討論の授業を行う
- /
- 作品世界を構築する物語の読みを
- /
- 教師自身が教材と格闘して楽しむこと
- /
- 限定し、基準を示すと、面白くなる
- /
- 読解の授業を面白くするコツ―中学校
- 「書き換え」学習で読みを深める
- /
- 楽しく和歌を読む―書き換えて自分の読みを発表し合う場を設定して
- /
- 「相互説明」で読みを形成する
- /
- 一つの言葉にこだわって読む
- /
- 読みの学習を面白くする3つのコツ
- /
- 「伝え合う力」を育てる教室づくり (第76回)
- /
- 「読書に親しむ」授業づくり (第76回)
- ホタルの光から読書の光へ
- /
- 書評
- 国語教育2月号臨時増刊『論理的な記述力の開発に挑む』(国語教育研究所編)
- /
- 『論理的な表現力の育成』(野口芳宏編・解説)
- /
- 国語教育人物誌 (第219回)
- 鳥取県
- /
- /
- 島根県
- /
- /
- 岡山県
- /
- /
- 広島県
- /
- 国語教育時評
- 読解授業の「面白さを実感させる」実践の開発
- /
- 現場訪問 「学力向上の国語教育」最前線 (第136回)
- 「活用型学力を定着する授業の創造」
- /
- 学習指導過程の発想の転換 (第4回)
- 実践2 宮沢賢治「雪わたり」から古典の世界へ
- /
- 伝統的な言語文化を教える (第4回)
- 敬語教育は社会人教育の第一歩
- /
- 「活用型」学力をどう育てるか (第4回)
- ディベートで「活用型」学力を育てる
- /
- 思考力・判断力・表現力等の育成と授業改善 (第16回)
- 思考力・判断力・表現力等の育成と「授業改善」(3)
- /
- ~学習意欲の向上や学習習慣の確立~
- なぜPISA型の活用力が必要か (第4回)
- 効率の悪い長時間精読型から効率のよいブッククラブへ
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…岩下修氏(立命館小学校)は新著『教師と子どもの読解力を高める』で、次のように述べています。「最近、読解の授業ほど面白いものはないと思う。子どもたちも、読解の授業が大好きである。なぜか? 読解の授業には、話し合いの場があるからである。自分を表現する場があり、発見的な学びが生まれるからである。」
〇…そのために、どこに重点を置くか、岩下氏は八つの重点を上げています。第一は、漢字・語彙指導。新出漢字の指導は、一―
四年生までは、毎日二個ずつ指導。四年生で六年生の漢字を終えることになる。漢字ドリルを使い、漢字の読みはもちろん、例文も音読させる。国語辞典、漢字辞典を使って熟語、例文を調べ筆記させる。第二は、音読・朗読指導。朝のモジュールタイムの音読、一回七分程度、週に四回。
〇…第三は、文学的文章と説明的文章の読解力指導。物語や詩の読解では、イメージの喚起・形成とともに発見的に理解するという作業をする。起承転結を基本とした構造、全体の要約、主題も検討する。物語や詩の中にある論理も知ることになる。説明的文章では、構文、段落の構成、段落の要約、段落相互の関係、文章全体の構成等を検討させることを軸にした授業をする。文章の至るところに、論理があることを見つけさせる。第四は、読解の指導と一体化した作文力の指導。読解で指導したことを利用させ、作文や日記を書かせる。その他、読解の指導の中での対話力の指導、読解と作文指導の中での文法指導、など。
〇…読解の授業が「大好き」になるための諸提案を集めたいと願い特集を組みました。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















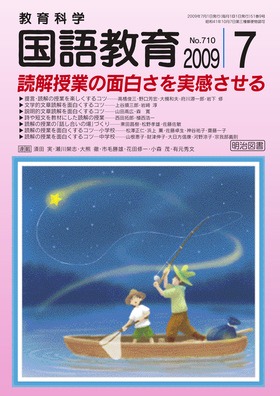
 PDF
PDF

