- 特集 話合い・討論が盛上がる“キー発問”100選
- その「話合い・討論」ホントに必要だった?―私の見た授業から―
- “個”を確立してからグループでの話し合い,そしてクラス討論を
- /
- 子どもの“知的騒がしさ”を誘発する発問を!
- /
- 「どちらが夏で、どちらが冬の写真か」
- /
- コミュニケーション活動自体に意味があるのか
- /
- 子供に「話合い・討論」の力をつける訓練・指導のポイント
- “根拠のある発言”どう訓練・指導するか
- /
- “思考がある発言”どう訓練・指導するか
- /
- “発言のつなげ方”どう訓練・指導するか
- /
- “聴き方”どう訓練・指導するか
- /
- 「話合い・討論」が出来る子を育てる指導のヒント
- 一斉授業 での「話合い・討論」の指導ヒント
- /
- グループ での「話合い・討論」の指導ヒント
- /
- ディベートでの「話合い・討論」の指導ヒント
- /
- 話合い・討論が盛り上がる“キーの発問”とは―私の体験からNo.3
- “発見を促す”キーの発問とは
- /
- “疑問に火をつける”キーの発問とは
- /
- “仮説の検証を促す”キーの発問とは
- /
- “意見を2つに分ける”キーの発問とは
- /
- “多様な意見を刺激する”キーの発問とは
- /
- “まとめ・集約を方向づける”キーの発問とは
- /
- どんな発問で「話合い・討論」にもっていくか―私の体験からNo.3
- 3年/話合い・討論が活性化する“キー発問”一覧
- チョウの一生・土や石・日なたと日かげ
- /
- 4年/話合い・討論が活性化する“キー発問”一覧
- 物のかさと温度・季節と生き物・月や星の動き
- /
- 5年/話合い・討論が活性化する“キー発問”一覧
- 種の発芽と成長・天気の変化と気温・花から実へ
- /
- 6年/話合い・討論が活性化する“キー発問”一覧
- 生物とその環境・物質とエネルギー・地球と宇宙
- /
- 中学/話合い・討論が活性化する“キー発問”一覧
- 恐竜は何類?・食物の養分
- /
- 「話し合い・討論」の新兵器・将来はこうなる
- 電子会議・Eメール・インターネットの可能性
- /
- ここにこんなものが!ユニーク博物館情報
- 日本最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館
- /
- わが理科室と理科準備室・ここが工夫点
- いつでもスタンバイOKです
- /
- 百人一首に登場する動植物 (第7回)
- キク
- /
- なぜ理科が大事か:21世紀の学力から考える (第7回)
- 科学はどのようなものだろうか
- /
- ポートフォリオ:子どものやる気を変える使い方 (第7回)
- ポートフォリオアセスメント事始め(その7)
- /
- 子どもを引き付ける楽しい実験アラカルト (第7回)
- 花から実へ
- /
- 小学校・移行期の理科指導のポイント (第19回)
- 基礎・基本の獲得を目指した第5学年B「物の溶け方」の展開
- /
- 中学校・移行期の理科指導のポイント (第4回)
- 基礎・基本の習得についての方策
- /
- 編集後記
- /
- ご存知“この動物の24時間” (第7回)
- 家族を守るチャボの父親
- /
編集後記
○…授業参観にいって,一番楽しいのは何んといっても子供たちの話し合い・討論が盛り上がる時です.でも最近,そのような授業にであうことが少なくなってきたように思います.
いやな例の代表格かなとは思いますが,授業が行き詰まった時,「じゃあ,みんなで話しあってごらん」というような,いわば,打開をはかるような形で入れる―そんな例も結構あるように思います.
こんな場合,当然,子供の多くはたいていやる気もなさそうに,参観者の方を見たりしている…というような,集中力に欠ける状態が出現する事になる…わけです.
その原因は,子供が変わってきているから,という意見もありますが,でも考えようによっては,その変わった部分に授業をあわせる―ということも,やはり工夫のひとつではないか,という気がします.
例えば,同じ聞くのでも,意見が分かれるような発問をするのと,ただ正解を求めるような発問をするのとでは当然,得られる結果はちがってくるはずです.
授業は発問が命―ともいわれます.まして話し合いや討論ということになると決め手は発問の善し悪しにかかってくることも多いのではないでしょうか.
「この発問より,この発問の方がよい」という事例を沢山ご紹介いただきたいと願いました.
(樋口雅子)
-
 明治図書
明治図書















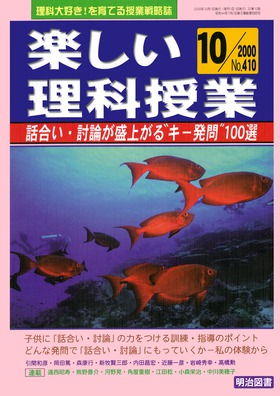
 PDF
PDF

