- 特集 「学び合う」学習をどう創るか
- 提言・支え合い「学び合う」学習とは?
- 子どもの学習をパワーアップする学び合い
- /
- 相互評価・相互判定・相互検討
- /
- 子どもの発疑からドラマを
- /
- 「全員参加」の多様性を支え合う
- /
- 「学び合い学習」の五条件
- /
- 「学び合う」学習をどう創り出したか―低学年
- 互いの顔を見、存在を意識することから
- /
- 子どもたちに黒板を開放せよ!
- /
- あるがままを受け入れ評価者に徹する
- /
- 「学び合う」学習をどう創り出したか―中学年
- 成功体験を核に、意見の違いを認める手だてを
- /
- 毎日「学び合う」作文指導
- /
- 子どもが板書し、発表することで学習の効果は一気に上昇する
- /
- 「学び合う」学習をどう創り出したか―高学年
- 友だちの意見には、必ず反応する習慣を付ける
- /
- マナーの上に成り立つことだ
- /
- 楽しい言語活動を通して学習用語を指導し、育てる
- /
- 「学び合う」学習をどう創り出したか―中学校
- 指名なし討論の第一歩は趣旨説明である
- /
- 「道徳」の授業が正常にできれば、〈学び合う〉学習が成り立つ
- /
- 一日のうちで一番長い時間行われていることを子どもはあらゆるところで再現する
- /
- 学び合う態度・学習集団・授業プラン
- /
- 「学び合う」クラスの土台を築く
- /
- 「学び合う」学習に教師はどう参加するか
- 児童同士も教師も学び合う
- /
- 【率先垂範】的参加
- /
- 学び合う場を作り、確認と評価をする
- /
- 「学び合う」場を創るのが教師の役割である
- /
- 「学び合う」子どもに感動した体験記
- 友達の考えを聞いて自分の考えを変える
- /
- 授業の中で認め合う
- /
- 意図的に子どもたちを鍛えていく延長線上に感動は生まれる
- /
- 熱中・集中した授業づくり
- /
- 教師修業への助言
- 学びの成長なくして授業の成立なし
- /
- 授業研究ニュース (第29回)
- 小学校英語の必修・保護者は賛成70%、教師は40%
- /
- プロの技術を身に付けよう 国語教育の技術 (第5回)
- レポート作成のイロハ「特別支援教育と向山型国語」
- /
- プロの技術を身に付けよう 算数・数学教育の技術 (第5回)
- 優れた技術を継承し発展させる―向山型「赤鉛筆」指導の源流
- /
- プロの技術を身に付けよう 社会科教育の技術 (第5回)
- 教科書を活用し尽くす「6つの展開例」(その5)
- /
- 〜教科書で自学させる(前半)〜
- プロの技術を身に付けよう 理科教育の技術 (第5回)
- 総復習のさせ方は、システムにある
- /
- 「必達目標」達成に教師はどう責任を持つか (第5回)
- 必達目標達成に「責任をもつ」とは
- /
- 子どもを見る目を鍛える (第5回)
- 「子どもの才能」を見つける目(技術)(2)
- /
- キャリア教育がなぜ必要か (第5回)
- フリーター・ニートを育てないために
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…かつて本誌で「学級を学びの共同体として再構築しよう」という呼びかけ特集をしたことがありました。(〇二年十二月号)そこでは「今日の授業不成立が問題になっているのは、子どもの社会的能力・集団的能力・子ども同士の人間関係がうまく育っていないからだ」と主張しました。さらに文科省が進めている新学力観政策は個人主義的な学びが強調されているのではないかと疑問を出しました。自己学習力、自学自習、自己決定、自力学習などを身につけることも大事ですが、学級での集団機能を通して子ども一人ひとりが人格的に陶冶されることに学級教育の目標があるのではないか。そのためにも「共に学び、共に励まし合う」学級における「学び」を一層大事にすべきではないでしょうか。
〇…「支え合い、学び合う学級」の成立を提起した福岡授業改善研究会では、学び合う学習を育てていくヒントを次のように上げています。(1)友だちの発表したことに対しては、すべて反応すること、(2)自分の考えと友だちの考えが違うことを見つけ出させること、(3)自分の考えも友だちの考えと同じであることを見つけ出させること、(4)距離がはなれていても支え合うこと、(5)マイナス面の支え合いからプラス面で支え合うこと、(6)心に響いたり感動したりしたことも大切にすること、(7)教師自身も支え、学び合う活動の場面に入り込むこと。
〇…支え合い、学び合う学習は、実際の授業の場で、多くを体験させ、能力として育てていくことが必要かもしれません。本号は、実際の学習の場での具体的活動例を報告していただく特集です。
-
 明治図書
明治図書















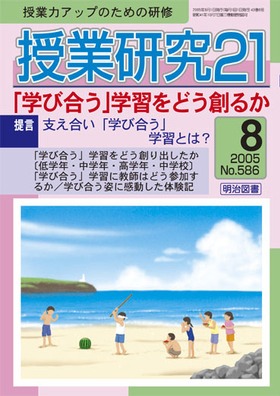
 PDF
PDF

