- 特集 教育改革時代の校内研修・緊急テーマ23
- 教育改革の流れと校内研修の焦点
- 変革期にこそ不易を忘れない
- /
- 研究主任のリーダーシップによる校内研究の活性化
- /
- 学校の自律・教員の意識改革に向けて
- /
- 取り上げたい校内研修のテーマと“研究の現状”―何が何処まで明らかになっているのか―
- 指導要録改変のポイントはどこか
- 絶対評価に耐えられる授業と評価技法
- /
- 絶対評価の規準づくりのポイントはどこか
- 実践を想像しながら結びつける
- /
- 絶対評価と相対評価―特色をふまえた使い方
- 「この評価の目的は」を絶えず念頭に
- /
- 評価方法の改革とポートフォリオの実践
- ポートフォリオ評価の意義と進め方
- /
- 習熟度別編成の可能性と導入の実際
- 学力を保証するために、学校は何ができ、何をしなければならないのか
- /
- 情報化の進展速度と対応のし方
- 子どもたちの学習まで考えてこそこれからの情報化研修!
- /
- 小学英語導入のステップのあれこれ
- 小学校英語導入の3つのステップ
- /
- ボランティア活動導入のステップ
- ボランティア活動をただのイベントにしては、いけない
- /
- TTと担任制の見直しの方向
- 教育改革の重要な拠点としてのTT
- /
- 学校選択制と特色ある学校づくりの方向
- カリキュラムマネジメントの基軸を探る方向性
- /
- 13年度の校内研修 焦点はここだ!
- 指導要録改変と通信簿改革の焦点
- 評価記述の用語、過程評価測定法の研究を
- /
- IT体験の場をどうつくるか
- IT体験研修は必要最低限で効率よく
- /
- 小学英語の場をどうつくるか
- 例示だからこそ しなくてはならない英会話
- /
- 生徒指導のどこをどう改革するか
- 学校に基礎をおくバランスのとれた研修を
- /
- 地域の教材化をどうすすめるか
- 地域の「はてな?」を教材化する
- /
- 特色ある学校づくりと参観授業のあり方
- 学び合う共同体をつくる参画授業へ
- /
- 学校行事のあり方をどう改革するか
- 共生の時代にふさわしい学校行事を
- /
- 校内研修の意識改革と管理職のリーダーシップ―“教職員の親方日の丸意識”とどう向き合うか―
- 「丸投げ」を見直し「議論」を引き出す
- /
- 体質改善は意識改革から―意識改革に向けてのリーダーシップ
- /
- 学校週五日制時代の教師論―そのなかの教員研修は
- /
- わが校の教育環境づくり ポイントはここだ (第1回)
- 植木林の中の“林間学校”
- /
- 不思議の国の教育論議 (第1回)
- 「目的」と「手段」を明確に区別できない不思議
- /・
- 職員室の困ったさん (第1回)
- 「用語」は正しく使おう
- /
- こう変わる こう変えよう教育評価・評定 (第1回)
- 学力への関心の高まりと教育評価
- /
- 校内研究会の戦略と戦術 (第1回)
- 教師への授業診断はカウンセリングマインドで
- /
- 同時進行ドキュメント●校長はどこまで仕事が出来るか (第1回)
- 新世紀はじめの職員会議
- /
- プロローグ―新米校長赴任する―
- /
- ポートフォリオで自己改造―仕事に自信と達成感が持てる作成術― (第1回)
- なぜ,ポートフォリオを作るのか
- /
- アメリカ発 だれにでもできる“校内暴力”対応法―非暴力的危機介入法の理論とエクササイズ― (第1回)
- CPI非暴力的危機介入法を身に付けよう
- /
- 〜学級崩壊・対教師暴力・キレる生徒への危機対応〜
- 文教ニュース
- 21世紀教育新生プランを策定/学校経営に関わる来年度予算
- /
- 編集後記
- /・
- あらふしぎカラーマジック 集中力は生きる力の源である (第1回)
- 創造力を開発して楽しく仕事をしよう
- /
編集後記
○…古くは国鉄の民営化、最近では省庁の改革と、このところめざましい勢いで、戦後ながく続いてきた機構の改革がすすめられています。そのなかでただ一つ課題を残しているのが学校教育の改革だともいわれています。
ところで、公立学校教頭会の機関誌に、
「…独断的・主観的なまとめや提言が多すぎる」とした上で、「“国民会議”の名からはほど遠く、国民的課題と真っ正面に取り組んで検討した形跡が認められない報告の内容を検討すると―」として、「…データによる裏付けや改革の理念の提示がなく、さらに提言相互の整合性もなく」とか、「…気持ちはわからないでもないが、仮に具体化するとして受け皿の問題だけでも実行が困難なことを全くわかっていない」とか、さんざんですが、最後は「…何を言いたいのか不明確などずさんさだけが目に付く」
といった案配で、この提言への批判文は締めくくられています。
ま、いろいろ論議が在ること自体は結構なことだとは思いますが、教育改革がいかに困難な事業であるのか、改めて思い知らされるような一文です。
新年度発足にあたっての校内研修には、このような波にどう向き合っていけばよいのか、ご紹介いただければと願いました。
(樋口雅子)
○…文部科学省は二〇〇〇年十二月十日付で「公立学校長、教頭の登用状況」を発表した。公立小学校、中学校、高校、中等教育学校、特殊教育諸学校の一九九九年度末の定期人事異動後の状況を調査したものだ。それによると校長の新規採用数は五千二百三人(前年度比三十五人増)、教頭は五千七百八十一人(同六十三人増)となり、校長、教頭とも新任者の数が前年度を上回っている。さらに女性校長は四千八十一人となり、戦後初めて四千人を超えたことになる。これからの学校経営には新しい資質が求められており、新任の管理職に大いに期待したい。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















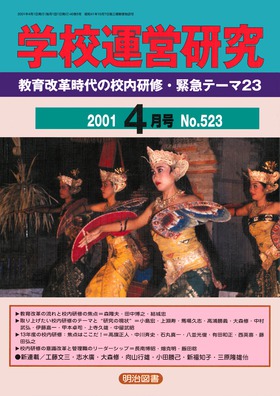
 PDF
PDF

