- 特集 3分で授業に引き込む“導入パーツ18”
- 特集の解説
- /
- 実践事例
- 基本の運動
- 単純な動きを使って、ゲームを仕掛ける
- /
- じゃんけん遊びで楽しく始めよう
- /
- ゲーム
- 変化のある繰り返しで「ジャンケン関所ゲーム」を有効に活用する
- /
- 空間的な動きを身に付けるゲーム
- /
- 器械運動
- 15字以内の指示で超簡単技から
- /
- 導入はテンポよく多くの運動を
- /
- 陸上運動
- 遅れてきたら損しちゃう!
- /
- ラダーロープ(なわばしご)を使った導入
- /
- ボール運動
- 個人技能を高めるシステム
- /
- 3分で授業に引き込むドッジボールの導入パーツ
- /
- 水泳
- 向山式入水のシステムを活用する
- /
- 子供が思わず動きたくなるゲームから始めよう!
- /
- 表現
- 誰もができる動きでゲーム
- /
- ウォーミング・アップの中に「基礎感覚」を育てる運動を
- /
- 保健
- 4年「第二次性徴 身体の変化」は、後ろ向きの男女のイラストで
- /
- 「あれ?」と思わせる導入パーツ2
- /
- 総合的な学習
- 「体操帽子」が大好きになるHPを活用した『健康・安全』の授業
- /
- 最初に全体を動かすとき必要な3つのシステム
- /
- ミニ特集 新学習指導要領「保健」の実践
- 「自分の健康は自分で守る」子供を育てる
- /
- 6年 病気の予防『食品添加物の害』
- /
- 体と心の「うんち」で健康教育を
- /
- 低学年でもできる!十万個の精子の図を使った保健の授業
- /
- 体の成長
- /
- 写真で見る指導のポイントとコツ
- 法則化体育直伝講座
- /
- この指導で子供が変わる
- ライフスキルを学ばせる
- /
- マンガで見る楽しい体育指導 (第21回)
- 根本体育直伝マンガ(開脚前転の巻)
- /・
- できなかった子ができた! 子供に学ぶ成功事例 (第21回)
- ロンダードだって簡単だ!
- /
- これだけは残しておきたい指導技術 (第9回)
- 長なわ跳び ダブルタッチ
- /
- 初心者の体育指導 (第9回)
- けがの可能性を予測する
- /
- 女教師の体育指導
- 「体育が苦手!」克服法
- /
- 健康な生活習慣をはぐくむ保健の授業 (第9回)
- 気持ちは体を変える
- /
- スポーツと健康づくり (第21回)
- ストレッチあれこれ 肉離れ&肩編
- /
- 法則化体育最前線
- 「法則化体育研究会」ML設立
- /
- 全国ネットワーク
- 法則化体育全国セミナーIN広島 参加者の声
- /
- 誌上授業ビデオ診断
- 合同よさこいソーラン
- /
- 運動会にいちおし演技
- よさこいソーラン
- /
- ~かっこよく踊るよさこいソーラン~
- 効果抜群!ファックスできる体育学習カード
- なわ跳び(低学年)
- /
- ~基礎から応用まで楽しく学べるなわとびカード~
- なわ跳び(高学年)
- /
- ~苦手な子供の意欲を引き出すなわとびカード~
- 授業の腕を高める論文審査 (第116回)
- 法則化シリーズの「追試編」を学べ
- /
- 新学習指導要領への提言 (第9回)
- 走り高跳びの指導(2)
- /
- ~基礎技能づくり~
- サークル紹介
- 法則化体育サークル 茨城リズム太鼓
- /
- 読者のページ My Opinion
- 編集後記
- /
- TOSS体育ニュース
- こうすればできる! (第21回)
- スピードにのったバトンパス2編
- /
特集の解説
3分で授業に引き込む“導入パーツ18”
千葉市立弥生小学校
根本正雄
一、ジャンケン関所ゲーム
体育の時間の導入をどうするかという問題がある。全員そろうまで待ってから始めると時間がなくなる。
岡山県の白石周二氏は、体育の導入の仕方を次のように工夫している。
体育館の授業の時は、いきなり「ジャンケン関所 ゲーム」をはじめることがあります。4つのチェックポイント(館内の4つのすみっこ)で誰とでもジ ャンケンし、勝ったら次へ走っていく。単純なルー ルです。
遅れた子はあわててやってきます。ルールが単純 なのでそのままゲームに参加することができます(遅れた分だけ自分は不利になりますが)。遅れたら損をすると感じさせることも大切な指導のように感じています。
いきなりの「ジャンケン関所ゲーム」は有効である。ルールが単純で遅れてきた子供も参加していけるからである。
しかも、「遅れたら損をすると感じさせる」ことができる。損をしないためには、急いで体育館に行かなければならない。
「早く並びなさい」「時間に遅れないように集まりなさい」と言わなくても、子供が進んで行動するシステムになっている。
しかも楽しいゲームである。進んで体育館にいこうという意欲が起きる。
子供にとっては遊びであるが、教師にとっては時間内に集合するというねらいが楽しく達成できる。
導入にこのようなゲームを行なっていけば、子供は喜んで学習に参加するようになる。
二、チャイムと同時に開始する
小林幸雄氏は次のように述べている。
5年団の水泳は、とにかく授業開始が早い。授業開始のチャイムが鳴るや否や準備体操を始め、直ちに入水するという具合だ。始まる時間が早いという ことは、プールでの練習時間がそれだけ確保できることになる。45分間を有効に使うか、これは授業者として大きな問題である。なぜ、そんなに早く子供たちは集まるのか。
それは、システムにある。5年団は、全員集合していなくても、水泳の授業を開始することにしている。
子供は、はやく水に入りたいという気持ちを持っている。それを活用して小林氏は、チャイムと同時に開始するシステムにしている。
「全員集合していなくても、水泳の授業を開始する」原則を貫いている。時間がくれば水に入れるのである。子供は待つ必要がない。
授業の始まりをいつも一緒に行う必要はない。来た順に始めるシステムを作っておくのである。
バスケットボールやサッカーであれば、シュート練習をしている。短距離・リレーであればグランドを走っている。
やることが分かっていれば、子供は動く。楽しく子供が参加できる指導を工夫するのである。
本特集では、白石氏や小林氏のような最初の3分で授業に引き込む導入例が紹介してある。
授業全体ではなく、最初の導入例を具体的に紹介し、その実践には、どんなシステムがあるのかが分析してある。活用して楽しい導入にしてほしい。
-
 明治図書
明治図書















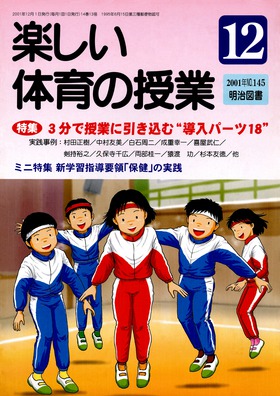
 PDF
PDF

