- 特集 サッカー:教材選択&指導の基本
- 特集の解説
- /
- 実践事例
- ボール蹴り遊び
- (ボール蹴り)楽しいボール蹴り遊びの指導
- /
- (たまご割りサッカー)たまご割りサッカーでサッカーの特性を味わおう
- /
- (シュートゲーム)グループでドラゴンシュートゲーム
- /
- サッカー型ボール遊び
- (ノーラインサッカー)得意な子も苦手な子も活躍できる
- /
- (フォーゴールサッカー)力の差が大きくても楽しめるフォーゴールサッカー
- /
- (ラッキーマンサッカー)女の子が「楽しかった」といってくるゲーム
- /
- (グリッドサッカー)作戦を立てて勝負!
- /
- (トライアングルサッカー)シュートチャンスが増え、パスがつながる
- /
- サッカー
- (ルールの工夫)スモールゲームを繰り返そう
- /
- (ルールの工夫)だれもがしっかり汗をかくルールの工夫
- /
- (コートの工夫)知的な守備を意識するコートの工夫
- /
- (コートの工夫)レベルに合わせて変える工夫
- /
- (作戦の工夫)守備、攻撃の型を作ることから始める
- /
- (作戦の工夫)作戦の工夫が、生きるコートの工夫を。コートは、作戦によって選ぶのだ!
- /
- (個人技能の工夫)向山式サッカー指導法でディフェンス力アップ!
- /
- (個人技能の工夫)5分でできるボール操作基礎運動
- /
- (集団技能の工夫)ワン・ツー・シュートで集団技能アップ
- /
- (集団技能の工夫)だんご状態さようなら、パスは壁当てワンツーから
- /
- ミニ特集 新学習指導要領「表現」の実践
- 新聞を使った体ほぐしから表現へ
- /
- パーツを組み合わせて楽しい表現の授業
- /
- 「向山式阿波踊り」的確な指示と個別評定、そして賞賛
- /
- 用意は簡単!新聞紙とリズム太鼓で
- /
- 絵日記から子供が体験したことをダンスにしよう
- /
- 写真で見る指導のポイントとコツ
- 法則化体育上達講座
- /
- この指導で子供が変わる
- 局面の限定と目標タイムの設定で子供が変わる陸上「リレー」の授業
- /
- マンガで見る楽しい体育指導 (第22回)
- 根本体育直伝マンガ(サッカーの巻)
- /・
- できなかった子ができた! 子供に学ぶ成功事例 (第22回)
- 短距離走の授業づくりで「授業パーツ」を意識する
- /
- これだけは残しておきたい指導技術 (第10回)
- マット運動 伸膝前転
- /
- 初心者の体育指導 (第10回)
- 体育授業もインターネットで
- /
- 女教師の体育指導
- すばやく取り組んでみよう
- /
- 健康な生活習慣をはぐくむ保健の授業 (第10回)
- 水を汚す加害者は私たち
- /
- スポーツと健康づくり (第22回)
- よくあるけがとその手当て1
- /
- 法則化体育最前線
- 準備運動についての論議
- /
- 全国ネットワーク
- 1月13日、沖縄初の体育講座
- /
- 誌上授業ビデオ診断
- 回旋リレー
- /
- 運動会にいちおし演技
- 阿波踊り
- /
- 〜やればわかる!阿波踊りの持つ力〜
- 効果抜群!ファックスできる体育学習カード
- サッカーゲーム(中学年)
- /
- 〜上手なパスでゲームを楽しもう〜
- サッカー(高学年)
- /
- 〜パスをたくさんつなごう〜
- 授業の腕を高める論文審査 (第117回)
- 「法則化シリーズ」「大系」の追試論文から学べ
- /
- 新学習指導要領への提言 (第10回)
- 走り高跳びの指導(3)
- /
- 〜運動課題づくり〜
- サークル紹介
- 法則化体育中学
- /
- 読者のページ My Opinion
- 編集後記
- /
- TOSS体育ニュース (第1回)
- こうすればできる! (第22回)
- コウモリ振り下り編
- /
特集の解説
サッカー:教材選択&指導の基本
千葉市立弥生小学校
根本正雄
1.中学年のサッカー指導
新学習指導要領の中学年のボール運動が、従来の内容と異なり大幅に変更された。
今まではラインサッカー、ポートボール、ドッジボールという種目名が入っていた。
しかし、新学習指導要領ではそれらの種目名がなくなり、サッカー型ボールゲーム、バスケットボール型ボールゲーム、ソフトボール型ボールゲームという名称に変わった。
これは、学校や学級の実態に応じて運動特性に触れさせることを目的にしている。
3年生に必ずしもラインサッカーを指導する必要はなくなった。ボールが蹴れない子供にラインサッカーは無理だと判断したら、別のサッカーを指導していく。
学級の実態にあわせて、教材を選択して指導できるようになったのである。
例えば、ボール蹴りの実態が低ければ、ゴールだけ設定し、ラインは決めないで自由に蹴りあうノーラインサッカーを行なえばよい。
ボールが蹴りあえるようになったら、ゴールを4つに増やしてフォーゴールサッカーを行なう。
どのゴールに入れても得点になる。シュートチャンスを増やして、サッカーの特性であるシュートする楽しさを体験させていく。
また、ラッキーマンを作り優先的にシュートができるラッキーマンサッカーなども考えられる。ボールに触れられない子供にシュートチャンスを作りサッカーの楽しさを体験させていく。
このように、ルールやコートを子供の実態に合わせて指導していくことが新指導要領では求められている。
以上のような中学年のサッカー指導で大切な基本の指導について、本特集では具体的な実践が紹介されている。
2.高学年のサッカー指導
5〜6年のサッカー指導で大切なのは、ルール、コート、個人技能、集団技能などの工夫である。
いきなり11人対11人で行なうのではなく、3対3、5対5などのミニサッカーから入ることが大切である。
いきなり11人対11人で行なうと、ボールコントロールの上手な子供だけが活躍する。逆に一回もボールに触れない子供が出てくる。
また、ボールに集中し、パスがつながらないゲームになる。ボールの蹴り合いになってしまう。
そういう問題を解消して、どの子供も楽しくサッカーができるようにルール、コート、個人技能、集団技能などの工夫を行なっていく。
コートとの工夫では、攻めと守りの範囲を決め行なうグリッドサッカーがある。
攻撃と守備を入り乱れて行なうのではなく、自分の役割を決めて行なうことでゲームが楽しくできるようになる。
また、ゲームを楽しむには個人や個人技能や集団技能を高める必要がある。本特集では、サッカーにおける基礎感覚・基礎技能が紹介されている。
例えば、インサイドステップでは、蹴り足の親指を上に上げるようにするとよい蹴りができる。
ドリブルの基礎技能を高めるには、コピードリブル、バトルロイヤル、追い出しドリブルなどの練習方法がある。
ゲームを行なうと同時にこのような技能づくりを行なうことによって、ゲームの楽しさも深まっていく。
個人技能や集団技能を高める課題ゲームを取り入れていくことが大切である。
本特集では、サッカー指導で大切な5つの基本を実践に即して紹介されている。どの子供にもサッカーの楽しさを体験させてほしい。
-
 明治図書
明治図書















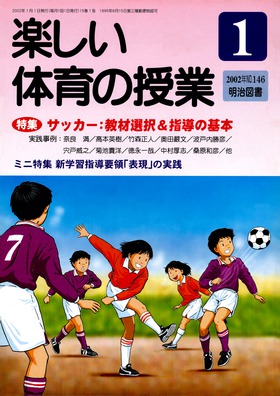
 PDF
PDF

