- 特集 技能を飛躍的に高めるボール運動の指導
- 特集の解説
- /
- 実践事例
- ボール投げゲーム
- ボール投げゲームのバリエーション
- /
- もうこわがらない!みんな熱中の的あてゲーム
- /
- ボール蹴りゲーム
- 3つの発問で「蹴る技能」を高める
- /
- ポートボール風サッカーで楽しく「蹴る」・「止める」をマスターしよう
- /
- バスケットボール型ゲーム
- みんな大好き「シュートボール」
- /
- 楽しみながら技能を高めるポートボールゲーム
- /
- サッカー型ゲーム
- こうすれば、女子もサッカー型ゲームが大好きになる!
- /
- 基礎技能を高めるウォーミングアップドリル
- /
- ベースボール型ゲーム
- ティーボールで打つ技能を高める
- /
- 細かな指示で技能アップ
- /
- バスケットボール
- 3種目をローテーションさせ、基礎技能を高める授業
- /
- みんなが熱中しながら技能を高める授業
- /
- サッカー
- フリーマンサッカーで戦術的行動を高める
- /
- ミニゲームと個別評定で技能を高める!
- /
- ソフトバレーボール
- ルールの工夫とオーバーハンドパスの習熟が大切
- /
- ボールに多く触れさせよ
- /
- ハンドボール
- どの子もできるようになるジャンプシュートの指導
- /
- 子供が熱中するハンドボール型ゲームは
- /
- ミニ特集 新学習指導要領への提言「サッカー」
- できた! 楽しい! を保障する
- /
- 技能をしっかり身に付け、ゲームはシンプルなルールで!
- /
- キープ力アップが組織的なサッカーを生む
- /
- 運動量を保障し、自然な流れで上達させる
- /
- 柔らかいボールタッチとボールキープ
- /
- ライブで体感!TOSS体育講座
- TOSS体育の重要な研究分野「向山型体育」
- /
- レベルアップ!ここが体育授業のポイント
- 「分かる」を大切にした球技の授業を
- /
- マンガで見る楽しい体育指導 (第58回)
- 根本体育直伝マンガ(トライアングルサッカーの巻)
- /・
- 1秒・1cmの記録アップはこの指示で起こす
- あと10cm腰を落としてよさこいソーラン名人!
- /
- 集中・熱中このゲームが子供を変える
- くるくる輪っかゲーム
- /
- 障害児体育の実践 (第10回)
- 選択とハンデでどの子も楽しめるボールリレー
- /
- 体育を好きにする女教師の体育指導 (第10回)
- 「自分の鉄棒」を決めよう
- /
- 子供が喜ぶ体育授業のシステム化 (第10回)
- 水泳の授業システム
- /
- ~教師の指示を通す~
- 効果絶大 インターネットの活用
- 一枚の写真がT君の動きを変えた
- /
- 健康な生活習慣を育む食の授業 (第10回)
- ホテルの朝食でどっちを選ぶ?
- /
- 時代の流れに対応した「性教育・エイズ教育」 (第10回)
- 抗レトロウィルス剤がエイズ治療を変える
- /
- TOSS体育研究会報告
- 校内一のやんちゃ君が応援団長
- /
- TOSS体育最前線
- 徹底指導!―「向山型跳び箱指導法」
- /
- 効果抜群!ファックスできる体育学習カード
- サッカー遊び(低学年)
- /
- ~ボールと仲良くなろう~
- サッカー(高学年)
- /
- ~ブルーシートゴールでコースをねらったシュート力アップ~
- 今、子供に伝えたい保健の指導
- シンナーの害をきちんと教えよう!
- /
- ライフスキルと健康教育 (第34回)
- 認知を変える「ひとりの時間」(2)
- /
- 授業の腕を高める論文審査 (第153回)
- 研究論文は、もっと明瞭な報告を!
- /
- 体育科における学力保障 (第22回)
- 猿渡功氏のボール蹴り遊びの指導
- /
- 読者のページ My Opinion
- 編集後記
- /
- TOSS体育ニュース (第37回)
- テクニカルポイントはここだ! (第34回)
- 走り幅跳び2
- /
- ~空中姿勢が距離を伸ばす~
特集の解説
技能を飛躍的に高めるボール運動の指導
TOSS体育授業研究会代表
根本正雄
2004年7月のTOSS体育全国セミナーで渡辺喜男氏は、ソフトバレーボールの模擬授業を行った。
ソフトバレーボールの楽しさとして次の二点をあげて展開している。
1.ラリーが続くことの楽しさ
2.スパイクをする楽しさ
その楽しさを保障するために、次のルールを工夫している。
1.ワンバウンドで返す。
2.1回で返すことを禁止する。
3.キャッチマンをおく。
いきなりゲームをしてもラリーは続かない。スパイクも上手には打てない。そこで、次の練習を行った。
1.ワンバウンドパスの練習。
2.ステージの上に1人のって、ワンバウンドパスをする。ステージの上の人はすぐにパスする。
3.スパイクの練習をする。
全体をグループに分け、3つの練習をローテーションして行った。練習の場が移動することによって子供には変化が生まれた。
固定した場所ではなく、新しい場所で新しい練習をするので、意欲が湧き、楽しく活動することができた。
チームは一組が4人である。ゲームは3人対3人で、1人が得点係である。少人数のため、1人のボールにタッチする回数も多くボールに触れる、スパイクを思い切り打つという目標が達成されていた。
村田斎氏はシュートゲームの模擬授業を行った。コートに跳び箱を2台設置して、跳び箱にシュートする。
自陣の跳び箱には当てられないように守る。反対に相手のチームの跳び箱に当てるようにしていく。
跳び箱に当てたら1点になる。得点係が得点番に点を入れていく。
このシュートゲームは熱中して活動していた。なぜなら、攻防の切り替えがひんぱんに行われたからである。
跳び箱の後ろからもシュートできるように設置されているので、動きが多様になる。作戦によって動きが変わっていった。
たくさんシュートできる作戦を工夫させることによって、仲間との関わりが生まれる。どんな作戦が効果的なのかを理解し、シュートのコツが分かっていった。しだいに運動量が多くなり、汗がびっしょりになるほど動いていた。
途中で村田氏は「困ったことはありませんか」と質問した。「なかなかシュートができません」という意見が出された。
そこで、「1人が連続してシュートしても得点にはなりません」という、新しいルールを作った。
このルールで、全員にシュートするチャンスができた。今までは上手な人が中心で活動しシュートをしていた。ところが「連続してシュートしてはできない」というルールによって、全員にシュートできるチャンスが生まれた。作戦タイムがとられ、チーム全員がシュートできる作戦が話し合われた。
全員シュートするには、全員が動いていかなければできない。運動量が多くなった。ボールをもらうために動きが多くなったのである。
本特集では、渡辺氏や村田氏の実践のように、技能を飛躍的に高めるボール運動の指導例を紹介してある。
授業に取り入れて活用してほしい。そしてよりよい方法を開発していってほしい。
-
 明治図書
明治図書















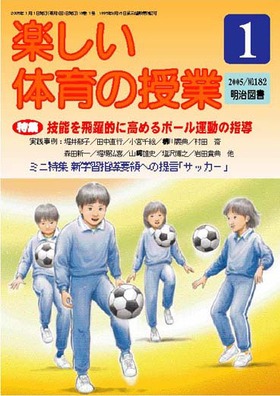
 PDF
PDF

