- 特集 仲間とつくる楽しい学級活動
- 提言・係活動の活性化・どう図るか
- 見通しを明確にし評価による達成感を
- /
- 能動性をいかに引き出すか
- /
- 自由の空気が、係り活動を活性化させる やりたいことをやりたい人が企画する
- /
- 「褒める」ことで創造的な活動を促す
- /
- キャリア教育の視点からも「関心」「意欲」の向上を
- /
- 子ども同士の結びつきを深める工夫
- 小学校/自分のやりたい係をつくらせ、活動させる
- /
- 小学校/私の繰り返したことは「チャレラン」と「遊び」の二点である
- /
- 小学校/高学年男女の仲をよくする遊びを
- /
- 中学校/アサーション・トレーニングでアサーティブに
- /
- 中学校/すぐれた教材と教具が自然な形で子ども同士の結びつきを深めてくれる
- /
- 学級の係活動を上手に進める工夫―小学校
- 子どもの心に響く話・仕組み
- /
- 「所時物の原則」「確認の原則」「激励の原則」で係活動は活性化する
- /
- 子どもの見方や考え方を変容させて係活動の充実を図る
- /
- 係り活動を様々にサポートする
- /
- オンリーワンの係活動―園田雅春学級から学ぶ!―
- /
- 学級の係活動を上手に進める工夫―中学校
- 《減点法》から《加点法》に、教師の発想を変えてみる
- /
- TOSSランドの教材・教具・資料にヒントがいっぱいある
- /
- 活動を評価すると活性化する
- /
- すべてを任せずに、フォローを入れながら
- /
- 居場所作り、評価・確認を!
- /
- ふしめを作る学級行事でありたい
- クラス全員が一つの目標を達成する
- /
- 心・頭・体の学び達成
- /
- トラブルを恐れずむしろ計画的に生かす
- /
- 楽しいクラスをみんなで創る (第3回)
- かかわり合いの中で成長する子ども
- /
- 心を育てる言葉かけ
- 教えてほめ、教えてほめる
- /
- 学級づくりへの挑戦 (第3回)
- 小学校/教師対子どもの関係をほめることで作り出す
- /
- 中学校/担任である私の働きかけと、生徒のがんばりがネットワークの線で結ばれ始めた
- /
- 小学校の道徳授業をどう変えるか (第3回)
- ルールの意義を教える②
- /
- ~世界の法律の起源を探る~
- 中学校の道徳授業をどう変えるか (第3回)
- 「らしさ」「らしく」を教えよ
- /
- 子どもの対人関係能力を高める (第3回)
- フィンランドの教師は修士だから優れていると思っていませんか
- /
- 学級経営をめぐる最新課題 (第3回)
- 学級像の具体化
- /
- 編集後記
- /
編集後記
○…子ども同士の連帯感は、言葉のやりとりではなく、具体的な活動を通してこそ生まれると先輩教師たちは言います。特に学級の仲間たちとつくる楽しい学級行事の活動は一層、仲間との連帯を熱くし育てるといわれています。学級の発展をうながす「学級行事」はふしめを作るともいわれており、そのふしめをどう作り出し、前進の場とするか、教師の力量がためされるわけです。
○…子ども同士の結びつきを強める工夫が期待されますが、そのためには「個性を伸ばし認め合う活動」も期待されています。その自由なグループで励まし合う活動も大切となるでしょう。
○…現場教師の集団活動を通して自主性を育てるために、次の三つの指導が紹介されていました。第一は、子ども一人ひとりに目的を持たせ、役割を自覚させる。第二は活動の手立を具体的な形で認め、励ます。第三は高学年の場合、全校に目を向けさせるために、学級生活を基礎にして活動の喜びを与える、というものです。(『集団意識が広まる』坂本昇一氏ほか監修より)○…「係による学級文化の創造を」と呼びかけた秋田健一氏は、係と当番を意識して区別すべきだと主張されていました。その結果、工作係、遊び係、なぞなぞ係、新聞係、探検係などが生まれたといいます。係活動における教師の仕事について秋田氏はさらに次のように指導していく必要があるといいます。それは「係を決定するのにあたっては例を示す」必要があるということです。さらに停滞している係にはアイデアを出してやることも必要だ、というわけです。その上に、時間を確保してやることも一番大変なのだ、と強調していました。
○…本号は、楽しい学級活動をつくるための実践を集めたいとする特集です。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















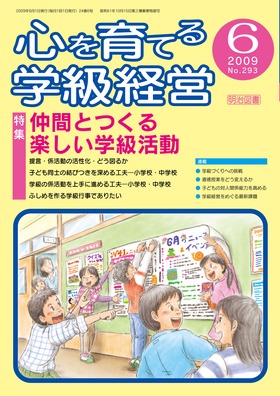
 PDF
PDF

