- 特集 学力保証への射程◇いま、学力問題とは何か
- 「学力低下」「ゆとり」論議の対立構造
- /
- タランモンハ タラント イワナ アカン―徹底した推敲指導で学力保障を
- /
- 確かな算数・数学の学力をどのように育てるか
- /
- 第28回にんげん実践研究集会
- 基調報告
- 生活を見つめ、共に生きる『にんげん』実践を創造しよう
- /
- 記念講演
- メディアの裏側から見た部落差別
- /
- 分科会総括
- 違いを認め合うことの大切さからより豊かな仲間づくりへ
- /
- つらいことを出し合い、支え合える集団に
- /
- ちがいを認め合うなかまづくりをめざして
- /
- 子どもの主体的な学びを育てるための実践をめざして
- /
- 人権総合学習の仕掛け作り
- /
- 本物にふれる人権総合学習
- /
- 心に響く出会いを創ろう
- /
- 全体総括
- 気づき、考え、感じ取り、そして人権へ!
- /
- 追悼・小沢有作先生
- 小沢有作氏の逝去を悼む
- /
- 小沢先生の急逝を悼む
- /
- エピグラフ
- 続く故郷の拒絶
- 〜徳永進著『隔離 故郷を追われたハンセン病者たち』(岩波現代文庫、二〇〇一年)三〇三〜三〇五頁〜
- 座標
- いま、三池を考える
- /
- 米国同時多発テロ事件の読み方
- その歴史的背景から
- /
- 調査に見る 素顔のいまどき高校生 (第6回)
- 生徒様は神様です
- /
- 「自己発見工房」―細うで奮せん記 (第4回)
- /
- 〈世界〉を読む・〈世界〉を感じる―異文化の風に乗って (第12回)
- 終わりのはじまり
- /
- 【資料】「伏見区小学校事件に関する専門家会議」報告書
- /
- 編集後記
- /
編集後記
▽教育現場は、来年四月実施の新学習指導要領にもとづく教育課程づくりに大わらわである。文部科学省は、完全学校五日制の実施を控え、「総合的な学習の時間」の導入を目玉とする、「新しい学力観」による「ゆとりと充実」を標榜する学校改革を唱導してきた。だが、出口の見えない深刻な経済不況のなかで、大学生の学力低下問題に端を発した大学人による「学力低下論」が、教育亡国論としてジャーナリズムを席巻し、その原因を文科省のすすめてきた小・中学校の「ゆとり教育」に求め、公立学校教育への不信感をあおる論調へ変質してきている。周知のように、学力低下論も実証的なデータに乏しく、学習時間の減少などの指摘で学力水準や学力内容・構造論は、あいまいなままに展開されている。指摘されている学習意欲の喪失状況も、つめこみ教育で克服することはできないはずである。解放教育の学力論は、人権感覚に根ざした生き方と真理と真実にもとづく豊かな学びを統一して追究してきており、共にグローバルに生きることを支え励ますための学力の内実を明らかにし、その学力形成の道筋と教材開発・授業改革、人権総合学習と教科学習とを有機的に関連づけるカリキュラムづくりに取り組んできた。本特集では、今日の学力低下論を克服するためにも、学習指導要領・教科書の学力観を批判的に検討し、二一世紀を生き抜くために求められる、学力保障の核心である学力と質と水準を明らかにしていく視座と方法論を検討した。今後、活発で生産的な論議を巻き起こすために、それぞれの領野からの問題提起をお願いした。
▽さる七月三一日、大阪市同教、大同教と当研究所との共催で第二八回『にんげん』実践研究集会が成功裏に開催された。本号には、基調報告、記念講演、各分科会総括、全体総括を収録した。執筆者をはじめ研究集会の運営に携わられた皆様に心より感謝したい。なお、報告原稿の編集は、実践研実行委員会事務局が担当された。
-
 明治図書
明治図書















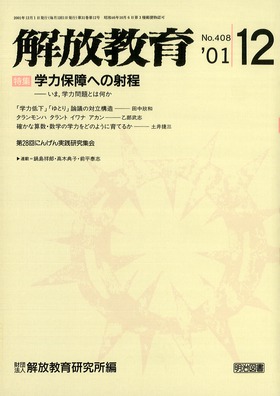
 PDF
PDF

