- 特集 あの子ができた!TOSS開発の指導パーツ26
- できない子ができるようになった26の事実
- トッププロが作った基本の指導(型)を学び、使いこなせるようにすることで、できない子もできるようになる
- /
- できない子ができるようになるのはなぜか
- 自然に変わるということはない 教育の営みの中で子どもは変わる その意味で教師の力量がすべてといえる
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【体育】
- 1 跳び箱が跳べない子ができるようになった事例
- 腕に体重をかける感覚を向山式で忠実に体感させることが重要
- /
- 2 さかあがりができない子ができるようになった事例
- くるりんベルトによって、くるっと回る感覚を実感させる
- /
- 3 二重跳びができない子ができるようになった事例
- 二重跳びがAさんに自信をつけた
- /
- 4 側転ができない子ができるようになった事例
- 側転ができるようになった事例
- /
- 5 25m泳げない子ができるようになった事例
- 5日間で背泳ぎができる方法
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【国算】
- 6 意見が発表できない子ができるようになった事例
- 声が小さい子の指導
- /
- 7 うまく板書が写せない子ができるようになった事例
- 「趣意説明」「アイテム」「教えてほめる」で板書が写せるようになった指導法
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【算数】
- 8 くり上がりのあるたし算ができるようになった事例
- A君に必要なのは、教えて褒めること
- /
- 9 かけ算九九が定着していない子ができるようになった事例
- 九九表を渡し、問題を解きながら九九を定着させる
- /
- 10 くり下がりのあるひき算を減加法で教えたら分かった事例
- シンプルな基本型を示すこと
- /
- 11 仮商をたてるわり算ができない子ができるようになった事例
- 仮商をたてるわり算の必勝法!「間違いを恐れさせない」
- /
- 12 およその数で混乱している子ができるようになった事例
- 書き方の基本型を示すことで、乗り越えさせる
- /
- 13 文章題を面積図で教えてできるようになった事例
- 問題を解きながら習熟させていく面積図の指導
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【国語】
- 14 漢字が覚えられない子ができるようになった事例
- お手本を示しながら繰り返した指書き指導
- /
- 15 漢字のまとめテストが極端に悪い子ができるようになった事例
- ほめ続けることで書けるようになる
- /
- 16 「てにをは」を間違う子ができるようになった事例
- 小さな成功体験を積み重ねる
- /
- 17 音読でつっかえてしまう子ができるようになった事例
- 苦手な子を調べ、音読の回数を保障する
- /
- 18 詩文がなかなか暗唱できない子ができるようになった事例
- 細分化し見通しを持たせる暗唱指導のパーツ
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【理科】
- 19 実験や観察が苦手な子ができるようになった事例
- とにもかくにも実験をして「理科好き」にさせること
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【社会】
- 20 調べ学習が苦手な子ができるようになった事例
- 調べる内容・方法・表現方法を教える
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【理社】
- 21 暗記が苦手な子ができるようになった事例
- 「授業」という「エピソード」で楽しく記憶させる
- /
- 22 ノートを見ていい小テストでできるようになった事例
- わからないところをできるようにするための形成的テスト(プレテスト)で学力向上
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【図工】
- 23 何を描いたらいいか分からない子ができるようになった事例
- 情報を限定し、どこから描くかを教える
- /
- 24 色を塗るときに失敗する子ができるようになった事例
- 色をぬる指導3つのステップ
- /
- できるようになった子どもたちの事実26の現場報告【音楽】
- 25 リコーダーが吹けない子ができるようになった事例
- 「細分化の原則」に徹し、運指指導の組み立てを工夫する
- /
- 26 簡単なリズムが取れない子ができるようになった事例
- 参照と反復練習で、リズムがとれるようになる
- /
- ミニ特集 子どもコンクールの有効活用伝授します
- 「手紙作文コンクール」
- /
- コンクールは学習とリンクさせる
- /
- 命を救うボランティア 献血俳句コンテスト
- /
- 意義とテキストのよさを伝え、まずは申し込む
- /
- 最先端課題への取り組みは、大きな力となる
- /
- 地域の宝をPRする「子ども観光動画」
- /
- 作品応募は日々の延長線
- /
- 授業の原則 (第16回)
- 個別評定の原則(3)
- /
- ~子どもたちの動きを変化させるプロの細分化~
- 授業の力量をみがく (第16回)
- 全国学力テストの実施が突き付けた教育委員会制度の穴
- /
- ~全国学力テストは来年度全面復活へ~
- 編集前記
- /
- グラビア
- 元総理、議員、文科省キャリア 向山氏の講演に学ぶ 第2回「親学」推進議員連盟総会 衆議院議員会館 2012.4.20 ほか
- 佐藤式工作法 (第62回)
- 授業過程が一目でわかる構造図
- /
- ~どのようにしてつくるのか~
- 全国ペーパーチャレラン (第242回)
- ルール・応募方法
- /・・
- 矢じるし迷路チャレラン
- /・・
- (4月号)ランキング/応募者からの手紙
- /・・
- 教科指導の基本
- 国語 (第16回)
- 「根拠」+「考え」 討論がかみ合うノートの書き方を教える
- /
- 算数 (第16回)
- いきなり授業に突入!作業から入る
- /
- ~「3割増」となった算数教科書では、学年末になっても教科書が終わらず、家庭学習にしたり、他教科の授業を算数にしている教室も多い。効率よい授業は、はじめに作業から入るのだ。~
- 理科 (第16回)
- 感動の理科授業を作るための「授業作り」のポイント7
- /
- ~小森栄治氏直伝の教材研究で、安心、安全、感動の理科授業を作ることができる。~
- 社会 (第16回)
- 社会科が面白くなる“人物”の取り上げ方
- /
- ~二宮尊徳の授業作りを通して② 教材研究では、時代背景にとことん迫る。~
- 体育 (第16回)
- 水泳指導
- /
- ~のんびり・だらだらな指導をしていないか、我流をチェック!~
- 音楽 (第16回)
- 拍にのる力を育てる「ふしづくり」に挑戦する
- /
- ~グループ活動で、楽しく、知らず知らずのうちに力がつく。~
- 生活指導 (第16回)
- 夏休みの生活指導で熱中
- /
- ~つまらないと思っている高学年の子を熱中させる手立て~
- 道徳 (第16回)
- 討論を取り入れると資料を見る視点が変わる
- /
- ~「見送られた二十球」の授業で5打席連続敬遠の是非を問う。~
- 英会話 (第16回)
- 「五色英語かるた」で教師主導から子ども主導へ
- /
- ~子どもだけで活動する時間を作ることで、教師に余裕が生まれる。~
- 続・向山洋一を追って (第94回)
- [第74巻]『“TOSS授業技量検定”が保障するプロ教師への道』(6)
- /
- ~「黒帯六条件」から「TOSS授業技量検定」へ~
- 向山実践の原理・原則 (第220回)
- 宿題を出す教師は少なくない家庭を破壊している
- /
- 特別支援の授業
- 日本最先端 翔和学園 (第16回)
- 「死とは何か」を授業する②
- /
- 特別支援の授業
- 特別支援教育の課題 (第4回)
- 発達障がいの子どもの保護者のための親学
- /
- 特別支援の授業
- 中学で生まれたドラマ (第16回)
- 向山氏から学んだ「初めてメガネをかける子」への指導
- /
- 笑顔で教えて笑顔でほめる (第16回)
- テキストを使って大いにほめよう
- /
- 医療連携での模擬授業 (第16回)
- 子どもの行動の理解と支援
- /
- ~「感覚統合」の視点で~
- 保護者・教師セミナーで訴えたこと (第16回)
- 「育てる」という視点に立った時、企業と教育は連携することができる
- /
- そうだったのかとわかった授業 (第16回)
- 自然と技術の習得ができる
- /
- 社会貢献活動
- まちづくり活動展開中 (第16回)
- 市の事業を委託される
- /
- わが地域のまちづくり活動 (第16回)
- あれども見えずに気づかせる
- /
- 食育・食卓教育 (第16回)
- 神様に食べ物を供える習慣
- /
- 観光立国教育 (第16回)
- 観光・まちづくり教育全国大会in福島
- /
- 子どものコミュニケーション能力を育てる郵便教育 (第16回)
- 季節限定 夏のお便りテキストと暑中見舞いはがきを授業で活用しよう
- /
- 環境教育最前線 (第16回)
- セミナーに参加して、環境に関する最新の情報を手に入れよう
- /
- 教科書・教具のユースウェア
- 算数教科書の使い方
- 「例題」部分の授業では教師の「指導法の工夫」が必要だ
- /
- 計算スキルの使い方
- 計算スキルでやんちゃ坊主を統率する
- /
- 五色名句百選かるたの使い方
- ドクターも推薦する「五色ソーシャルスキルかるた」
- /
- スーパーとびなわの使い方
- カード シール 一覧表で、子どもが熱中する授業システム
- /
- 新卒時代*挫折をのりこえてきた (第16回)
- 原点に戻って、謙虚な気持ちで学び続けることが大切だ サークルへの感謝の気持ちを忘れずに学びたい
- /
- 学級崩壊からの生還
- /
- 学生時代 (第16回)
- 【TOSS学生の授業修業】日々の授業が一番大切
- /
- 【TOSS学生の授業力】進化する学生模擬授業インカレ
- /
- 全国サークル案内 (第16回)
- 7月
- /
- Free Way 読者のページ
- 編集長日記
- /
- TOSS最新講座情報
編集前記
▼私は跳び箱が跳べない子を、跳ばせることができる―と発言したのは二十代教師の頃、今から四十五年ぐらい前だ。
▼他の学校に招かれ、学校中から集めた跳べない子を跳ばせたのは三十歳の頃。
間もなく、跳ばせる方法を本に書いた。
「向山式跳び箱指導」は全国に広がり、NHKはじめ、ほとんどのテレビ局が特番を組んだ。
▼その当時、日本中で、何百、何千という学校が「跳べない子の研究」をしていたが、成功して、現在も残っているのは「向山型」だけだ。他の研究はすべて消えた。
▼跳べない子の跳ばせ方は、誰でもできる。私の指導時間は、一人あたり三分程度だ。それで、九十七パーセントの子は跳べる。
▼跳ばせる方法はすぐ学べる。TOSS体育のセミナーなどに来れば、十五分で身につけられる。
▼こんなに効果があり、簡単に身につけられる指導法があるのに、日本中に跳べない子がいっぱいいる。
TOSSの教師は担任してすぐ跳ばせるから子どもからも保護者からも感謝される。
▼このような指導技術が、いっぱいある。多くは、全国に名を知られたトッププロの教師によって開発されたものだ。
▼絵画の酒井式など、どの学校でも見られる。一部の美術教師は毛ぎらいしているが広がっている。
何よりも世界の美術界の最高峰、ハプスブルク王家が、酒井式の絵を買いあげた。日本人初だ。作者の中学生のまいねさんは、ヨーロッパの宮廷画家のサロンに招待された。世界の最高峰は酒井式を認めたのだ。
▼立ちはばとびで、十センチ位しかとべなかった主婦を、根本先生は一日で、一メートル以上とばせた。テレビの特集だったこともあり「すごい!」とフィーバーした。
▼このような指導技術を身につけてほしい。まずはさまざまな「指導技術」の存在を知ってもらいたい。
自分のものにするには、自転車にのれるようになるくらいの練習は必要だ。
▼できたらTOSSサークルで学ぶのが確実だ。月一回位だ。TOSSのセミナー等に出るのもいい。体験こそ上達への道だからである。
(向山 洋一)
-
 明治図書
明治図書















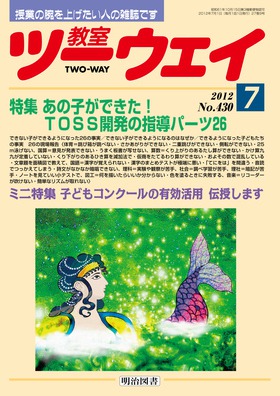
 PDF
PDF

