- 特集 やんちゃ君と対話!教室話術の磨き方
- 子どもに“慕われる語りかけ”と“心が離れる話し方”―違いはここだ!―
- 子どもを加点主義で見ているか
- /
- 「具体的に」を心がける
- /
- 一人ひとりの子どもを大切に、真実を
- /
- 明るいトーンの話し方=教室話術の磨き方
- 学級会―明るいトーンの話し方ポイント
- /
- 朝の会―明るいトーンの話し方ポイント
- /
- 保護者会―明るいトーンの話し方ポイント
- /
- “ここを変える”だけで伝わり方がUPする話術―“話しベタ”度のセルフチェックと改善ポイント
- 発問の仕方―ちょっと変えてみませんか
- /
- 説明の仕方―ちょっと変えてみませんか
- /
- 指示の仕方―ちょっと変えてみませんか
- /
- 注意の仕方―ちょっと変えてみませんか
- /
- “こんなSOS場面”に効果がある対話術
- 忘れ物をした時に効果がある対話術
- /
- けがをさせた時に効果がある対話術
- /
- 嘘をついた時に効果がある対話術
- /
- 野次を飛ばす時に効果がある対話術
- /
- “こんな場面”でする話し方と決めセリフNO.3
- 反抗的場面でする話し方の決めセリフNO3
- /
- 私語場面でする話し方の決めセリフNO.3
- /
- いじめ場面でする話し方の決めセリフNO.3
- /
- やんちゃ君への切り返し=プロ教師の話術
- 勝てない「切り返し」はやめたほうがよい
- /
- 教師の余裕 ―明るく封じこめる
- /
- 想定外の角度と内容で切り込む
- /
- 授業参観で見た!スゴイと思った“あの人の話術!”
- 児童の全ての行動を「受け入れる」とは
- /
- 子どもの心をつかむ教師の接し方
- /
- 話術は、①言葉を確定させる②削る③練習する、ことで身につく―河田学級は、教師の話「0」で、授業が進んでいた!
- /
- 特別支援の子に入る話し方の基礎基本はここだ!
- 子どもを「受容」し、「共感」することが、特別支援を要する子への対応の第一歩だ
- /
- 「理解」「共感」「自己決定」「どうすれば~できた」が発達障がいの子どもたちとの「信頼関係」を作り出す
- /
- シンプルな言葉・目で入れる・触覚で入れる 三つの基本
- /
- “こんな話術”にトライしませんか―“コードスイッチ話法”の有効な使い方
- 教室話術への応用
- /
- “待遇表現”で判別できる!子どもの集団ポジションの見分け方
- やんちゃ君を許す 便乗した子を叱る
- /
- 楽しいクラスをみんなで創る
- 楽しくてたまらない学校生活を
- /
- 教師修業への助言
- それぞれの年代でできることを前向きに
- /
- 体験活動が人生を決める (第11回)
- 長期自然体験の教育的な効果
- /
- 授業崩壊から生還するために (第11回)
- 模擬授業研修をビルトインしよう
- /
- 発達障がいの子どもに学ぶ (第11回)
- 教師は子どもの鏡(ミラー)の存在である
- /
- 授業の知的組み立て方 (第11回)
- 子どもたちが「もっとやりたい」と言った算数の授業
- /
- ~それは「短く、明確で、イメージしやすい指示」で構成されていた〈算数の授業分析 その2〉~
- 子どもの発言を引き出す技 (第11回)
- 発言が出にくい原因と新しい教材
- /
- 実感道徳のすすめ (第11回)
- 「孝・公教育」の重視、再興
- /
- 編集後記
- /
編集後記
○…今となってはいささか旧聞ものですが、
「ノーサイドにしましょう、もう」
どじょう宰相・野田氏は、この言語技術で視聴者の心をわしづかみしたといわれています。ここ、普通は、「もう、ノーサイドにしましょう」というところですが、一呼吸おいての、「もう」が、うんざりしているみんなの共感を呼んだというわけです。
生い立ちの貧しさも、単なる貧乏物語ではなく、「貧しかったけれど夢も希望もあった時代」のイメージを共有しようという語りだと、梶原しげる(アナウンサー)氏はいいます。
さらに梶原しげる氏は、プレゼンの心得としてよくいわれるのは、
・ロゴス(論理性)
・パトス(情熱)
・エトス(信頼性・人柄)
の3つのバランスだといわれるが、25年間辻立ちして獲得した話芸はこのバランスの絶妙なうまさにつながったと分析しています。
もちろん、話芸で宰相が務まるわけのものでないことは当然ですが、人心を掌握しなくては事が始まらないこともまた、事実です。
教室の宰相?でもある先生に、子どもの心をつかむ教師話芸が必要なことは言うまでもないと思います。
最近、ある著名な方の授業を見学していて、こんなことに遭遇しました。
その先生の授業はもう、完璧といっていい完成度だと思って見ていたのですが、「あれ、緊張が途切れたかな?」と思った一瞬、1人のやんちゃ君が私語したのです。
その瞬間を捉える、やんちゃ君の感性も教師の日ごろの訓練の賜物なのでしょうが、その時、授業者は、
「俺も真剣にやっているんだ」と。
未だかつて聞いたことがない、忘れられない発言をしたのです。
やんちゃ君を真剣に授業に立ち向かわせる決めセリフなのではないかと思いました。
本号はそんな具体例を沢山ご紹介いただきました。
(樋口 雅子)
-
 明治図書
明治図書















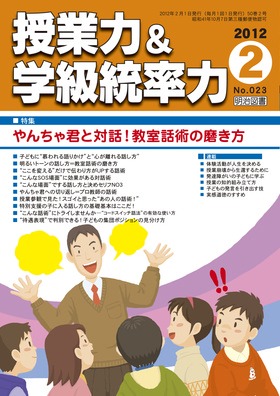
 PDF
PDF

