- 特集 支援を縦と横につなぐ「個別の教育支援計画」
- 特集について
- /
- 〈巻頭〉子どもの支援をつなぐ「個別の教育支援計画」作成のポイント
- /
- 〈巻頭〉学校の外から見た「個別の教育支援計画」活用のヒント
- /
- 〈巻頭〉「個別の教育支援計画」参考様式とその活用~縦と横で支援をつなぐために~
- /
- 〈実践〉「個別の教育支援計画」で支援をつなぐためのポイント
- 本人・保護者とつくる「個別の教育支援計画」~保護者との信頼関係を築いていくために~
- /
- 校内での「個別の教育支援計画」活用術~サポートを必要としている子どもに適切な理解・配慮・支援を~
- /
- 特別支援学級における「個別の教育支援計画」の縦横連携~美瑛町子育てファイル「すとりーむ」を通して~
- /・
- 高校通級における「個別の教育支援計画」の縦横連携
- /
- 放課後等デイサービスとの「個別の教育支援計画」の横連携~個別の教育支援計画を使って,学校と放デイが一体になる連続した支援体制をめざす~
- /
- 進路先との「個別の教育支援計画」の縦連携~中学から高校へ縦につなぐ「個別の教育支援計画(引き継ぎシート)」~
- /
- グループウェアによる「個別の教育支援計画」の縦横連携
- /
- ESSAY
- みんな人の役に立ちたい
- /
- 写真で見る運動発達支援と教具 (第4回)
- 運動発達の方向性④
- /・
- ~目の運動~
- 発達障害の子どもに役立つ!ちょこっと支援の教材・教具 (第40回)
- 家庭科でちょこっと支援
- /
- 算数の学習に困難のある子どもへの支援 (第8回)
- 算数・数学のつまずきの支援に必要な視点とは?
- /
- 教室の中の愛着障害 (第4回)
- 愛着障害・愛着の問題への支援
- /
- 子ども理解に役立つ!行動観察から始めるアセスメント (第4回)
- 児童期~青年期のアセスメント
- /
- 実行機能の理解と支援 (第8回)
- マインドフルな教育支援
- /
- ハジメテ先生のためのICT活用の授業づくり実践 (第4回)
- リモートを活用した多様な学び方の工夫
- /
- 特別支援教育ほっこり日記 (第8回)
- 教えたくても教えられないもの
- /
- 一度は手にしたい本
- 不登校の歩き方(荒井裕司編著 小林正幸監修)/特別支援教育とアクティブ・ラーニング(涌井恵編著 柘植雅義監修)
- /
- 特別支援教育ステップアップ講座 (第18回)
- 神経発達症での「薬」の考え方・使い方
- /
- S.E.N.S実践の小箱 (第2回)
- 多様性を認め合う学級づくり
- /
- ~あたりまえにしていることを見つめ直す~
- SENS for S.E.N.S (第35回)
- S.E.N.Sになって
- 子どもや保護者の味方になるために
- /
- つながりを大切にして
- /
- 特別支援教育士資格認定協会からのお知らせ
- 編集後記
- /
編集後記
「うちの地域では,すでに,本人・保護者と一緒に作成していますよ。」
「うちの学校では個別の教育支援計画を保護者に見せていないです。」
今号を読まれたみなさんの感想は,このようにさまざまに分かれることと思います。それは,自治体や学校によって取り組み方に違いがあるからです。
みなさんに質問です。「この違いはあってもよい違いでしょうか?」
今回の特集は,「トライアングル」プロジェクト報告,平成30年8月の学校教育法施行規則改正という基本的な考え方の流れの中にある「本人・保護者の意向を踏まえること」,「関係機関と情報を共有すること」を中心に据えた内容になっています。
このことは,障害者の権利に関する条約が国連で採択される動きの中の,「Nothing About Us Without Us.」(私たちのことを私たち抜きに決めないで)という当事者の合言葉と大きく関係します。個別の教育支援計画を作成・活用する際に,忘れてはいけない言葉だと考えています。
今号の事例とみなさんの現場の取り組み方の違いはあってもかまいませんが,この合言葉と平成30年8月の学校教育法施行規則改正により義務となった部分は違ってはいけない部分です。
「私の地域では,それは難しい。」と思われるかもしれません。
行政を長く経験すると,いろいろな方から学校の悪い面を耳にすることが多くあります。しかし,現場をたくさん見てきた私は,「現場によい実践,取組は数多くある。それがみなさんの目に触れていないだけだ。」といろいろな場面で話をしてきました。また,「隣の学校,隣の地域に参考にすべき取組がありますし,あなたのところにもそれがありますよ。」とも話してきました。すべての原稿に目を通し,私が感じたことは,「よりよい個別の教育支援計画の活用方法は現場にたくさんある!」という再確認でした。
本人・保護者と学校がテーブルを挟んで,個別の教育支援計画について話し合いをする姿がどの学校でも見ることができるようになれば,障害のある子どもの教育が大きな変化をむかえることになると確信しています。早くその日が来るよう,今号を活用いただき,学校等の現場での実践が深まることを期待しています。
/田中 裕一
-
 明治図書
明治図書















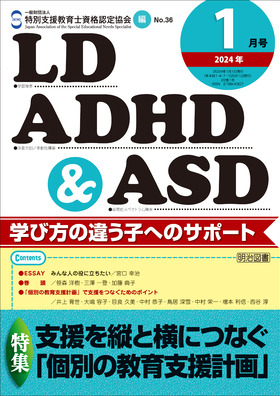
 PDF
PDF

