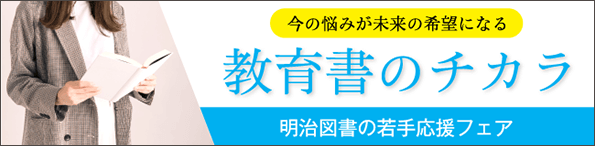- はじめに
- 第1章 まちがいだらけの「集団づくり」
- 1 「全員が深い絆で結ばれた学級」を一足飛びにつくろうとしている
- 集団づくりの手立ての順序性を知ろう
- 2 「子どもを個別に叱ること」で学級を落ち着かせようとしている
- 学級集団としてのゴールを子どもと共有しよう
- 3 「できるだけ教えない」で活動をさせている
- 価値観と具体的な行動を活動の前に示そう
- 4 学級が荒れる原因を特定の「個人」に求めている
- 環境=集団の質を高めよう
- 5 「子どもの実態」を無視して指導方法にこだわっている
- 自らの実践を振り返るシステムをつくろう
- 6 学級の問題の解決を「子ども任せ」にしている
- 集団づくりの土台を築くことから始めよう
- 7 「子どもの自然な成長」を過信している
- おおらかに構えつつ、問題を教育の場面にしよう
- 8 無意識のうちに「目立つ子」だけに関わっている
- どんな戦略を採っても、特定の子だけに関わっていないかを振り返ろう
- 第2章 まちがいだらけの「子ども対応」
- 9 「過去の延長線上」で子どもを捉えている
- 未来のゴールから逆算して子どもの現状を捉えよう
- 10 「厳しく叱る」ことで子どもを変容させようとしている
- 先入観なくゴールを描かせ、それを維持するための働きかけをしよう
- 11 教師も子どもも「成長の限界」を決めている
- 子どもの「自分はこんな人」というマイナスイメージを変えよう
- 12 「減点主義」で子どもを現状に縛っている
- 対症療法と根本的解決方法の両方を意識しよう
- 13 「問題行動を重要視」するために、問題ばかりが見えてしまう
- 教師が重要視することを前向きな方向に変えよう
- 14 子どもに好かれようとし過ぎている
- 子どもに目指してほしい「ビジョン」を示そう
- 15 子どもの長所を「引き出す」ことができない
- 長所を「引き出す」のではなく、「表出される」場を設定しよう
- 16 子どもの自己評価を高める言葉かけができない
- 問題が起きたときほど、よさやがんばりの「事実」を伝えよう
- 第3章 まちがいだらけの「環境・雰囲気づくり」
- 17 教師の余裕のなさから、「マイナスのサイクル」に陥っている
- ゴールとゴールに至る筋道をつかみ、子どもにも示そう
- 18 「平等」ではあるものの、「公平」な学びになっていない
- 「学習の個別最適化」によって、全員の成長を保障しよう
- 19 「個々のがんばりに見合った関わり」ができていない
- 子どもの視点から自分という教師を見直してみよう
- 20 落ち着いた学級を「管理と統制」で実現しようとしている
- 子どもの実態や理想を知るツールをもとう
- 21 「特定の子だけが活躍する」ことが当たり前になっている
- 「スポットライトが当たっている場面」を学級全員分書き出してみよう
- 22 「同調効果」で荒れが広がっている
- 学級の雰囲気づくりのために子どもを参画させよう
- 23 物理的な自由はあっても、「心理的な自由」がない
- 自身のわずかな表情の変化まで自覚し、学級の心理的な自由度を高めよう
- 24 不適切な行動に「注目する」ことで、不適切な行動を助長している
- 保護者の協力も得ながら、適切な行動に注目、称賛しよう
- 第4章 まちがいだらけの「学級システムづくり」
- 25 子どもが「メタ認知」できるシステムがない
- ゴールのイメージと具体的な評価基準を示そう
- 26 「集団」の統率に意識が傾き、「個」を見失っている
- 「個人のゴール」を知り、指導や支援ができるシステムを構築しよう
- 27 「連携して対処すべき問題」を担任が独りで抱え込んでいる
- 様々な関係者と連携しながら子どもを支援するシステムをつくろう
- 28 近視眼的になり、「布石」を打っていない
- 厳しい状況においてこそ、長期的な視点に立った教育も意識しよう
- 29 子どもの「自立」を意識した指導がなされていない
- 「見守る」「待つ」を指導に組み込もう
- 30 「その学級ならでは」の活動や仕組みがない
- 学級経営には多様な内容が含まれることを知り、学級の特色を出そう
- 31 活動の「手段が目的化」している
- 活動のゴールを丁寧に共有、設定し、そこから手段を考えよう
- 32 「保護者との連携」のシステムがない
- 学級経営のゴールを共有したうえで、実践を積極的に発信しよう
- 第5章 まちがいだらけの「行事・生活指導」
- 33 教師に求められる「複数の役割」を意識できていない
- 場面に応じて、教師の役割を臨機応変に変化させよう
- 34 「ダメ出し」で演技の改善を図ろうとしている
- 学級に「ほめ合う文化」を浸透させよう
- 35 教師が「何もかもすべて」行おうとしている
- 方法の工夫で、子ども主体で動く機会を増やそう
- 36 注意を与えるとき、「うまくいかなかったこと」を強調している
- よりよいイメージに慣れ親しむよう導く
- 37 行事や生活指導のように「授業」で力を発揮できない
- 授業方法の知識を基礎から身につけ、意識して活用しよう
- 38 トラブルに目くじらを立て、「犯人捜し」をしてしまう
- トラブルは理想の姿を意識させる好機と捉えよう
- 39 全体が落ち着いていることに安心し、「個々の不満や願い」を見落としている
- 指標となる子の様子に気を配ろう
- 40 「過去につくられた色眼鏡」で、現在の子どもを決めつけている
- 過去の子どもの姿にとらわれず、未来に目を向けよう
- その他の参考文献一覧
- おわりに
はじめに
日々の教育活動から学び続けるために
「学び続ける教師」になることが重要だと言われています。
日々の教育活動を振り返り、反省を行います。自分の教育行為のどこがよくて、どこが悪かったのか、自らを省みます。そして自分の教育行為を改善していくのです。
最高の教育を目指して、絶え間なく改善を続けていく。そのことで、よりよい教育ができますし、教師としての力も高まっていきます。
では、どうすれば、日々の教育活動から学べるのでしょうか。
教師生活を送る中で、様々な出来事に出会い、経験をするはずです。
その出来事から何を学び、今後の教育にどう生かせばよいのでしょうか。
本書は、「日々の教師生活の経験から何を学び、自分の実践にどう生かせばよいのか」を紹介するものです。
私もまた、自らを省みる活動を続けてきました。放課後のだれもいない教室で、1日の出来事を振り返るのが常でした。そして、学びや振り返りを、日記に記録していたのです。
本書では、私自身の経験や、出会った出来事を紹介しながら、そこから何を学び、どう教育行為を改善していけばよいのかを紹介しています。
本書のテーマは「学級経営」です。学級経営に関して出会った出来事や経験したことを、どう振り返り、自らの実践にどう生かしていくのか、「学び続けるとはどういうことなのか」の一端が明らかになるはずです。
教育活動には、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。
成功から学べることもありますし、失敗から学べることもあります。
だれしも自分の失敗を見つめ直すのは辛いものです。だから、失敗から学べる人は多くありません。しかし、失敗の中にこそ、教師生活の糧になることが多々あります。つまり、学び続けるには、失敗を成長につなげるためのアプローチも必要なのです。
本書の構造として、最初に「失敗のエピソード」を紹介しています。続いて、そのエピソードから何を学び、どう実践に生かすべきか(私が何を学び、どう実践に生かしたか)を紹介しています。
本書には様々な人物が登場します。私の経験が主なので、主人公の多くは私なのですが、他の人物も登場します。失敗例が多いこともあり、少し事例をぼやかすために、「三人称」の人物を登場させ、エピソードを紹介するようにしています。
本書が、「学び続ける」ことのヒントになることを願っています。
※本書で示した研究成果の一部は、JSPS科研費 JP 20K03261の助成を受けたものです。
2022年12月 /大前 暁政
-
 明治図書
明治図書- 目的やゴールを共有することがとても大事だと思った。2025/3/7小学校教諭
- 書店で見て、少し中身を読んでみて、これは今の自分に足りないものだ…とはっとして、ついつい購入してしまいました。クラスは何となく回っているけど、もう少し上を目指せないか…そんな思いをもっている方にぴったりです。学級がうまく行かなくなる事例を具体的にあげた上で、それに対するアプローチが様々な視点から書いてある本です。2023/2/1930代・小学校教員
- よい2023/1/720代・中学校教員














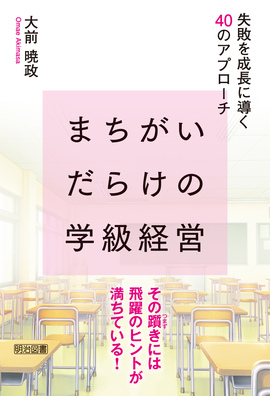
 PDF
PDF