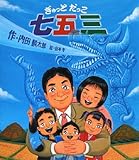
七五三といえば、11月15日に子どもの成長を祝う行事ですが、それが通年行事になりつつあり、さらには行う年齢すらも親の判断によりまちまちになってきていると17日の産経新聞記事が伝えています。親たちの子どもを大切にしたいという気持ちが、本来の意味を失わせてしまっているようです。
七五三とは、そもそも子どもの成長を、陽数である奇数の年に氏神様へ感謝する行事。昔は乳児の死亡率が高く、7歳まで生きることはとてもありがたいことでした。そのため7歳までの子どもは神様からの預かり物という考えが生まれ、陽数ごとに神様に成長のお礼をしていたのです。
11月15日に行う所以は、徳川将軍綱吉の息子の袴着(5歳の男の子のお祝い)がこの日に行われたことから。秋は実りの季節で、神に感謝するお祭りが多く、特に鬼の出歩かない日とされる鬼宿日が旧暦の11月15日であることも、関係があります。
また、七五三に欠かせないものといえば千歳飴ですが、これは子どもの長寿を祈って作られるお菓子。神社で七五三の祈祷をしたあとに分けてくれるところもあり、お祝いしてくれた近所の方などへ子どもが配るものでもあります。
さて、そんな中国の陽数思想と日本の民俗が生んだ七五三。神社では、10月から12月まで祈祷を行っていたり、11月ではすでに寒い北海道では10月が主流となっていたりするようですが、さすがに春や夏の祈祷はお断りするところが多いようです。
春休みや夏休みの時間のある時期に、子どもの負担にならないようにしたい、という親の気持ちも理解できますし、子どもの成長を祝うのに季節なんて関係ないはず。でも、七五三の、何枚も重ね着をする衣装で暑そうな子どもが、祈祷をしてもらえず、形だけの千歳飴を持って参拝だけ済ます、という光景も見られるようで、それもかわいそうかな、と思ってしまいます。
伝統よりも合理性が優先されているかのような七五三ですが、七五三にこだわるということは、まだ親の中に伝統を大切にする気持ちが残っているということ。七五三の本来の意味も考えつつ、子どもの成長を祝う行事として、いい形で残っていくといいですね。

込むのが嫌という気持ちも、秋に神に感謝するなんて気持ちがないこともわかりますね。