- 特集 到達目標を明確にした授業を創る
- 提言・戦後五十年の相対評価から絶対評価へ―教育評価の新時代をどう評価するか
- 子ども一人ひとりの「学習成立」をめざす評価の創造
- /
- 相対評価と「機械的な人数の割り振り」
- /
- 新しい「絶対評価」の意義と問題点
- /
- 越えなければならない苦かい
- /
- 目標に準拠した評価の正念場に!
- /
- 教師の責任の明確化と授業改善
- /
- 到達目標を明確にした授業づくりのコツ―基礎・基本となる言語技能の習得をめざす
- 低学年/音読・漢字・視写の到達度を明確にする
- /
- 低学年/俳句の授業での到達目標と指導
- /
- 中学年/音読できないことには始まらない
- /
- 中学年/向山型算数のノートチェックを応用する
- /
- 高学年/三つの視点から授業をつくる
- /
- 高学年/評価意識・相互評価・自己評価を関連的に機能させる
- /
- 中学校1〜2年/内容をもとに作品を吟味する
- /
- 中学校1〜2年/到達目標の具体化とそのチェックを
- /
- 中学校3年/生徒を見つめる教師の観察眼を
- /
- 中学校3年/やはり分析批評の授業である
- /
- 到達目標を子どもたちに明示する授業づくり
- 学習指導案を変えよ!
- /
- わかりやすく、挑戦しやすい目標を
- /
- 到達目標を明示、評定できる向山型国語の基本システム
- /
- 到達目標への道筋・方法を具体的に示す
- /
- 汎用可能な問いで授業を作ればいい
- /
- 絶対評価の問題づくりーどこに留意するか
- 「話す・聞く能力」診断のためのテストづくり
- /
- 「書く能力」診断のためのテストづくり
- /
- 「読む能力」診断のためのテストづくり
- /
- 参加型板書で集団思考を育てる (第6回)
- /
- 総合的学習を国語学習で支える (第18回)
- 国語科リテラシーの授業開発
- /
- 書評
- 『国語の「基礎・基本」の学び方』(柴田義松編)
- /
- 『書きの力を確実につける』(神戸落ち研・岡篤著)
- /
- 国語教育人物誌 (第138回)
- 青森県
- /
- /
- 岩手県
- /
- /
- 宮城県
- /
- /
- 秋田県
- /
- 現場訪問 「学力向上の国語教育」最前線 (第54回)
- 価値の発見と創造
- /
- 国語教育時評 (第18回)
- 「音読教科書」をどう読むか
- /
- 到達度を見る絶対評価の問題づくり・小学校 (第6回)
- 絶対評価を見えるようにする(2)
- /
- 到達度を見る絶対評価の問題づくり・中学校 (第6回)
- 作文技術の習熟度を総合的に評価する―書くこと(2)
- /
- 「漢字文化の授業」がなぜ必要か (第6回)
- 漢字の学習構造改革―読み先習の取り組み
- /
- 国語の基礎学力とは何か―言語技術教育の視点から考える (第6回)
- 勝田守一氏の「学力」論に学ぶ
- /
- 絶対評価で変わる国語の授業 (第6回)
- 学びの緊張感を生かす絶対評価
- /
- メディア教育の実践課題 (第6回)
- メディア教育の教育内容(3)
- /
- 編集後記
- /
編集後記
戦後五十年続いてきた相対評価を排除し、絶対評価を導入することになったことは、教育評価の一大転換であると加藤幸次氏(上智大)は言います。多くの研究者が指摘されていますように、学習は本来「絶対評価」であるべきであり、そのことを公的に承認したことに大きな意義があります。では、なぜ戦後五十年近く「相対評価」が続いてきたのでしょうか。加藤氏の批判は辛辣です。相対評価の持つ「あいまいさ」が多くの人間にとって「心地よいもの」であったからだ、と言います。つまり良くない評価を受けた子どもたちや親たちをこの「あいまいさ」が救ってくれていた、というわけです。評定1や2でも、それは属している学習集団が優れているからに違いないと解釈できるし、直接「下から何番目」と言われるわけでもない、逆に評定5や4でも、学習集団が優れていないかもしれないし、「上から何番目」かを正確に示したわけでもないから、評価を下す教師をも救ってきたのではないか、と手厳しい評価をしています。絶対評価の導入は、この「まあまあ主義」や「あいまいさ」が許されないことを意味しています。須田実氏が言われるように「目標・指導・評価の相互関連を図る一体化プランによる授業が必須」となります。基礎的・基本的な国語力を育てるために、授業に当たってその起点となる到達目標のチェックを十分に行い、目標到達を図る指導や目標到達としての評価など、そのチェック機能が生きて働くように努める必要があると須田氏は言うわけです。つまり「到達目標と指導」―「指導と評価」―「評価と目標」という循環的な発想が必要となるわけです。最低基準の新学習指導要領の具体化として、「基礎・基本となる言語技能」という観点から言語技能を取り出すべきだという実践者の提言も無視できないでしょう。本号は「到達目標チェック」のある授業づくりの第一回特集です。本誌を裏方で長い間支えてくれた松本幸子さんが本号を最後に退職することになりました。ご苦労を謝し今後のご健康を祈りたい。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















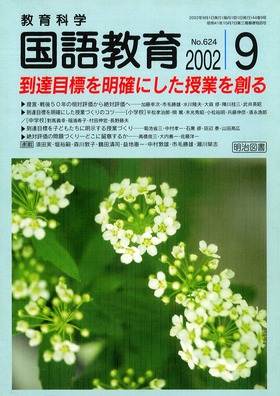
 PDF
PDF

