- 特集 資料&図解で丸わかり!教材研究と授業デザイン
- 1 資料&図解で丸わかり!おさえておきたい教材研究と授業デザイン
- ポジティブな解決志向型授業で新たな文化価値創造の視点を
- /
- 2 「同じ教材での授業」使い方・教え方でここまで変わる
- 実感を持って社会科を学ぶために
- /
- 3 【授業最前線】資料&図解で丸わかり!教材研究と授業デザイン 小学校
- 3年
- 【地域に見られる生産や販売の仕事】社会的事象の背景にある「理論・法則」を意識する~世田谷区の農家の仕事~
- /
- 【市の様子の移り変わり】すぐに日常化できる!教材研究と授業デザインのツボ!
- /
- 4年
- 【自然災害から人々を守る活動】「問いの構造図」をもとに児童たちの社会生活を組み込んだ授業づくり
- /
- 【県内の特色ある地域の様子】無数の単元デザインアイディアは,楽しい教材研究から
- /
- 5年
- 【日本の国土と世界の国々】教師の疑問から授業デザインをスタートする~日本の裏側はどこだろう~
- /
- 【水産業のさかんな地域】既習と関連付け,社会科の見方・考え方を鍛える産業学習~青森のホタテ養殖を具体的事例とし,視点を広げる~
- /
- 6年
- 【世界のなかの日本とわたしたち】板書計画を軸にした授業づくりと単元構想
- /
- 【大陸に学んだ国づくり】中学校の授業も視野に入れ,東アジアとの強いかかわりを実感する授業づくり
- /
- 【わが国の歴史上の主な事象】学習内容と子どもの思考を「架橋」し,探究的な学びを実現する~戦争とくらし~
- /
- 4 【授業最前線】資料&図解で丸わかり!教材研究と授業デザイン 中学校
- 地理的分野
- 【世界の様々な地域】アフリカに「今」何が必要か考えよう
- /
- 【日本の様々な地域】探究的な学びのプロセスを意識する~近畿地方を事例に~
- /
- 歴史的分野
- 【歴史との対話】学校教育現場の実態に合わせた,コンパクトな単元設計
- /
- 【ユーラシアの動きと武家政治の変化】育みたい社会的概念を意識した授業デザイン
- /
- 【近世までの日本とアジア 近世の日本】三段階の教材研究で楽しく学べる近世の単元づくり
- /
- 【近現代の日本と世界】多角的な視点を育て,判断を揺さぶる資料の活用
- /
- 公民的分野
- 【私たちと現代社会】リアルで身近なストーリーをプロデュース!~体操は時代を映す鏡~
- /
- 【私たちと国際社会の諸課題】SDGs完結までのシナリオをつくろう
- /
- 5 【授業最前線】資料&図解で丸わかり!教材研究と授業デザイン 高等学校
- 地理
- 【地図GIS(地理総合)・現代世界の地誌的考察(地理探究)】世界各国官製Web地図サイトの活用
- /
- 歴史
- 【歴史総合】「過去・現在(いま)・わたし」の三視点からの問いとその往還
- /
- 公民
- 【社会保障制度の充実】これからの日本の社会保障制度を考えよう
- /
- 最新情報で徹底解説! どうなる・どうする社会科教育 (第52回)
- 「単元で考える」授業づくり⑮
- /
- 1人1台端末も有効活用!板書&資料でよくわかる授業づくりの教科書 (第52回)
- スーパーマーケットでの売上の工夫とエシカル消費
- /
- ~3年生「店ではたらく人」~
- 「個」の学びを豊かにする!社会科「個別最適な学び」への挑戦 (第16回)
- 「学び方」を,見て学ぶ
- /
- 100万人が受けたい!見方・考え方を鍛える中学社会 大人もハマる最新授業ネタ (第40回)
- 内線,地震,難民下のシリアそして日本
- /
- ~歴史・公民~
- 最新情報でしっかり解説!歴史教育はどう変わるか (第46回)
- 高等学校「探究」科目の実施にあたって(4)
- /
- ~「課題把握」としての「問い」や「仮説」の表現~
- リアルな世界と日本がわかる!地理授業デザイン (第4回)
- 気候変動のリアルと地理授業デザイン
- /
- 多様性と向き合う公民教育 (第4回)
- エンパワーメントから多様性をどう考えるか
- /
- 見方を変えると世界が変わる!「考えたくなる」社会科授業 (第4回)
- アナザーストーリーの社会科授業
- /
- ~「おいしい水道水の安定供給を多角的に考察する」後編~
- みんながゴールに到達できる!課題設定&授業展開スキル (第4回)
- 単元の学習の核になる概念を定める
- /
- 生徒も教師も楽しくなる中学校社会科ゲーム&アクティビティ (第4回)
- [地理/地図を活用した学習内容]宝探しの要素を取り入れた主体的に取り組む態度を養う学習
- /
- 明日の授業づくりに役立つ!学習指導案の理論と実践モデル (第4回)
- 「技能」と「思考,判断,表現」の目標をどう作成するか
- /
- ~目標の理論II~
- 〈全国社会科教育学会の広場〉社会科教育は子どもや教師,社会のために何ができるか (第4回)
- [社会科教育は子どものために何ができるか]子どもの学習レリバンスを保障するために
- /
- ~学習のねらいを共有し,社会に生きる~
- わが県の情報 ここに「この授業あり」 (第304回)
- 新潟県の巻
- /
- 編集後記
- /
編集後記
社会科の授業づくりにおいて,教材研究はとても重要です。文部科学省教科調査官の小倉勝登先生は,『教材研究×社会 実例でゼロからわかる超実践ガイド』(明治図書,二〇二三年)の中で,「社会科は,具体的な事例を通して社会を学ぶ教科であり,授業でどんな社会的事象と出合わせるか,どんな具体的な事例を扱うのか,ここは教師の教材研究にかかっている」と述べられています。また,「学習指導要領の内容ときちんとすり合わせる」ことの大切さも,あわせて指摘されています。
「同じ教材で学力差が出るのはなぜか」という点は,これまでも課題とされてきました。その原因としては,教科書を含めた資料や先行実践の分析やねらいに即した学習問題と発問づくり,その教材を「どのような活用方法」で授業するか,そのユースウェアと言える部分がよく挙げられます。
教材研究と授業の関係も踏まえながら,またそれらをもとに,どのように授業全体を描いていくか,その授業構想・授業デザインが,子どもたちに確かな力をつけるか否かの分岐点とも言えそうです。
そこで本号では,「資料&図解で丸わかり!教材研究と授業デザイン」と題し,各学年や各分野の単元においてどのように教材研究をし,また単元を構想していくか。その基礎基本と,それらを活かした授業づくりのあり方について,実際の教材メモや単元構想図などを入れ,全国の先生方に取り組みをご紹介いただきました。
/及川 誠
-
 明治図書
明治図書- 授業に対して、どのように準備しているのかよくわかり、マネしてみようと思えるような内容でした2023/8/930代・中学校教員















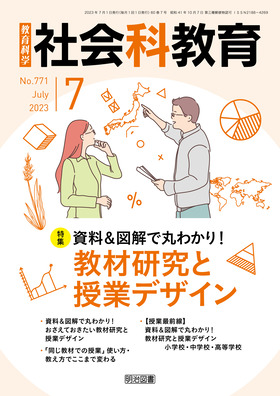
 PDF
PDF

