- 特集 学校が挑戦する基礎学力向上作戦
- 提言・基礎学力向上に賭ける学校への期待
- 学力充実・向上のための総合戦略
- /
- ゆとり教育に別れを
- /
- 競争的刺激を怖れない指導原理
- /
- 年14日間全日、徹底的な研究会を持つ
- /
- 「三者」と連携する評価と指導の一体化
- /
- 基礎学力保障の「説明責任」―問われる指導力
- 子どもの質問力を育成する
- /
- 日々の授業実践の充実で
- /
- 基礎学力保障で問われる校長の指導力
- 教育は人ではなくシステムである。学力の差はシステムの差である
- /
- 小・中一貫の図書館教育の推進
- /
- 基礎学力保障を学校経営方針に
- /
- 基礎学力保障で問われる研究主任の指導力
- 執念が必要、その上に謙虚さ
- /
- 必要な三つの力
- /
- みんなで情報交換の場を
- /
- 現場からの問題提起・学校が挑戦する基礎学力向上作戦
- 校内に基礎学力向上の具体的システムを確立
- /
- 力の入れ方を保護者へ公開する
- /
- 算数は時数を確保し、国語は漢字の読み先習をシステム化する
- /
- 学力公開時代だからこそ学校あげての取り組みが必要である
- /
- 研究授業で提案する
- /
- 国語科基礎学力向上へ向けての全校指導態勢の確立
- /
- 教師の意識が変われば、成果は現れる
- /
- 授業で勝負できる態勢作りをする
- /
- 学力低下への危機意識を自覚することが、出発点である
- /
- 二兎を追う者は一兎をも得ず
- /
- 学校で取り組む学力向上作戦
- /
- 教師修業への助言
- 豊かな情報と情報間の結合
- /
- 授業研究ニュース (第27回)
- 文科相が中教審に指導要領見直しの検討を要請
- /
- プロの技術を身に付けよう 国語教育の技術 (第3回)
- 日本語の授業づくり
- /
- プロの技術を身に付けよう 算数・数学教育の技術 (第3回)
- プロなら「語り」を磨こう―趣意説明・別れのあいさつ
- /
- プロの技術を身に付けよう 社会科教育の技術 (第3回)
- 教科書を活用し尽くす「6つの展開例」(その3)
- /
- 〜絵や写真から入る場合〜
- プロの技術を身に付けよう 理科教育の技術 (第3回)
- 厚みのある「自由試行」をどのように組織するのか(その1)
- /
- 「必達目標」達成に教師はどう責任を持つか (第3回)
- 必達目標で、学校の何が変わるのか(その2)
- /
- 子どもを見る目を鍛える (第3回)
- 子どもの性格を見ぬく技術
- /
- キャリア教育がなぜ必要か (第3回)
- 小学校からのキャリア教育の必要性(その1)
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…文部科学省による教育内容の三割削減に端を発した「学力低下論争」は、ここにきて「ゆとり教育の見直し」にまで発展しつつあります。その間、前文科大臣が出した「学びのすすめ」などという中途半端な通達など机上の空論化しつつあります。結果的に塾と受験産業の復活を促し、家計における教育費の増加という社会的基盤を揺るがす問題となりつつあります。
〇…「基礎学力低下論」は、ドリル学習と習熟度別指導の拡大を促し、さらに少人数授業の増加が学級解体を促進させる可能性すら予測される事態になっています。しかし現実には、「基礎学力の保障」といっても、担任の努力では限界があり、吉永順一校長が提言されているように、「問われているのは学校の態勢であり、校長のマネジメント能力」であるということになりそうです。
〇…国立市の教育長・石井昌治氏が喝破されたように、公教育に課せられた根本的使命に立ち返るべきかもしれません。(『現代教育科学』〇四年六月号)「古来、過ちを改めるに憚ること勿れ、と言う。この期に及んで確かな学力とか不確かな学力とか曖昧なことを言っている場合ではない。気の遠くなるような繰り返しを経て、基礎的で基本的な知識、教養を一つ一つ段階を追って子どもたちに地道に伝えることこそが、学校の荷う社会的使命の中核である。読み・書き・計算等の基礎学力の習得を学校教育の中心課題に改めて据え直す必要がある」(石井氏の言)
〇…伝えられる義務教育改革案にも、義務教育の到達目標の明確化や学校評価システムの確立と教員評価の徹底が上げられています。本号は、学校が挑戦する学力向上作戦の提案を特集するものです。
-
 明治図書
明治図書















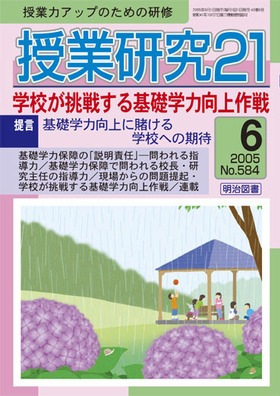
 PDF
PDF

