- 特集 基礎基本重視へ=学校の何を変えるか
- 基礎基本重視へ=“時代の風”をどう受けとめるか
- 「すべての人」に必要なものは何か?
- /
- 道徳の基礎基本を忘れまい
- /
- 歓迎すべき回帰点
- /
- ミニシンポ 教育世論は今“基礎基本重視”を求めている
- 提案/「読売報道」の背景と反響
- /
- 提案を読んで/「7・5読売記事」のコピーは、全国の職員室で配布され、日本中の教育現場に激震が走った!!
- /
- 提案を読んで/自己点検なき教育改革論の不毛
- /
- 提案を読んで/お手軽な「学力低下」批判には御用心を
- /
- ミニシンポ 指導要領は“最低基準”で予想される変革の波
- 提案/「生きる力」教育は基礎基本の充実から
- /
- 提案を読んで/「最低規準」には納得できません
- /
- 提案を読んで/最低基準だから学校はやり易い
- /
- 提案を読んで/たくましい「知力」の形成を
- /
- ミニシンポ 基礎基本重視と新指導要録の波紋
- 提案/目標に準拠した評価をどう充実させるか
- /
- 提案を読んで/もうひとつの評価を活かす
- /
- 提案を読んで/意見というよりもいくつかの提案を
- /
- 提案を読んで/豊かな基礎・基本を豊かな評価方法で
- /
- 基礎基本重視の教育思想=ルーツをたどる
- 「基礎・基本」重視の思想とは何か
- /
- ミニシンポ “基礎基本”のラベルと中味は明確なのか
- 提案/教育課程の次元で学力を
- /
- 提案を読んで/授業の質を上げる方向での論議を
- /
- 提案を読んで/学力構造から見た学力低下と基礎・基本
- /
- 提案を読んで/学力向上は教科書の内容を充実させることだ
- /
- 「子どもありき」の教育思想=ルーツをたどる
- 「かれ自身の作品」(ペスタロッチ)をつくれ
- /
- 基礎基本重視へ=学校が取り組む課題の焦点はどこか
- 習熟度別指導は、パンドラの箱
- /
- 学校における基礎・基本のポイント
- /
- 焦点は習熟度別指導と情報公開
- /
- 読み書き計算の徹底が子供を変える
- /
- わが校の教育環境づくり ポイントはここだ (第5回)
- 心のふれあい感動いっぱい
- /
- 不思議の国の教育論議 (第5回)
- 「個性化・多様化」まで「一律」に推進しようとする不思議
- /・
- 職員室の困ったさん (第5回)
- 危ない橋
- /
- こう変わる こう変えよう教育評価・評定 (第5回)
- 指導要録の改訂と評価の改善
- /
- 校内研究会の戦略と戦術 (第5回)
- シミュレーション授業のすすめ(2)
- /
- 同時進行ドキュメント●校長はどこまで仕事が出来るか (第5回)
- 入学式顛末記
- /
- 周年記念バザーを開く
- /
- ポートフォリオで自己改造―仕事に自信と達成感が持てる作成術― (第5回)
- 評価規準(ルーブリック)誕生の背景
- /
- アメリカ発 だれにでもできる“校内暴力”対応法―非暴力的危機介入法の理論とエクササイズ― (第5回)
- CPI非暴力的危機介入法を身に付けよう
- /
- 〜CPIニュースレターの一部紹介〜
- 文教ニュース
- 指導要録の改善で文部科学省が通知/「生きる力」の育成を総合的に評価
- /
- 編集後記
- /・
- あらふしぎカラーマジック 集中力は生きる力の源である (第5回)
- 創造力には伝播するという嬉しい性質がある
- /
編集後記
○…新年一月五日、読売新聞の一面トップに出た「“ゆとり教育”抜本見直し」「学力向上に力点」という記事ほど衝撃をもたらしたものはない!というのが、率直な感想…というご意見をあちこちで耳にします。
記事の真偽を確かめるべく文部科学省にも問い合わせが相次いだ…ようです。一月二四日、都道府県教育長協議会で文部科学省の小野元之次官は、この問題への説明で、誤解を招きかねない報道があったとしながらも、「ゆとりが過度に強調されるあまり、結果としてゆるみともいえるような状況が一部に見受けられます」と語りました。
これは、どう考えても?!現場に軌道修正を求めている…としか思えぬ発言です。それだけ、新教育課程で創設された総合的学習ともからめて、学力定着への不安が増大してきていたということでしょう…。あるいは、このような形での世論のほうが説得力があった…ということなのかも知れません。
本号は、この問題の発端をつくったというか、流れの方向を転換させるきっかけをつくるのに、大きな役割を果たした、読売新聞の勝方信一編集委員にご登板いただきながら、この問題の背後にある?教育世論が今どう動いているのか、反響などを交えて問題提起していただきました。
(樋口雅子)
○…六月二一日付朝刊の朝日を開いてびっくり仰天。一ページの全面広告には、全寮制の○○中学は「ゆとり教育」を行いません。「ゆとり教育」は子どもの学力を低下させ、日本を三流国家に落とす教育のこと、とあるではありませんか。朝日は広告の宣伝文句にもうるさいと聞いていたし、現に私どもの広告にも注文をつけられた経験があります。
○…今回の広告には何んの疑問も感じなかったのでしょうか。私は「ゆとり教育」の代表格の総合的学習を支持している立場からいえば、この広告には納得できませんでした。「総合的学習」がソバ打ちやカレーを賞味した時は終わっています。「総合的学習」を教科の発展として大いに活用しようではありませんか。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















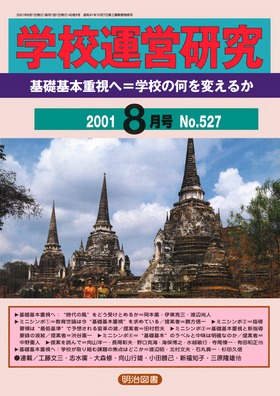
 PDF
PDF

