- 特集 特色ある学校づくり=挑戦者30の提言
- あなたの意見は“賛成・反対・態度保留?”―公立校で“特色ある学校づくり”=正しい選択なのか
- 円周が直径の「3倍」では…特色ある学校など生まれようがない
- /
- 結果(特色)より過程(創出)に意味が
- /
- 理科教育で保護者・生徒を引きつけたい
- /
- 地域に根ざした特色のある学校づくりを
- /
- 体験活動から学ぶ生きる力
- /
- 学校選択制の光と闇
- /
- 形より理念を
- /
- 教育理念を明示し,信を問うシステムを
- /
- 市場原理が否応なく 公立学校にも…
- /
- 記者レポート 動き出した“公立の特色ある学校づくり”
- 欠かせない現場発の地道な取り組み
- /
- 特色ある学校づくり=“挑戦する実践者”の提言
- 学校の教育相談についての提言
- 信頼性を育む教育相談の充実
- /
- 数学授業を英語で―選択教科の提言
- 学校間による智恵比べ。始まったばかりの本校の新たなる挑戦!
- /
- 地域参加型授業の提言
- 「地域を学ぶ」「地域で学ぶ」「地域を生かす」視点に立つ授業づくり
- /
- OBPTA土曜授業の提言
- OBサポートティチャーによる自習指導(PTA企画)
- /
- 習熟度別指導の提言
- 生徒に学習方針を身に付けさせる
- /
- 小学校で教科担任制導入の提言
- 「一部教科担任制」の導入による指導システム改善の試み
- /
- 海外の“特色ある学校づくり”=どんな挑戦が進行中か
- 校区の要望と課題に基づく学校運営(カナダ)
- /
- 「成果を出す責任」を問われ続ける学校(イギリス)
- /
- 長期戦略と学校裁量の拡大(ドイツ)
- /
- 自由化の中のサバイバル(イギリス)
- /
- 特色ある学校づくり=“挑戦する行政マン”の提言
- 経営論的発想に基づく成果基盤型の学校づくり
- /
- 「仕組み」を変えて大胆に発想する
- /
- 地域で育ち 地域を育てる 学校への挑戦
- /
- 若者を育てる街づくり―大学生によるインターンシップ―
- /
- 我ら特色ある学校づくりを支援す!
- /
- ヤング教師が考える“特色ある学校づくり”
- キーワードは義務教育の弾力化
- /
- まず校時表をかえてみよう
- /
- 教師の「志」と「行動力」
- /
- 外と内からの変革で特色ある学校をつくる
- /
- 「読み書き計算」に責任をもつ
- /
- わが校の教育環境づくり ポイントはここだ (第6回)
- 京都市立御所南小学校
- /
- 不思議の国の教育論議 (第6回)
- 「すべての子どもたちに必要なこと」を特定しない不思議
- /・
- 職員室の困ったさん (第6回)
- 何もしらない教師たち
- /
- こう変わる こう変えよう教育評価・評定 (第6回)
- 各学校における評価規準の作成に向けて
- /
- 校内研究会の戦略と戦術 (第6回)
- シミュレーション授業のすすめ(3)
- /
- 同時進行ドキュメント●校長はどこまで仕事が出来るか (第6回)
- 授業研究を改革する
- /
- 研究会を組織する
- /
- ポートフォリオで自己改造―仕事に自信と達成感が持てる作成術― (第6回)
- 評価規準とパフォーマンス
- /
- アメリカ発 だれにでもできる“校内暴力”対応法―非暴力的危機介入法の理論とエクササイズ― (第6回)
- CPI非暴力的危機介入法を身に付けよう
- /
- 〜学校安全管理は,人間の「怒り」理解からスタート〜
- 文教ニュース
- 教育改革関連六法改正が成立/教育研究開発学校を新規指定/学校の安全対策で予算措置へ
- /
- 編集後記
- /・
- あらふしぎカラーマジック 集中力は生きる力の源である (第6回)
- 先生は、みな発明家である
- /
編集後記
○…全国に先駆けて、教育改革計画「プラン21」で学校選択制を導入し、注目を集めている東京都品川区が、二〇〇一年度の活動を「プラン21フォーラム」として報告会を開きました。一〇〇〇人の参加者があり、習熟度別学習や小学校の教科担任制など、特色ある学校づくりが注目を集めたようです。
この品川区のフォーラムを紹介した日本経済新聞の横山編集委員によれば、特色ある学校づくりの“結果がよければ、それを取り入れたいという学校がでてくるのはいわば当たり前の現象”でもあるわけで、“特色ある学校づくりの画一化”が起こりうるといいます。現に、若月教育長はそれをもっとも懸念していると指摘されているようです。
もちろん、公という概念のなかには、すべての人に“等しくサービスをすべき”ということがあったと思います。ですから、“あそこであれをやったら、ウチもやらないと不公平になるかも”という懸念?が横並びにさせていた―ということもあったかも知れません。
この辺についても、本号でどう考えていけばよいのか、ご意見をいただきました。
(樋口雅子)
○…来年の三月をもって「同和」事業の推進を中心とした特別法が期限切れとなる。これをもって「同和」行政・人権行政は終了とする声が一部にあるが、これは大きな間違いである。すでに昨年十二月上旬には、国会で成立した「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」があり、ことしに入って施行されているからである。
○…問題は所管が法務省と文部科学省にかかわっている点、さらには財政上の措置が明確にされていない点など具体性を欠いた法律になっていることである。人権教育・啓発の課題を盛り込んだ地方自治体の行動計画の策定はこれからである。そのためのカリキュラム開発やテキストづくりの早急な取り組みが期待される。「同和」行政の発展・継続をめざし各地で取り組みが展開されているが、私たちも心を新たに行動を起こす必要があるようだ。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















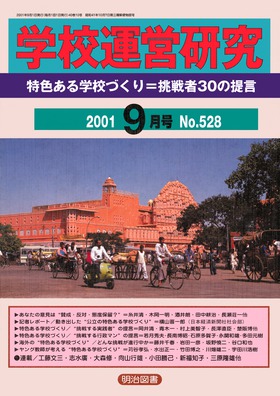
 PDF
PDF

