- 特集 新しい時代“教育情報の読み方・解き方”
- IT活用の情報収集と発信=ここまで変わるポイント
- 「手段が変わる」「目的が変わり得る」
- /
- 教育情報の電子化の光と影
- /
- 情報化時代は、発信する内容を本気でつくることが大切だ!
- /
- 変わってくる学校を取り巻く情報環境:どう対応するか
- “進む地方分権”で学校の情報環境はどう変わるか
- まず見える学校づくりから
- /
- “進む横並び意識の払拭”で情報環境はどう変わるか
- 情報のツーウェイ(双方向性)が活発になる
- /
- “進む外部評価”で情報発信はどう変わるか
- すべては校長の明確な経営方針にある
- /
- アカウンタビリティ・説明責任と学校の情報公開―何をどこまで発信することが期待されているのか―
- 情報公開基準をつくる
- /
- 教育機能拡大のためのアカウンタビリティ
- /
- 保護者・地域等へどのような情報を開示するか
- /
- 学校への要望や関心が生まれる情報開示
- /
- 達人がする“情報の収集・吟味・活用術”に学ぶ
- 歴史人物に学ぶ情報の収集・吟味・活用術―豊臣秀吉
- 情報が富と権力を集中させ天下人を作る
- /
- 人を動かす情報の収集・吟味・活用術―カーネギー
- 声掛けて返事がもらえるうちが“花”だね
- /
- 海外の学校に学ぶ情報の収集・吟味・活用術―イギリス
- 情報公開に基づく学校改善のあり方に学ぶ
- /
- メディア現場に学ぶ情報の収集・吟味・活用術―広告代理店
- 広告代理店の進化・発展とその最前線
- /
- 「この教育情報」から時代を読む=私が思う“一年後の姿”
- “絶対評価”の実現度―私はこう読む
- /
- “絶対評価”の実現度―私はこう読む
- /
- “習熟度別指導”の実現度―私はこう読む
- /
- “習熟度別指導”の実現度―私はこう読む
- /
- “小学校英語”の実現度―私はこう読む
- /
- “小学校英語”の実現度―私はこう読む
- /
- “奉仕活動”の実現度―私はこう読む
- /
- “奉仕活動”の実現度―私はこう読む
- /
- “教育基本法の改定”の実現度―私はこう読む
- /
- “教育基本法の改定”の実現度―私はこう読む
- /
- 役に立つ学校情報のキャッチアップ術 初めて赴任する学校―私がする“情報チェックのツボ”
- まず信頼関係の構築を
- /
- 「人」を知り,「地域」を知ることから
- /
- どういう授業がなされているか
- /
- 情報収集は三つの視点から
- /
- 好感度の学校が発するオーラ=どこが違うか―私が体感した“成功する学校のPR”とは―
- やる気と実感できる表現こそ
- /
- 的をしぼった研究テーマができているか
- /
- 学校の活性化―そのポイント
- /
- 学校の情報化―どんな形で進むか 学校の現場は、未曽有の激変期に入る!
- 若い教師の五年後の予想
- /
- わが校の教育環境づくり ポイントはここだ (第7回)
- 前原市立南風小学校
- /
- 不思議の国の教育論議 (第7回)
- 「心の教育」の中身を議論しない不思議
- /・
- 職員室の困ったさん (第7回)
- 校内研修
- /
- こう変わる こう変えよう教育評価・評定 (第7回)
- 評価の本来の役割を生かす
- /
- 校内研究会の戦略と戦術 (第7回)
- 「良い・上手い授業」参観のすすめ(1)
- /
- 同時進行ドキュメント●校長はどこまで仕事が出来るか (第7回)
- 殺傷事件の教訓
- /
- 休業日に研究会を開く
- /
- ポートフォリオで自己改造―仕事に自信と達成感が持てる作成術― (第7回)
- 知識は自分でつくる
- /
- 〜「知識構築型の学び」への転換〜
- アメリカ発 だれにでもできる“校内暴力”対応法―非暴力的危機介入法の理論とエクササイズ― (第7回)
- CPI非暴力的危機介入法を身に付けよう
- /
- 〜生徒同士のケンカ場面への対応を知ろう〜
- 文教ニュース
- 教科書問題で日本と韓国・中国関係が悪化/総合規制改革会議が「校長公募」など提言
- /
- 編集後記
- /・
- あらふしぎカラーマジック 集中力は生きる力の源である (第7回)
- 教師が作る教材・教具は思いのほか商品化されやすいのだ
- /
編集後記
○…いくら何でもあんまりよ―きっと森前総理は嘆いているのではないかと思うほどの小泉人気のようです。同じ自民党で、しかも森派出身なのに…と。要因はいろいろあるのでしょうが、要は小泉氏が良く見える・見たいというオーラ・好感度を感じさせる何かがあるのでしょう。いつまで続くかはともかくとして、このようなオーラを発することは、現代のような情報化時代にリーダーシップを必要とする職にある人にとっては、必要不可欠な能力ではないか…と思います。
ま、昔から、“あばたもえくぼ”といわれてきたわけですが、坊主にくけりゃ袈裟までにくい…というたとえ通り、風向きが変わればころりと態度が豹変することは間々あることではあります。
このような、いわゆるピープズパワーなるものも、当てに出来ない?要素があることは、確か…なのですが、そこにもっとも作用しているのが、いわゆる第四の権力といわれる情報産業の旗振り?があることはいうまでもないことです。ここに、メディアリテラシーということが特に大事だと言われる今日の社会の大きな特徴があるのではないかと思います。
ま、メディアとの上手なつきあい方も、情報公開時代に生きる教育現場人の大事な資質となりつつあるのかも知れません。
(樋口雅子)
○…最近の文部科学省は主張に一貫性が無いような気がする。三割カットの新学習指導要領に対する批判がマスコミを通じて「学力低下」批判の大合唱になるや学習指導要領に定めた学習内容は最低基準だと言い出している。その上、進んだ子に対しては、「発展学習」のための教材を用意すべきだと言う。新学習指導要領が最低基準ならば、全員がクリアをめざすしそれを学校教育が保障しなければ公教育としておかしいことになる。さらにクリアしたあとの対策は、ということになる。これまで遅れがちな子に重点を置いてきた政策の大転換といえる。地方分権を言うならば、まず法的拘束力を撤廃したらどうか。
-
 明治図書
明治図書















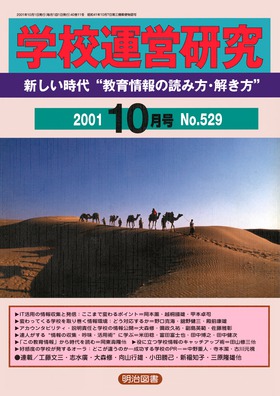
 PDF
PDF

