- 特集 絶対評価への転換―緊急対応の重点23
- 絶対評価への転換―私が考える意識変革の“特効薬”
- 他に何が変わるのか?
- /
- 個の成長を見守る眼差しを送り続ける
- /
- 絶対評価は授業で子どもを活かす
- /
- 絶対評価への転換―校内体制でバックアップの可能性を探る
- 習熟度別指導への対応―少人数学級の活用ポイント
- 習熟度別指導の正しい理解を
- /
- 出来る子への対応―発展学習をどうするか
- 個に応じた指導(習熟度別学習の実践)
- /
- 保護者への説明責任―どんなデータを用意するか
- 絶対評価はデータによって語られる
- /
- 到達させる学校責任―指導力不足教員制度とは
- 指導力不足教員への学校内外サポート
- /
- 総合的学習の評価基準づくり:わが校の対応
- 評価の組織化をめざして
- /
- 自分自身の成長を確認できる評価を!
- /
- 自己評価力を伸ばす評価の提唱
- /
- 絶対評価と通知表改革のヒント―ポイントはどこか
- 学習内容に即した評価情報の提示を
- /
- 授業改善との一体化こそが重要
- /
- テスト問題作成の工夫と各種検定テストの利用
- /
- 「我が校の通知表」づくりのための絶好のチャンス
- /
- 絶対評価への転換:ホットな疑問に応えるQアンドA
- 到達度評価と絶対評価―どこが違うのか
- 学習者と共有できる評価をめざすこと
- /
- 評価規準と評価基準―どう違うのか
- 評価基準は観点別評価の「ものさし」
- /
- 評価と評定―どう違うのか
- 「評定」から「評価」へ、用語の整理と普及を
- /
- 絶対評価導入への対応―行政サイドの進捗状況
- 文科省、通知で絶対評価の重視を強調
- /
- 絶対評価でどこがどう変わるのか―具体場面で考える
- 小学校国語の絶対評価
- 評価を公表するシステムで授業を変える
- /
- 小学校算数の絶対評価
- 学習指導要領の最低基準性を受けて
- /
- 中学校国語の絶対評価
- 教育界の大変革!全てが変わる
- /
- 中学校数学の絶対評価
- 絶対評価を生かした数学授業改善
- /
- 中学校英語の絶対評価
- 「力をつける授業」へ
- /
- わが校の教育環境づくり ポイントはここだ (第12回)
- /
- 不思議の国の教育論議 (第12回)
- 「国全体の将来像」を現実的に選択しない不思議
- /・
- 職員室の困ったさん (第12回)
- 子供が主人公?
- /
- こう変わる こう変えよう教育評価・評定 (第12回)
- 新教育課程の実施と評価の改善
- /
- 校内研究会の戦略と戦術 (第12回)
- 熱心な学校と不熱心な学校
- /
- 同時進行ドキュメント●校長はどこまで仕事が出来るか (第12回)
- 新教育課程の詰めをする
- /
- どこまで仕事ができたか
- /
- ポートフォリオで自己改造―仕事に自信と達成感が持てる作成術― (第12回)
- 再び、ポートフォリオは何のため
- /
- アメリカ発 だれにでもできる“校内暴力”対応法―非暴力的危機介入法の理論とエクササイズ― (第12回)
- CPI非暴力的危機介入法を身に付けよう
- /
- 〜大丈夫、善のサイクルはあなたからスタートします〜
- 文教ニュース
- 文科省が「問題行動白書」を発表/教員免許制で中教審が「中間報告」
- /
- 編集後記
- /・
- あらふしぎカラーマジック 集中力は生きる力の源である (第12回)
- 発想力アップトレーニング その2
- /
編集後記
○…このたびの指導要録の改定で、絶対評価という概念が新たに導入されました。今まで、集団の中での、その子の位置付け、いわゆる集団準拠の評価がずっと続いていたわけです。ですから、目標に準拠した評価である絶対評価への転換だ!と、いきなり言われても…と言うことかな、とは思いますが、かなりあちこちから、“どうしよう”という不安というか、戸惑いの声がきかれます。
そのような声、要求に応えようと言うことだと思いますが、絶対評価を推進していく上での手だてというか、フォローとして、少人数指導、習熟度別指導の導入ができるようになりました。
また、更にはきちんとこれが機能するようにということでしょう、保護者への説明責任、いわゆるアカウンタビリティということも重視されるようになりました。なぜ、到達させることができなかったか、説明できないとまずいことになる…わけです。
本号では、先生方の意識改革を含め、学校としてどのような対応を考えていけばよいのか、想定される問題に対してどう取り組んでいけばよいのか、さまざまな角度からアプローチしていただきました。
(樋口雅子)
○…「ゆとり」路線の学習指導要領が一九八〇年に初めて登場して以来、文部科学省(当時は文部省)は、教えこまない、知識や技能を注入しないという教育を説きつづけてきた。この間、読売新聞の解説ではないが「子どもの学習意欲」は著しく低下した。今や日本の子どもの勉強や読書の時間が、他の先進諸国に比べて極めて少ないことが各校の調査で明らかになっていると、読売は報じた。
○…ここにきて、遠山文部科学相は、去る一月十七日に開かれた全国都道府県教委連合会総会で、児童・生徒の学力向上に向けて、教科書の内容を超えた授業や補習・宿題を奨励する新たな方針を表明した。これは「ゆとり教育」から「学力向上」重視への転換ではないか。「ゆとり教育」という亡国的発想は直ちに終止符を打つべきである。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















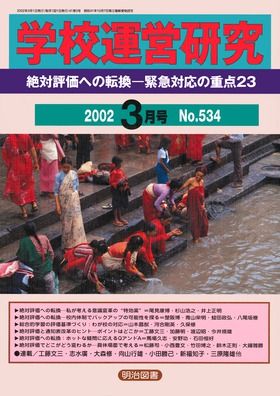
 PDF
PDF

