- “ءڈWپ@‚©‚ء‚±‚¢‚¢پIٹد‹q‚ًٹھ‚«چ‚ق‰^“®‰ïژي–عڈW
- “ءڈW‚ج‰ًگà
- پ^
- ژہ‘Hژ–—ل
- Œآگlژي–عپ^’لٹw”N
- ‹t“]Œ»ڈغ‚إٹد‹q‚ًٹھ‚«چ‚ق
- پ^
- ٹد‹q‚©‚ç”ڈژèٹ…چرپIپ@ڈخ‚¢‚ھ‹N‚«‚é‰^“®‰ïڈلٹQ‘–
- پ^
- Œآگlژي–عپ^’†ٹw”N
- ژ©•ھ‚ج“¾ˆس‚ب“¹‹ï‚إƒgƒ‰ƒbƒN‚ًژ¾‘–پIپ@‚SژيƒٹƒŒپ[
- پ^
- ƒ‰ƒbƒLپ[ƒJƒ‰پ[‚حپHپ@گâ–‚بƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚إگFٹّ‚ًڈم‚°‚é
- پ^
- Œآگlژي–عپ^چ‚ٹw”N
- ƒRƒچƒRƒچƒhƒbƒJƒ“پI
- پ^
- پuƒhƒLƒhƒLٹ´پv‚إٹد‹q‚ًٹھ‚«چ‚ق
- پ^
- ’c‘جژي–عپ^’لٹw”N
- ‘ه‹ت‘—‚è
- پ^
- ‹t“]Œ»ڈغ‚ھ‹N‚«‚éپIپ@‚Sگl‘gƒٹƒŒپ[پu—ح‚ً‚ ‚ي‚¹‚ؤپv
- پ^
- ’c‘جژي–عپ^’†ٹw”N
- ƒXپ[ƒpپ[ƒٹƒŒپ[ƒAƒ‰ƒJƒ‹ƒg
- پ^
- ”\—حچ·‚ً–„‚كپAƒ`پ[ƒ€ƒڈپ[ƒN‚ًگ¶‚قپu–_ژو‚èپv
- پ^
- ’c‘جژي–عپ^چ‚ٹw”N
- ”——ح–“_پIپ@ژ™“¶‚جˆہ‘S‚ة”z—¶‚µ‚½پu‹R”nگيپv‚جژw“±‚ح‚±‚ꂾ!!
- پ^
- ‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚½‰‰ڈo‚إ’è”ش‚ج‹R”nگي‚ً–£‚¹‚é
- پ^
- ƒٹƒYƒ€پE•\Œ»پ^’لٹw”N
- ٹب’P‚ب“®‚«‚إ‚à‘àŒ`ˆع“®‚إ‚©‚ء‚±‚¢‚¢•\Œ»‚ة•دگgپI
- پ^
- ƒqƒbƒg‹ب‚ًƒRƒsپ[‚·‚é
- پ^
- ƒٹƒYƒ€پE•\Œ»پ^’†ٹw”N
- ٹد‹q‚à”M‚¢ŒŒ’ھ‚ھ‚³‚ي‚®ƒٹƒYƒ€ƒ_ƒ“ƒXپw‚m‚dپE‚a‚tپE‚s‚`پx
- پ^
- ٹî–{ژw“±‚جƒ|ƒCƒ“ƒg‚حٹî–{‚ج“®‚«‚جŒآ•ت•]’è
- پ^
- ƒٹƒYƒ€پE•\Œ»پ^چ‚ٹw”N
- گVٹwچZ‹³چق—p‚و‚³‚±‚¢ƒ\پ[ƒ‰ƒ“پuژکSAMURAIپv
- پ^
- •غŒىژز‚à‚ج‚è‚ج‚èپIپuƒEƒHپ[ƒ^ƒ{پ[ƒCƒYپ•ƒKپ[ƒ‹ƒYپv
- پ^
- ƒ~ƒj“ءڈWپ@‚XŒژ‚ج‘جˆç‚ح‚±‚¤ژw“±‚·‚é
- ’لٹw”N
- ‚¢‚ë‚¢‚ë‚ب‹S—V‚ر‚ً‚µ‚ؤٹy‚µ‚ق
- پ^
- ’†ٹw”N
- ‘–‚è•’µ‚ر‚إپu‹Lک^‚ھگL‚ر‚½پv‚ئ‚¢‚¤ٹى‚ر‚ً–،‚ي‚ي‚¹‚é
- پ^
- ƒVƒXƒeƒ€‚ً‚«‚؟‚ٌ‚ئچؤٹm”FپA‚»‚µ‚ؤٹy‚µ‚¢‹S‚ ‚»‚ر‚ً
- پ^
- چ‚ٹw”N
- ƒٹƒŒپ[‚جٹî‘bٹ´ٹo‚ً—{‚¤
- پ^
- ‘g‘ج‘€‚ج—ûڈK‚ًƒVƒXƒeƒ€‰»‚·‚é
- پ^
- ƒ‰ƒCƒu‚إ‘جٹ´پI‚s‚n‚r‚r‘جˆçچuچہ
- ژِ‹ئ‚ج‘g‚ف—§‚ؤ‚ًٹw‚ش
- پ^
- ƒŒƒxƒ‹ƒAƒbƒvپI‘جˆç‚جژِ‹ئ‚ً•د‚¦‚é
- “®‚«‚ًٹدژ@پE”نٹr‚·‚é—ح‚ًˆç‚ؤ‚و‚¤
- پ^
- ƒ}ƒ“ƒK‚إŒ©‚éٹy‚µ‚¢‘جˆçژw“± (‘و78‰ٌ)
- چھ–{‘جˆç’¼“`ƒ}ƒ“ƒKپi‘g‘ج‘€‚جٹھپj
- پ^پE
- گV‘²‹³ژt‚جٹׂè‚â‚·‚¢‘جˆçژw“± (‘و6‰ٌ)
- ژِ‹ئ‚ج“±“ü‚جƒLپ[ƒڈپ[ƒh
- پ^
- پ`پu‚¢‚«‚ب‚è‰^“®‚ة“ü‚éپvپEپu‚¢‚آ‚à“¯‚¶گو“ھ‚جژq‚ة‚µ‚ب‚¢ƒچپ[ƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒXƒeƒ€پvپ`
- ڈWچ‡پEگ®—ٌپEƒOƒ‹پ[ƒv•ھ‚¯‚ج”÷چ׋Zڈp (‘و6‰ٌ)
- ‚Qگl‘g‚جژwژ¦ƒoƒٹƒGپ[ƒVƒ‡ƒ“
- پ^
- ٹwچZ‚ئ’nˆو‚ً‚آ‚ب‚®‚x‚n‚r‚`‚j‚n‚hƒ\پ[ƒ‰ƒ“‚جگV“WٹJ (‘و6‰ٌ)
- ‚ـ‚½Œ©‚½‚¢پI‚x‚n‚r‚`‚j‚n‚hƒ\پ[ƒ‰ƒ“‚جژہ—ح
- پ^
- پgƒ{ƒN‚ئ‚ي‚½‚µ‚ج‚©‚炾‚ئƒXƒ|پ[ƒcپhژ؟–âپE‹^–âپE”Y‚ف‘هڈWچ‡! (‘و6‰ٌ)
- ƒPƒK‚ً‚µ‚ؤ’ة‚¢ژ‚ة‚ح‚ا‚¤‚µ‚½‚ç‚¢‚¢پH
- پ^
- ƒ‰ƒCƒu‚إٹw‚ش‘جˆçژw“±‹Zڈp (‘و6‰ٌ)
- •‘‘ن‚ھگl‚ًˆç‚ؤ‚é
- پ^
- ˆê–ع—ؤ‘RپI‹³ژt‚جŒآ•ت•]’è (‘و6‰ٌ)
- ƒoƒgƒ“ƒpƒX50‰ٌ‚ً–عژw‚µ‚ؤ‡A
- پ^
- ’m‚ç‚ب‚©‚ء‚½پI‹Z‚جگ”پXپI‚ب‚ي’µ‚ر‚جگ¢ٹE (‘و6‰ٌ)
- ƒ_ƒuƒ‹ƒ_ƒbƒ`‚جژw“±پ@‚»‚جŒم
- پ^
- ژq‚ا‚à”M’†پI“S–_‚جگVƒhƒٹƒ‹ (‘و6‰ٌ)
- ڈ¼–{ژ®ژw“±–@‚إ‚ذ‚´‚©‚¯Œم“]‘Sˆُ’Bگ¬
- پ^
- ‚P–‡‚جژتگ^‚إژ¦‚·—¤ڈم‰^“®‚جƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg (‘و6‰ٌ)
- ‘–‚è•’µ‚ر‚ج“¥‚فگط‚è
- پ^
- ‚s‚n‚r‚r‘جˆçچإ‘Oگü
- پu‚ب‚ٌ‚خپv‚ج“®‚«‚جƒGƒLƒX‚ًژو‚è“ü‚ꂽ•àپE‘–‚جژw“±
- پ^
- Œّ‰ت”²ŒQپIƒtƒ@ƒbƒNƒX‚إ‚«‚é‘جˆçٹwڈKƒJپ[ƒh
- “S–_—V‚ر
- پ^
- پ`ˆê–ع‚إ•ھ‚©‚éپ@‹tڈم‚ھ‚è—ûڈKپ`
- “S–_‰^“®
- پ^
- پ`‘g‚فچ‡‚ي‚¹‹Z‚ة’§گيپIپ`
- چإگVڈî•ٌ‚ًگ·‚èچ‚ٌ‚¾ƒ{پ[ƒ‹‰^“® (‘و6‰ٌ)
- Œزٹضگك‚جژg‚¢•û‚ً‹³‚¦‚و
- پ^
- ƒ‰ƒCƒtƒXƒLƒ‹‚ئŒ’چN‹³ˆç (‘و54‰ٌ)
- ƒRƒ“ƒZƒvƒgژ‘م‚جƒXƒLƒ‹(2)
- پ^
- ژِ‹ئ‚جکr‚ًچ‚‚ك‚éک_•¶گRچ¸ (‘و173‰ٌ)
- ژ‘م‚ًگط‚è‘ٌ‚‹C”—‚ًپI
- پ^
- ‘جˆç‰ب‚ة‚¨‚¯‚éٹw—ح•غڈل (‘و42‰ٌ)
- ƒtƒ‰ƒbƒg–ت‚©‚ç‚ج‹tڈم‚ھ‚èژw“±
- پ^
- پ`گخ‹´Œ’ˆêکYژپ‚جژہ‘Hپ`
- “اژز‚جƒyپ[ƒWپ@My Opinion
- •زڈWŒم‹L
- پ^
- TOSS‘جˆçƒjƒ…پ[ƒX (‘و57‰ٌ)
- ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ح‚±‚±‚¾پI (‘و18‰ٌ)
- کr—§‚ؤŒم“]
- پ^
“ءڈW‚ج‰ًگà
‚©‚ء‚±‚¢‚¢پIٹد‹q‚ًٹھ‚«چ‚ق‰^“®‰ïژي–عڈW
‚s‚n‚r‚r‘جˆçژِ‹ئŒ¤‹†‰ï‘م•\
چھ–{گ³—Y
پ@ژD–yژs‚ج‹{–ىگ³ژ÷ژپ‚©‚çپA‰^“®‰ï‚إ‚s‚n‚r‚r‘جˆç‚و‚³‚±‚¢ƒ\پ[ƒ‰ƒ“‚ًژw“±‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤•ٌچگ‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@پuچ،”N‚ج‚و‚³‚±‚¢ƒ\پ[ƒ‰ƒ“‚جژw“±‚إچl‚¦‚½‚±‚ئ‚حˆب‰؛‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB
‡@چً”N‚à‚©‚ء‚±‚¢‚¢—x‚è‚ً—x‚ء‚ؤ‚¢‚éژq‚ا‚à‚½‚؟‚ب‚ج‚إپA‚ـ‚ء‚½‚•ت‚ب‹بپE—x‚è‚إ‚¢‚‚±‚ئپB
‡A‚»‚جژ‚ة‚حپA‚¢‚©‚ةژq‚ا‚à‚ةƒCƒ“ƒpƒNƒg‚ج‚ ‚éڈo‰ï‚ي‚¹•û‚ً‚·‚é‚©‚ھ‘هگط‚إ‚ ‚邱‚ئپB
‡Bژw“±ژٹش‚ًچً”N‚و‚èڈ‚ب‚‚µ‚½‚¢‚±‚ئپB
‡CŒ^‚ً‹³‚¦‚é‚ئ‚¢‚¤ژw“±ژٹش‚ًڈ‚ب‚‚µ‚½‚¢‚±‚ئپB
‡Dژq‚ا‚à‚ج•\Œ»—ح‚ًˆّ‚«ڈo‚·ڈê–ت‚ً“ü‚ê‚邱‚ئپB
‡Eچً”N‚حژè‚ة‰½‚àژ‚½‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAچ،”N“x‚حژè‚ة‚à‚آ•¨‚جژg‚¢•û‚ًژw“±‚µ‚½‚¢‚±‚ئپB
پ@‚»‚±‚إژو‚è‘g‚ٌ‚¾‚ج‚ھپAگîژq‚ً‚à‚ء‚½‚و‚³‚±‚¢ƒ\پ[ƒ‰ƒ“‚إ‚·پB‹ب‚حپAژ„‚ھƒ`پ[ƒ€‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½ژ‚ج‹ب‚ًژg‚¢‚ـ‚µ‚½پB—x‚è‚جŒ^‚حپA‚R‚آ‚جƒpپ[ƒc‚ةچiچ‚فپAŒJ‚è•ش‚µ‚ً“ü‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ج‚R‚آ‚جƒpپ[ƒc‚حپAژq‚ا‚à‚جپw‚â‚肽‚¢پxگS‚ً‚‚·‚®‚éژ؟‚جچ‚‚¢‚à‚ج‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پv
پ@‹{–ىگ³ژ÷ژپ‚ح‚و‚³‚±‚¢‚جژw“±‚إپAƒCƒ“ƒpƒNƒg‚ج‚ ‚éڈo‰ï‚¢پAژw“±ژٹش‚جچيŒ¸پAژq‚ا‚à‚ج•\Œ»—ح‚ًˆّ‚«ڈo‚·ڈê–ت‚ج‘}“üپAژè‚ة‚à‚آ•¨‚جژw“±‚جچH•v‚ًچs‚ء‚½پB
پ@‚»‚جŒ‹‰تپAژں‚ج‚و‚¤‚بŒ‹‰ت‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ•ٌچگ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پuژü‚è‚إŒ©‚ؤ‚¢‚½“¯ٹw”N‚جگوگ¶•û‚ھپAپwچ،“ْ‚جژq‚ا‚à‚ج—lژq‚ًŒ©‚ؤ‹¹‚ھ”M‚‚ب‚ء‚½پxپwژq‚ا‚à‚½‚؟‚ج‚ذ‚½‚ق‚«‚إپA‘f’¼‚إپcپcپxپw‚ ‚ٌ‚ب‚ة–²’†‚ة‚ب‚é‚U”Nگ¶‚جژp‚ة‚à‚ء‚ئژ©•ھژ©گg‹³ژt‚ئ‚µ‚ؤ‚ھ‚ٌ‚خ‚ç‚ب‚‚ؤ‚ح‚ئژv‚ء‚½پx‚ئپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ظ‚ا‚إ‚·پB‰^“®‰ï‚إ‚ح‘ه”½‹؟‚إ‚µ‚½پv
پ@ژü‚è‚إˆêڈڈ‚ةژw“±‚µ‚ؤ‚¢‚½“¯ٹw”N‚ج‹³ژt‚ھٹ´“®‚µپAˆّ‚«چ‚ـ‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@‚±‚ê‚ح‹³ژt‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAژQٹد‚µ‚ؤ‚¢‚½ٹد‹q‚à“¯—l‚إ‚ ‚éپB•غŒىژز‚©‚çپA‰‰‹Z‚جڈI‚ي‚ء‚½‚ ‚ئ‚ةƒAƒ“ƒRپ[ƒ‹‚ج—v–]‚ھ‚ ‚ھ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB
پ@‚»‚جŒ‹‰تپA‹{–ىگ³ژ÷ژپ‚حپAپuژ~‚ك‚é“®‚«پAژ~‚ـ‚é“®‚«پv‚ھ‘هگط‚إ‚ ‚é‚ئڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB
‡@ˆêڈu“®‚«‚ھژ~‚ـ‚éپB
‡Aˆêڈu‘§‚ھژ~‚ـ‚éپB
‡BˆêڈuŒ©‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ج–ع‚ھ—¯‚ـ‚éپB
پ@‚»‚¤‚¢‚¤“®‚«‚ًچى‚èڈo‚·‚±‚ئ‚ھ‚و‚³‚±‚¢‚ج—ا‚³‚إ‚ ‚é‚ئژه’£‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پuٹد‹q‚ًٹھ‚«چ‚قپv‚ئ‚حپuˆêڈuŒ©‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ج–ع‚ھ—¯‚ـ‚éپv‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@•\Œ»‰^“®‚ًژw“±‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒxƒeƒ‰ƒ“‚جڈ—گ«‚جگوگ¶‚ةپAپuƒٹƒYƒ€ƒ_ƒ“ƒX‚ج”éŒچ‚ح‰½‚إ‚·‚©پv‚ئژf‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB
پ@ƒxƒeƒ‰ƒ“‚جڈ—گ«‚جگوگ¶‚ح‘¦چہ‚ةپAپu‰¹ٹy‚ھŒˆ‚كژè‚إ‚·پv‚ئ‹‚‹’²‚³‚ꂽپB
پ@‚ا‚ٌ‚ب‚ةگU‚è•t‚¯‚ھ‚و‚‚ؤ‚à‰¹ٹy‚ھˆ«‚¢‚ئژq‚ا‚à‚حƒٹƒYƒ€‚ة‚ج‚ء‚ؤ—x‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢پB
پ@‹t‚ة‰¹ٹy‚ھ‚و‚¢‚ئ‘½ڈ‚جگU‚è‚آ‚¯‚â“®‚«‚ھˆ«‚‚ؤ‚àپAژq‚ا‚à‚جٹy‚µ‚³‚ھ“`‚ي‚ء‚ؤ‚‚éپB
پ@‰¹ٹy‚جƒٹƒYƒ€‚ھژq‚ا‚à‚ج“®‚«‚ًˆّ‚«ڈo‚µپAٹy‚µ‚³‚ًˆّ‚«ڈo‚·‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@‚»‚µ‚ؤٹد‹q‚àژq‚ا‚à‚ئˆê‘ج‚ة‚ب‚ء‚ؤٹy‚µ‚ق‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB‚ـ‚³‚µ‚ٹد‹q‚ًٹھ‚«چ‚ق‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@–{“ءڈW‚إ‚ح‹{–ىگ³ژ÷ژپ‚ج‚و‚¤‚بپAٹد‹q‚ًٹھ‚«چ‚ق‰^“®‰ïژي–ع‚ھڈذ‰î‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBژں‚جژèڈ‡‚إڈذ‰î‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é
‡@ژي–ع–¼
‡Aژي–ع‚ج‚ ‚ç‚ـ‚µ
‡Bڈ€”ُ•¨
‡CˆêڈuŒ©‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ج–ع‚ھ—¯‚ـ‚èپAٹد‹q‚ئ‰‰‹Zژز‚ھˆê‘ج‚ئ‚ب‚邽‚ك‚جژw“±‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
‡D‰‰‹Z‚ًگ·‚èڈم‚°‚éڈ¬“¹‹ï
پ@‰‰‹Z‚ًگ·‚èڈم‚°‚é‚ة‚حڈ¬“¹‹ï‚àŒ‡‚©‚¹‚ب‚¢پB‚و‚³‚±‚¢ƒ\پ[ƒ‰ƒ“‚إپA–@”ي‚ً’…‚ؤ‚¢‚é‚©‚¢‚ب‚¢‚©‚إ‚حپA•µˆح‹C‚ھ‘ه‚«‚ˆظ‚ب‚éپB
پ@Œ©‚ؤ‚¢‚éٹد‹q‚جژَ‚¯‚àˆل‚ء‚ؤ‚‚éپBژèچى‚è‚ج–@”ي‚ًچى‚é•û–@‚à‚ ‚éپB’nˆو‚©‚çژط‚è‚ؤ‚‚é•û–@‚à‚ ‚éپB‚ا‚ٌ‚بڈ¬“¹‹ï‚ھ‚ ‚é‚©پA–{ڈ‘‚ًٹˆ—p‚µ‚ؤٹy‚µ‚¢‰^“®‰ï‚ة‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB
-
 –¾ژ،گ}ڈ‘
–¾ژ،گ}ڈ‘















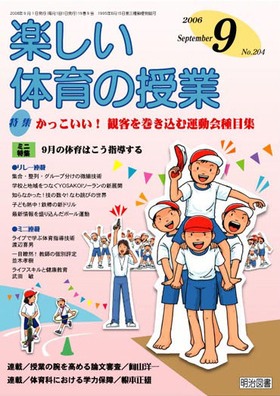
 PDF
PDF

