- 特集 「学級のルール」が生かされているか
- 提言・「学級のルール」を生かす知恵
- ルールを子どもの希望を紡ぐ糧に
- /
- ない方がよいルール厳しく対応すべきルール緩やかでよいルール
- /
- ルールを守っている子どもを褒める
- /
- 必要感と心地よさ、そして点検
- /
- 無茶なルールは作らない
- /
- 「学習のルール」が生かされているか
- 低学年/「確認+誉める」で、ルールを定着させる
- /
- 中学年/点検報告システムを作れば生かされる
- /
- 高学年/授業の原則でルールを生かす
- /
- 中学校/学習のルールを生かすも殺すも、教師の授業の腕にかかっている
- /
- 中学校/教師の指示がなくても学習活動ができているかどうかを見る
- /
- 「生活のルール」が生かされているか
- 低学年/自己評価を取り入れる
- /
- 中学年/チェック・誉め・チャンスで生かす
- /
- 高学年/ルールが生かされる基本を知り、妥協せず実践する
- /
- 中学校/三つの手立てで生活のルールを生かす
- /
- 中学校/「願い」を伝え生徒の自治を育てる
- /
- 「集団活動のルール」が生かされているか
- 低学年/クラス遊びを中心に集団活動を組織する
- /
- 中学年/係活動のルールをどう生かすか
- /
- 高学年/素早い集団行動と公平な当番活動のルールを身につけさせる
- /
- 中学校/ルールに則った生活が心地いいことは授業で体験させる
- /
- 中学校/教師が「ありがとう」を言えば、教室掃除が短時間で終わる
- /
- 「学級のルール」を守れない子への対策
- 「ルール違反」には、指導あるのみ!
- /
- 闘いかたも大切だが、「教師側の見直し」にも着手する。それなくしてスムーズな解決はない。
- /
- 集団の力を借りて、良い姿を示していく
- /
- 脳内の回路をつくる
- /
- ダメなものはダメと言い、成功体験の場を作り、ほめ続ける
- /
- 楽しいクラスをみんなで創る (第8回)
- 楽しいクラスのための環境作り
- /
- 心を育てる言葉かけ
- シャワーのように感謝の心かけ
- /
- 11月の仕事
- 必ず成功する個人面談の秘訣
- 面談用のアイテムを用意する
- /
- 周囲の子どもたちの評価が見える資料を用意する
- /
- ねらいを持って行う
- /
- 学習の遅れがちな子への配慮
- 遅れている子のプライドを傷つけない
- /
- 遅れがちな子がわかる授業は、どの子もわかる授業だ!
- /
- 配慮は、まさに授業のつかみから始まる
- /
- 「力のある資料」で命の授業を創る―小学校 (第8回)
- 脅威の昆虫機能研究インセクトテクノロジー
- /
- 「力のある資料」で命の授業を創る―中学校 (第8回)
- 「命を賭ける」を授業する(2)
- /
- 母親失格 (第8回)
- 友情のレクイエム
- /
- ネット時代の心の教育 (第8回)
- その人の生き方から出てきた言葉を子どもたちに知らせる
- /
- モラルジレンマで道徳の授業を変える (第8回)
- モラルジレンマを絵で訴える④
- /
- 酒井式で子どもの絵が変わる (第20回)
- 紙版画のニューバージョン「海のものがたり」
- /
- 変容する子ども世界 (第8回)
- 問題構成力の弱さ
- /
- 編集後記
- /
編集後記
○…学級のルールは守るために作られているはずです。学級の実態と学級目標に照らして、適切なルールを精選してつくり出されたはずです。しかしクラスは共同体であることの自覚がなかなか徹底しないし、学級担任と子どもたちや子ども同士のつながりを深めるためのはずのルールが機能しないという場面が出たりします。
○…そこから子どもたちがルールの必要性と重要性を共通に理解しているのだろうかという疑問も出てくることになります。改めてルールづくりの条件を再検討してみたいという焦りを感じたりするものです。
○…「学習のルール」には、(1)学習の仕方の基本に関するもの、(2)学習形態に応じた学習の進め方、発言や応答の仕方、(3)ノートや記録の仕方、(4)グループ学習、協同学習の仕方、(5)自己評価、相互評価などいろいろあります。さらには「生活のルール」や「集団活動のルール」などあります。特に「生活のルール」として学習生活を楽しくしたいという願いが生かされているか点検する必要があります。友だち関係、チャイムに従う行動のルール、それぞれの役割分担を果たすためのルール、など子どもたちの生活を安定させ向上させるために機能しているかという問題も出てきます。
○…また「集団行動のルール」となりますと、自分たちの創意が生かされているか、みんなで楽しく進んで参加しているか、計画通りに実践できたかどうかなどの反省も出てくるでしょう。
○…そのためには山下政俊氏(島根大)が言われるように、教師が子どもたちに(1)必要となる行為・行動を実行するよう確信を持って要求すること、(2)そのためのルールを確立し、定着するまで練習・訓練をさせること、が必要になるでしょう。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















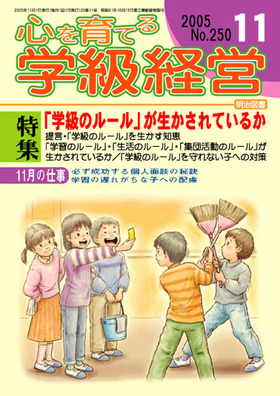
 PDF
PDF

