- 司書教諭を中心とした読書活動の展開
- はじめに
- /
- 序 「司書教諭を中心とする読書活動の確立に向けて」
- /
- 第1部 司書教諭を中心とした読書活動の実践的展開
- 第Ⅰ章 司書教諭配置による読書活動の充実
- 1 司書教諭配置の現状と役割
- /
- 2 司書教諭配置から読書活動が変わる
- /
- 3 司書教諭の関わりを明確にする読書計画
- /
- 4 読書活動を豊かにする学校図書館/(1)行きたくなるような学校図書館に変える―子どもたちが集う学校図書館に変える―
- /・
- 4 読書活動を豊かにする学校図書館/(1)行きたくなるような学校図書館に変える―子どもたちが集う学校図書館に変える―/思わず行ってみたくなる図書室に
- /
- 4 読書活動を豊かにする学校図書館/(1)行きたくなるような学校図書館に変える―子どもたちが集う学校図書館に変える―/読書の架け橋になろう
- /
- 4 読書活動を豊かにする学校図書館/(2)図書館を情報センター化する/読書活動から教科学習へ
- /
- 4 読書活動を豊かにする学校図書館/(2)図書館を情報センター化する/わかりやすい、借りやすい、本に親しめる図書館を目指して
- /
- 4 読書活動を豊かにする学校図書館/(2)図書館を情報センター化する/ITを活用した学校図書館
- /
- 第Ⅱ章 日常的な読書活動の実践的展開
- 1 心を豊かにする朝の読書活動
- /
- 2 読書環境をつくる地域ボランティア活動
- /
- 3 家庭と連携した読書活動
- /
- 第Ⅲ章 教科等における読書活動の実践的展開
- 1 国語科から広がる読書活動/(1)「話すこと・聞くこと」を広げる読書活動/「おはなしたからばこ」すてきなお話いっぱい
- /
- 1 国語科から広がる読書活動/(1)「話すこと・聞くこと」を広げる読書活動/ゲームをしながら、楽しく読もう!
- /
- 1 国語科から広がる読書活動/(1)「話すこと・聞くこと」を広げる読書活動/グループで構成するブックトークサービス
- /
- 1 国語科から広がる読書活動/(2)「書くこと」につながる読書活動/「心に残った一冊」感動を誌に表そう
- /
- 1 国語科から広がる読書活動/(2)「書くこと」につながる読書活動/自分の国語辞典を作ろう
- /
- 1 国語科から広がる読書活動/(2)「書くこと」につながる読書活動/人物事典にファイリング
- /
- 1 国語科から広がる読書活動/(2)「書くこと」につながる読書活動/世界にひとつだけの図鑑や絵本を作ろう
- /
- 2 他教科における読書活動/「町たんけん」発見・ふしぎ・なぞを本で調べよう
- /
- 2 他教科における読書活動/お天気博士になろう
- /
- 2 他教科における読書活動/隣接している図書館の利用
- /
- 2 他教科における読書活動/日常の図書館利用に生かすための地域図書館の見学
- /
- 3 総合的な学習の時間等における読書活動/自己教育力の向上を目指した発展学習としての読書
- /
- 3 総合的な学習の時間等における読書活動/民話の読み聞かせを通して心を育てよう
- /
- 3 総合的な学習の時間等における読書活動/「伝え合う」よろこびを味わう幼小連携の関わり
- /
- 第2部 各地における読書活動の基本的計画の策定
- 秋田県―「県民の読書活動推進計画」の策定について
- /
- 千葉県―子どもの読書活動の推進について~千葉県子どもの読書活動推進計画から~
- /
- 京都市―京都市における子ども読書活動の推進状況について~読書活動推進の基本計画策定に向けて~
- /
- 執筆者紹介
はじめに
学校図書館法が平成9年6月11日に改正になり,平成15年4月1日から12学級以上すべての学校に司書教諭を任命しなければならなくなった。そこで,各校に司書教諭が置かれることになった意義について考えてみたい。
新学習指導要領が本格実施となった今年度,教育の考えが従来の「教える教育」から「自ら学び自ら考える教育」へと教育の基調の転換が図られようとしているのである。
その中にあって学校図書館の役割が大きく見直されようとしている。つまり,従前の単なる図書室のイメージを大きく変換することとなる。今までは図書室に子供が読書に行く,本を借りに行く,調べ学習に行く,ということであった。ところが,司書教諭が配置されるということは学校教育の中に司書教諭が位置づけられ教育の内容に大きく関わることになると考えられる。子ども一人一人のニーズに応じて読書課題や他の課題に対応することが求められ,さらに教科の学習や総合的な学習に対応するということが求められる。要するに学校図書館は,「読書センター」としての役割,「学習情報センター」としての役割を機能させ,授業に活用される図書館となることが求められているということである。
このように考えると,司書教諭としては次のような仕事が求められていると考えられる。
●図書館教育全体計画の作成 ●図書館教育部の設置
●学校図書館経営年間計画の作成 ●学校図書館の仕事の整理
●学校図書館活用年間計画の作成 ●読書意欲を高めるための環境作り
●読書週間の取り組み ●選書会の取り組み
等々があるが積極的に各部と連携を図りながら取り組みを進め,学校教育の全体にわたっての活性化の起爆剤となることが求められているように思える。こういう取り組みを推進していくことが司書教諭の12学級以上の全校に配置された意義であると考える。司書教諭として上記のような内容に積極的に関わり,実践していくことが新教育課程の実現へと道を開くことにつながっていくものと確信している。
さて,本書は,文部科学省の井上一郎教科調査官より京都市国語教育研究会として実践を中心にして本を出版してはどうかというお話を頂き,本研究会でまとめたものである。井上教科調査官には序まで頂き感謝している。
最後に,今回の私たちの企画を快くお引き受け頂いた明治図書の間瀬季夫氏・松本幸子氏に心からお礼を申し上げる次第である。
2004年1月
京都市小学校国語教育研究会会長 鈴木 博詞
-
 明治図書
明治図書















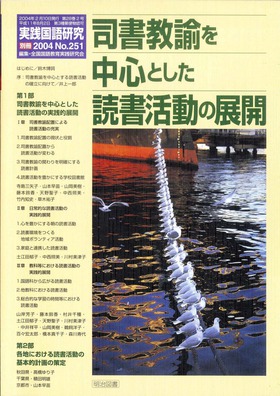
 PDF
PDF

