- 特集 教科学習への支援 小・中学校における授業づくり―国語,算数・数学の学習支援の工夫―
- 特集について
- /
- 提言
- 教科の本質を外さない支援の工夫
- /
- 事例〔小学校から〕
- 【国語】
- 1 国語科のねらいに迫る支援の在り方―若手教員の授業改善の試み―
- /・
- 2 どの子も参加できる学習活動の工夫―国語科4年「ごんぎつね」の実践から
- /
- 3 一人一人がもっと輝くために
- /・
- 【算数】
- 4 算数科におけるわかる授業づくり―視覚化・参加の促進・構造化の工夫―
- /
- 5 学習のユニバーサルデザインを目指した授業改善―算数科を窓口にして―
- /
- 事例〔中学校から〕
- 【国語】
- 6 学習支援の工夫 中学校国語を中心に
- /
- 【数学】
- 7 ICT機器の活用とpush・inの形態を採り入れた数学の授業
- /・
- 8 「共通化をはかる」「環境をつくる」を柱とし,教職員全員で取り組む“授業研究”と“開発的生徒指導”―授業改善の“四つの視点”を取り入れた数学の授業
- /
- Essay
- 基礎研究の意義
- /
- 子どものページ
- ドラゴン
- /
- 【特別寄稿】DO-IT:米国ワシントン州の障害のある学生たちの高等教育と就労への移行支援 (第1回)
- /
- 親の会ニュース (第38回)
- 「発達障害児のためのサポートツール・データベース」をご活用ください
- /
- 医療との連携 (第38回)
- LD通級指導教室における視覚支援の実際(2)
- /
- 〜眼科医やオプトメトリストとの連携の必要性―子どもに見えている世界を理解するために―〜
- 実践の小箱/臨床学校現場から (第36回)
- 子どもの目線の環境づくり
- /
- 情報最前線/行政や海外の動向は (第38回)
- 平成23年度特別支援教育予算額の概要
- /
- ユニバーサルデザインの授業づくり (第2回)
- 小学校における学習指導案の工夫
- /
- 〜ユニバーサルデザインの考え方に迫る授業展開〜
- クラスではじめる応用行動分析の基礎基本 (第2回)
- 安定したクラスづくりを考える
- /
- 誤り分析から子どもの読み書きを支援する! (第2回)
- 特殊音節の誤り分析から
- /
- 発達障害の子どもを持って (第2回)
- 親の思い(疑問・現状・課題)
- /
- 一度は手にしたい本
- 『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』(齊藤万比古編著)/『学ぶことが大好きになるビジョントレーニング』(北出勝也著)
- /
- 編集後記
- /
特集について
教科学習への支援 小・中学校における授業づくり―国語,算数・数学の学習支援の工夫―
国立特別支援教育総合研究所総括研究員/笹森洋樹
発達障害のある子どもの多くは,自分のペースであれば学習する力があるにもかかわらず,集団の流れに沿って学習したり,相手に合わせて学習したりすることを苦手としている。集団学習の場である通常の学級にはたくさんの刺激があり,不要な刺激を制御し必要な情報だけを選択しながら学習を進めることが求められる。集団で学ぶことが苦手な子どもにとっては,注目したり,集中したりすることが難しい学習環境でもある。発達障害のある子どもが通常の学級において,落ち着いてそして安心して学習に取り組める支援はどう考えていけばよいのだろうか。学習面における「わからない」「できない」経験の多い教室は,発達障害のある子どもに限らずどの子どもにとっても,安定して生活しづらい場所であり,学習意欲は低下する。さらに不登校等の二次的な障害を引き起こすきっかけにもなりかねない。
発達障害のある子どもの特性は,通常の学級における教科学習の様々な困難につながると思われるが,そのつまずきを見ると,同じように教科学習に困難を抱えている他の多くの子どもたちと共通している面も多い。このことは,通常の学級において,教科学習に困難のある子どもたちのつまずきに対する支援を学級全体への支援として工夫することが,発達障害のある子どもにも有効である可能性が高いということである。また,発達障害のある子どものための個別的な支援の工夫が,同じような学習のつまずきのある他の子どもたちにも,有効な支援になると考えられるということでもある。
学校の生活時間のほとんどは教科学習の時間である。授業の内容が理解できるかどうかは,子どもの学校生活での適応状態を大きく左右する。多くの子どもたちにとって,授業がわかりにくく,達成感や成就感が得られにくい学習環境であれば,子ども一人一人の学習内容の習得・定着が不十分であるばかりか,学級全体の雰囲気も支え合い認め合う支持的なものにはなりにくい。発達障害のある子どもに個別的な指導を行うためには,学級全体の学びを保障することが基本になる。各地域においても,特別支援教育の立場から,わかる授業づくりや授業研究会等を進めている学校も少しずつ増えてきている。
そこで,今回の特集は,特に国語,算数・数学を中心に,発達障害のある子どもへの教科学習における支援をテーマとして,小学校,中学校における特色ある実践を紹介する。
-
 明治図書
明治図書















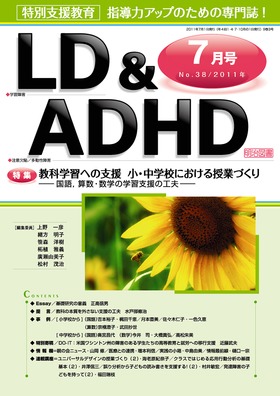
 PDF
PDF

