- 特集 来年度カリキュラム―新動向どう入れるか
- 総合の将来像・次期改定でどうなるか
- 朝令暮改ではダメ
- /
- 地域社会に生きる人間の育成
- /
- 自己の生き方を考え、実践する時間としての定着を
- /
- 来年度カリキュラムづくりのコンセプト
- いま、総合に求められているもの
- 学校としての目標を定め、全体計画の作成を
- /
- 原点に戻って、「知の総合化」の具体化を
- /
- 福祉教育は総合の必修にすべきである
- /
- 安定した計画と生きざまの鮮明な人間との出会い
- /
- 総合で何をするか・何が出来るか
- 個人力量の伸長を
- /
- 自己成長発表会で子どもの自尊感情を育てる
- /
- 今こそ「生き方」を考えさせよう
- /
- 新教科書の枠組みを意識すべきだ
- /
- 総合の動き「この8年」で見えてきたこと
- 教育の転換への大きな一歩
- /
- 目標・内容は書き分けられているか
- /
- 総合学習で確かな学力を伸ばす
- /
- 子どもの生きる未来からの要請に挑む責任と気概を
- /
- 新動向をキャッチした 来年度カリキュラムのヒント
- 地域づくり推進と来年度カリキュラムのヒント
- /
- 発展学習と来年度カリキュラムのヒント
- /
- 奉仕活動と来年度カリキュラムのヒント
- /
- インターネット活用と来年度カリキュラムのヒント
- /
- 英語を使える日本人と来年度カリキュラムのヒント
- /
- 伝統文化こども教室と来年度カリキュラムのヒント
- /
- 環境基本計画と来年度カリキュラムのヒント
- /
- 栄養教諭創設と来年度カリキュラムのヒント
- /
- タイプ別 総合カリキュラムのモデル例と自校化のヒント
- 生き方探究型のカリキュラムづくりのヒント・小学校
- /
- 生き方探究型のカリキュラムづくりのヒント・中学校
- /
- 体験活動型のカリキュラムづくりのヒント・小学校
- /
- 体験活動型のカリキュラムづくりのヒント・中学校
- /
- イベント型のカリキュラムづくりのヒント・小学校
- /
- イベント型のカリキュラムづくりのヒント・中学校
- /
- 教科発展型のカリキュラムづくりのヒント・小学校
- /
- 教科発展型のカリキュラムづくりのヒント・中学校
- /
- 新動向を入れたカリキュラムづくりのために
- 国際理解教育 どんな動きがあるか
- /
- 環境教育 どんな動きがあるか
- /
- 福祉教育 どんな動きがあるか
- /
- 情報教育 どんな動きがあるか
- /
- 健康教育 どんな動きがあるか
- /
- 来年度カリキュラムの青写真づくり―何を検討しておくか
- 教務主任がする総合カリキュラムの検討点
- /
- 研修主任がする総合カリキュラムの検討点
- /
- 学年主任がする総合カリキュラムの検討点
- /
- 学級担任がする総合カリキュラムの検討点
- /
- 食のネタと授業化のヒント (第7回)
- 牛乳でカルシウム不足を補うという考えは見直す必要がある
- /
- 子どもと教師のための“総合で鍛える発想術” (第7回)
- ネーミングで「2×2マトリクス」を生かす
- /
- 総合で追う「なりたい自分」と「なれる自分」を広げる (第7回)
- 「総合」が学校を開く―大学や地域との連携
- /
- 総合的学習―今とこれからを構想する 総合的学習十二の間違い探し (第7回)
- 夢を語れない、あるいは無駄に真面目
- /
- 川が汚い 汚い川だ―あなたの総合はどちら? (第7回)
- ナラティヴによる意味づけ
- /
- ホンモノの総合を求めて―古今東西の名授業に近づく道 (第7回)
- 授業記録を起こすこと
- /
- 中学校の総合―「知的探究」の構想 (第7回)
- アメリカのひかりとかげと多様性を探る!
- /
- 総合で仕掛けるキャリアガイダンス 子どもの夢を育む“世の中仕事カタログ” (第7回)
- 家電の歴史、ふしぎを楽しく学ぶ
- /
- 編集後記
- /
- 子どもに伝えたい“日本の伝統文化” (第7回)
- 地域から文化と子供を育む歌舞風―喜多流能大島家
- /
編集後記
○……村上龍氏の『13歳のハローワーク』がロングセラーを続けているようです。たしかに、値段の割にカラフルで情報量も沢山あり、さすが!と思います。それにしてもどういう年齢層の人が読んでいるのか―気になります。
つまりあの本は、まさに13歳というような、これからどういう方向に船出をしていけばよいのか悩む年齢層の人に読んで欲しいのだと思うのですが、中学校では、こういう指導がなされているのか?いささか疑問に思います。
ところで、総合的学習のねらいには、「自己の生き方を考えること」と明示されているわけですから、進路、とりわけ、「これからどういう仕事をしていくことが自分にあっているのか」、「自分はいったい、何をしたいのか」について考えるための情報提供を、この時間の大きな柱にしていくことが、今一番もとめられているのではないでしょうか。それがまた、この時間の、なによりの有効な活用の仕方ではないかと思います。
特にこのところ、若者のフリーター志向が増大しているといわれます。そういう若者を取材したテレビ番組などを見ると、何が自分にあっているのか、20歳を過ぎても模索してあれこれ体験してみているということもあるようです。
もう少し、成人する前に自分のしたいことをじっくり見つめる機会がなかったのか―という気もします。
本号はその具体像を、ご紹介いただきました。
-
 明治図書
明治図書















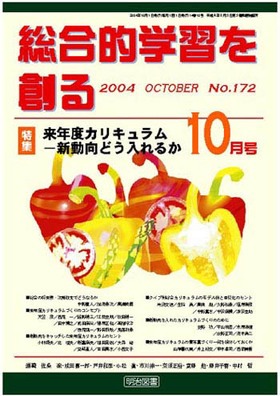
 PDF
PDF

