今回は、大空小学校初代校長の木村泰子先生にご寄稿いただきました。なぜ「みんなの学校」なのか、木村先生はそれを、教育の公共性(パブリック)の視点から説き起こしてくださっています。「「障害」をみると、その子がみえなくなってしまう」という木村先生の言葉の意味を、深くかみしめたいと思います。
「みんなの学校」は全国のパブリックの学校の本名です。通名が大空小学校です。地域に生きるすべての子どもが地域の学校で安心して学び合う事実をつくることが校長の責任です。
貧困の家庭の子どもや「障害」と診断されている子ども、すぐに暴力をふるってしまう子どもや虐待されている子ども、外国にルーツをもつ子どもなど、それぞれに多様な「自分」をもっています。これらのすべての子どもが「自分から 自分らしく 自分の言葉で語る」子どもの事実をつくることがインクルーシブ教育の目的だと考えてきました。
大空小学校がインクルーシブ教育の実践校だとの評価を耳にすることがありますが、大空小のみんなは「インクルーシブ」という言葉さえ使ったことがありませんでした。それは、自分たちには難しいことがわからないからです。地域に生きる地域のすべての子どもが地域の学校で誰一人排除されることなく、安心して学び合う子どもの事実をつくることだけをみんなで大事にしてきました。このことは評価されることではなく、憲法で定められていることをパブリックの学校として実践してきただけのことです。
「すべての子どもの学習権を保障する」を学校の理念として、地域の学校が地域にあり続ける限り、進化・継続していかなければなりません。この目的を達成するための手段は、目の前の子どもや社会のニーズに応じて柔軟に変えていくことを、子どもの周りにいるすべての大人が常に確かめ合ってきました。
ただ、このあたりまえのことをあたりまえに実践することがどれだけ難しいか、悪戦苦闘の連続でした。「みんなの学校」の9年間は「分ける教育」や「分けない教育」を考えたこともなければ、「通級」の制度を必要と考えたこともありませんでした。「障害」をみると、その子がみえなくなってしまうことが何度もありました。「自閉症」のAさんBさんCさんはみんな違います。それなのに、この子は「自閉症の子」などと目の前の子どもをくくりでみてしまったときのその子の困った姿に謝りながら、何度もやり直しをしてきました。「自閉症」と診断された子どもは24時間「自閉症の子」ではなく、周りの子どもや大人とのかかわりの中で「自閉症」の特性が現れるということを、子ども同士の関係性から学びました。その子が周りの子どもたちと安心して学び合えない要因は、その子の「障害」が問題なのではなく、その子の周りの子どもや大人がつくるかかわり方や空気が問題なのだということを子どもたちに教えてもらってからは、大人の私たちがすることは何なのかが明確になりました。
開校当初、「みんなの学校」の映画の中で、言葉でコミュニケーションをとることができない「自閉症」と診断されている「彼」が、みんなと一緒の教室に居てそれでいいのだろうか、別室でこの子のスキルを高める個別指導が必要ではないだろうかと日々悩み続けていたとき、彼の母が教えてくれた言葉がその後の大空の教育の根幹にいつもありました。
「先生たち、彼はいやだったら教室から出ていきます。朝、学校に行きたくないそぶりもみせるはずです。彼に必要な学力はいつも周りの子どもと一緒にいることが当たり前の空気を吸い続けることです。先生たちがどれだけがんばって彼にスキルをつけようとしてくれても先生たちはこれから彼と一緒に生きる人たちではないですよ。周りの子どもたちから彼が学び取る力を信じてやってください」
母の言葉は「みんなの学校」の復元力として根づいています。
まとめ
- 「障害」を理由に子ども同士を分断する場で、学びの本質は生まれません。みえない排除を生みます。個の力をどれだけつけても、その力を試す場がなければ生きて働く力にはなりません。子どもは子ども同士の関係性の中で育ち合います。


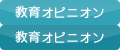
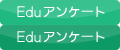

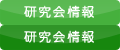
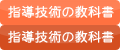


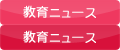










“子供同士の関係性の中で育ち合います”で、「責任を子供に擦り付け」ということまでおやりになるのですね。
「木村泰子の学校」が本当のタイトルです。