【文学教材】
「心情曲線」を使って文学教材全体の構造を押さえたいのですが、どうもうまくいきません。どのようにすればよいでしょうか。
ココがポイント!
文学教材の多くにおいて、登場人物の心情が消沈、回復、上昇、昂揚する
例えば、「スイミー」(2年上、光村)ではこれが非常に明確です。
「たのしく くらして いた。」(昂揚)
↓
「こわかった。さびしかった。とても かなしかった。」(消沈)
↓
「スイミーは、だんだん 元気を とりもどした。」(回復)
↓
「スイミーは 見つけた、スイミーのと そっくりの、小さな 魚の きょうだいたちを。」(上昇)
↓
「みんなは およぎ、大きな 魚を おい出した。」(昂揚)
学年が上がるにつれ教材文が長くなり、この消沈、回復、上昇、昂揚が複雑にからみあっていきます。そうした変化を目に見える形にする「心情曲線」は、文学教材の全体構造を押さえる方法として、うまく使うと非常に効果的です。
効果抜群! 堀江式 大ワザ&小ワザ
ワザ1 授業実践の基本となる学習指導要領を押さえる―「叙述を基に」読む―
「心情曲線」を活用した授業を何度も観ましたが、残念なことに曲線を描くだけにとどまっている場合があります。授業実践の基本となる学習指導要領を押さえてみましょう。例えば、〔第3学年及び第4学年〕の「C 読むこと」領域の指導事項ウを挙げることができます。
ウ 場面の移り変わりに注意しながら,登場人物の性格や気持ちの変化、情景などについて、叙述を基に想像して読むこと。
登場人物の気持ちの変化を読む際に、「叙述を基に」読むことが重視されています。
ワザ2 「心情曲線」に叙述を添える―心情曲線と本文の叙述をつなぐ―
「心情曲線」を活用する際にも、この「叙述を基に」読むことが基本となります。「大造じいさんとガン」(5年)のノートに書かれた「心情曲線」の例を示しましょう。「心情曲線」をはさんで、上に「行動(叙述)」が示され、下にその叙述から読み取った「心情」が書かれており、それをつないでいます。廣門知紗学級(赤穂市立赤穂小学校5年)において生み出されたノートです。
さらに詳しくは、堀江祐爾編著『小学校国語科授業アシスト 実物資料でよくわかる!教材別ノートモデル40』をご参照下さい。
















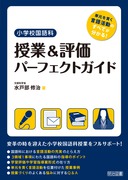



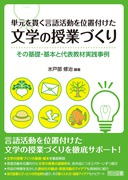

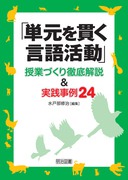

登場人物の叙述を添えるという簡単な工夫だけで、本文に立ち返らせて心情曲線をかくことになる。心情曲線を「読むこと」の学習として生かす工夫を教えていただくことができた。
私も心情曲線をよく使うのですが、本文の引用を板書し、そこに黄色チョークで読み取った気持ちを書き込む、その後赤チョークで心情の高まりや心の通い合いなどを線で書き込むことが多いです。もっとすっきり表す方法はないかと模索していました。今回の廣門先生のノートは、上段に本文、中段に曲線、下段に読み取った気持ちと整理されていて、とてもすっきりとわかりやすいです。ぜひ板書にも取り入れたいと思います。
心情曲線によって、中心人物の心情、つまり、昂揚、消沈、回復、上昇など、心情の変化を視覚的に理解しやすくなったのは確かなのです。しかし、児童の中で、どうも叙述との結びつきが弱いと感じていました。そんな時、今回の例がとても参考になりました。心情曲線、叙述、心情を結びつけて、視覚的にもさらにわかりやすいものになっているのです。次回、心情曲線を使うときには、この例を参考に、さらに視覚的に理解、そして、叙述に沿って、児童が物語文を読めるように努めたいと思いました。
心情は文章中にそのまま書いてあるとは限りません。台詞、行動、情景描写を手がかりに、正しく解釈することが求められます。このワザでは「行動」の欄に取り出した情報について、「心情」の欄に子どもたちが自身の言葉で解釈した結果を書いています。これならば高い読解力が身に着くと考えられます。
叙述を抜き出すだけでも、曲線を描くだけでも、心情を言葉で書くだけでも理解は深まりません。それらを複合的に考えることを可能にしているのが、このワザなのだと思います。
また、授業の中で物語の状況を一通り確認してからこのワザを使うと、より効果的なのではないでしょうか。