- きょういくじん会議
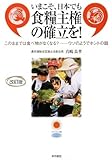
10月16日は何の日だったか皆さんご存知でしょうか? 正解は「世界食料デー」。幸いにして、食べるものに困るということが少ない日本人には、なかなかなじみのない日かもしれません。しかし、世界中では数多くの人が飢餓に苦しんでおり、わたしたちの生活スタイルがその原因となっていることも否定できません。少し、世界の食料事情について考えてみるのはいかがでしょうか。私たちにもなにかできることがあるかもしれません。
「世界食料デー」は、国連が食料問題への関心を高め、より一層の協力を呼びかけるために、国際連合食糧農業機関(FAO)の設立記念日である10月16日を「世界食料デー」として1979年に定めたのが始まりですが、今年は、「危機における食料安全保障の達成」というテーマで、世界的経済危機の農村への影響を考えるとともに、世界食料安全保障の達成のため、農業への投資を拡大すべき、ということを呼びかけています。
「世界食料デー」に合わせて特集された、16日の読売新聞の記事によると、FAOの推計によれば現在、10億人以上の人々が飢餓の状態にあえいでいるとのこと。ここ数年の、食料危機及び経済危機の組み合わせが、世界各地の飢餓人口を記録的なレベルに押し上げており、その飢餓人口のほとんどすべては、開発途上国に暮らしています。FAOの年次飢餓報告書「世界の食料不安の現状」によれば、アジア・太平洋では推定6億4200万人、サハラ以南アフリカでは2億6500万人、ラテンアメリカ・カリブ海では5300万人、中東・北アフリカでは4200万人、そして先進国では1500万人が慢性的な飢餓に苦しんでいるようです。
日本では?
カロリーベースの食料自給率が41%しかない日本でも世界的な食糧危機の影響は大きく、小麦を使った食料品の値段が高騰したのは記憶に新しいところです。しかし、食料を輸入に頼る日本で、1年間に捨てられる食べ物の量は約1900万トン。そのうちまだ食べられる食べ物は500〜900万トンといわれています。発展途上国の飢餓の原因が、先進国への食糧の輸出などであることを考えると、外食をするときや、家で調理をするときなど、世界の食料事情について、1人1人が考慮しなくてはいけないかもしれません。また、5日の読売新聞の記事には、「アフリカに給食を届けよう」と題してNPO法人「テーブル・フォー・ツー(TFT)」の取り組みが紹介されていました。アフリカで学校給食を1食提供するのにかかる費用20円を、日本国内の協力レストランなどで用意した低カロリーの食事を食べた人に、料理代金の内から寄付してもらう仕組みで、気軽に社会貢献でき、健康的な食事でメタボリックシンドローム予防にもつながるとして、参加する企業や自治体などが増えているようです。今回は大手コンビニのスリーエフも協力するとのことで、11月4日からは寄付ができるお弁当が店頭に並ぶようです。
世界中で10億人以上が飢餓にあえいでいる状況と、身の回りに食料が溢れている現実は、なかなか結びつかない、というのが本当のところかもしれませんが、なにか大きな問題になってから考えるというでは遅すぎるのも事実です。今からできること、自分たちでできることを1つ1つ行っていくことが必要になってくるのかもしれませんね。
- 日本国際飢餓対策機構
http://www.jifh.org/ - 国際連合食糧農業機関(FAO)
http://www.fao.or.jp/index.html
