- 特集 「授業上達法」をみんなで学ぶ
- 提言・名人芸の先達はこう助言する
- 五つの技術(対応の技術)と人間性をみがく
- /
- 理解と確認と体現の三条件
- /
- 学級崩壊クラスで授業成立が25級、クラスを建て直す力量が20級。TOSS技量検定の目安
- /
- 腹の底からの実感に依拠する
- /
- 緊張感のある場数を踏む
- /
- 「プロ教師」の教え方・ここを学ぶ
- 授業を見る「基準」をもって学び、修業する
- /
- 大森修氏の「教態」と戦略的実践に学ぶ
- /
- 模擬授業・技量検定を経験することで新たに見えだしたプロ教師の教え方
- /
- 憧れの授業をいくつ持っているか。それが授業上達のバロメーターだ
- /
- 「校内研修会」で、ここを学ぶ
- 授業技術という視点を校内研修に導入すべし
- /
- 研究授業と日常の授業をつなげていく
- /
- 直球どうしの衝突
- /
- 学校の実態に即した授業改善の方法を
- /
- 生徒の事実をつかむ場として
- /
- 「子ども研究」から学んだもの
- 日記による「子ども研究」から見えてくるもの
- /
- 授業の腕を上げたい教師は、TOSS授業技量検定を受検すべきだ!
- /
- 子どもが教えてくれる教師のレベル
- /
- 「子ども自身が自分をどう思っているのか」を理解する
- /
- 「生徒をみる目」をどこに置くか
- /
- 「模擬授業」で授業の腕を上げる
- 模擬授業で、授業力に必要な「瞬発力」と「基礎体力」を鍛える
- /
- 段クラスの授業を追試し、授業の腕を上げる
- /
- イメージがすべての出発点である
- /
- 校内研究に模擬授業を取り入れる
- /
- 授業がうまくなるために取り組んだこと10
- /
- 「サークル」の研究会から学んだもの
- サークル研究会から自分の技量不足を学ぶ
- /
- 法則化論文は、教師修業のシステムだ
- /
- 多くの情報を学ぶことができた
- /
- 上質な情報は、やる気の火をともす
- /
- サークルで、教師修業のすべてを学んだ
- /
- 模擬授業で腕を上げる
- /・・
- 校内研修・研究への私の助言
- 教え育てる力量の組み換えを誘発する研修
- /
- インターネットで授業は進化する (第8回)
- 『インターネット活用授業集成』は、周りの先生にも好評です
- /
- 子どもが自分で勉強したくなる授業づくり (第8回)
- 「目標の魅力」×「うまく行く確率」=やる気
- /
- 教科書の使い方を変える (第8回)
- 「何を」「どのように」鍛えるか常に考える
- /
- 授業研究ニュース (第20回)
- コンピュータ活用して授業できる教員は60%
- /
- 授業力アップのための修業 (第8回)
- して見せて鍛える(2)
- /
- 〜あれども見えずを見えるようにする〜
- これからの授業研究の在り方 (第8回)
- ミクロ教育社会学の授業研究について
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…授業の上達論は向山洋一氏が主宰した教育技術法則化運動の中から誕生した、といえます。私の編集者生活五十年に及ぶ中で、授業の技量を向上させることを具体的に提案した運動は皆無であったと反省するこのごろです。
〇…向山氏は教師の技量向上のステップについて、大きく分けて二つの段階があると提案しています。「一つは、黒帯・初段程度の段階。一つは、名人・高段の芸の段階。法則化運動が対象としているのは、前者、黒帯・初段程度までの上達である。このレベルまでは、まじめに熱心に教師修業すれば、ほぼ全員が到達することができる」と。
〇…さらにつづけて「黒帯への上達のための六項目」をクリアすることを提案されています。(『新卒教師の授業上達論』参照)例えば、教師としてよく使う指導技術を一〇〇分野以上知っているとか、名人級や著名実践家の授業の追試を一〇〇時間などしているとか、研究授業を一〇〇時間以上やるとか、さらには、サークルの研究会で提案を検討されたのが一〇〇回以上ある等々。
〇…「黒帯六条件」をクリアすれば、誰でも「プロの入口」まで到達できる、と向山氏は言っています。これまで教師修業の目安を明確に示した「上達論」は皆無であったといわれる所以です。
〇…いまや文科省の諮問機関である中央教育審議会でも教員のやる気を引き出す工夫や校長がリーダーシップを発揮する態勢づくりを検討している時代です。例えば、教え上手ならば「マイスター」(名人)として校長待遇にしたらどうかなど処遇に連動させる仕組みを議論していると伝えられています。
〇…教員の意識や能力を高める方法への期待は、時代の要請でもあるわけです。本号は、そのための具体的検討を試みる特集です。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















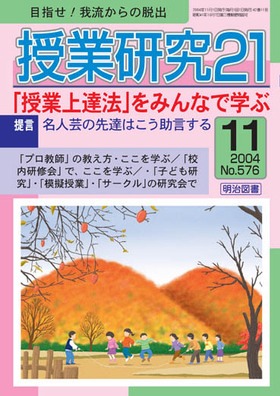
 PDF
PDF

