- 特集 学級に必要なルール・必要ないルール
- 提言 学級に必要なルールとは何か
- 提案するルールと解決するルール
- /
- 必要なのは習わしの改廃
- /
- 「他者」との関係性の構築がルールづくりの基盤である
- /
- 三つの側面に目配りしたルールを!
- /
- 学級や自他の向上を促進する要因をルール化する
- /
- 低学年に必要なルール・必要ないルール
- 何事も徹底してこそのルールである
- /
- ルールがあるからこそ、安心できる居場所があるクラスが作れる
- /
- なぜ、そのルールが必要なのかを分かっていることが大事
- /
- 中学年に必要なルール・必要ないルール
- 「仲間関係」に着目してルールを作る
- /
- 「他律」から「自律」へ移行していく成長を、正しく支援する
- /
- 「教師が一週間いなくても、子どもたちがきちんと生活できる」ことをイメージしてつくりあげるルール―児童の生活を細かく分けて何をすべきかを最初に示す
- /
- 高学年に必要なルール・必要ないルール
- 基本的なルールを示し、数を減らす
- /
- 子どもが納得し、機能させてこそ本当のルールとなる
- /
- 学習の仕方・生き方のルールを教えて子どもたちの生きる力を育む
- /
- 中学校に必要なルール・必要ないルール
- 教師の都合が優先されているルールは必要ないルールである
- /
- 忘れ物を例に考えてみる
- /
- 自主・自立・自治の力を育てるルール
- /
- ルールが機能すれば、不要なルールは淘汰される
- /
- 誰のためのルールか、何のためのルールかという視点で考えてみる
- /
- 特別支援の子へのルール指導
- 教師の細やかな目配り・全員の原則と個別指導
- /
- 人に迷惑をかけることはダメ・そうでないことは大目にみる
- /
- 受け入れる・教えてほめる・信じて待つ
- /
- 楽しいクラスをみんなで創る
- 減り張りがあるから楽しい!
- /
- 教師修業への助言
- 国民形成という責務
- /
- 体験活動が人生を決める (第3回)
- 平成の時代でも「寝る子は育つ」か
- /
- 授業崩壊から生還するために (第3回)
- 初日から荒れた! 新卒教師の奮闘
- /
- 発達障がいの子どもに学ぶ (第3回)
- 「勉強やりたくない」と言う広汎性発達障がいの子にどう対応するか
- /
- 授業の知的組み立て方 (第3回)
- 飛び込み授業の導入で子どもたちを変化させた「その場での対応方法」とは
- /
- 子どもの発言を引き出す技 (第3回)
- 写真にねらいを込めて考えを引き出す
- /
- 実感道徳のすすめ (第3回)
- 実感道徳の授業は授業者の「観」が基本
- /
- 編集後記
- /
編集後記
○…かつて山下政俊氏(島根大)は、「学級にルールがなければ、もっと楽しくもっと自由に学べるはずだ、と考える子どもと教師は少なくないのではないか」と問いかけ、「失望させるルールと希望を紡ぐルール」があるとして、学級のルールがなぜ必要なのか、検討を呼びかけていました(『心を育てる学級経営』二〇〇五年一一月号)。さらに、ルールを生かす知恵と方法の開発を呼びかけ「必要なことは、形骸化し有名無実になっているルールの現状を、子どもの学びに照らして分析・評価し、必要な改正や改廃を、即刻彼らと共に行うことである。もう一度、子どもと学級の実態に即してルールを提案・要求し、その価値や必要を彼らに実感させるまで、取り組むことが求められる」と訴えています。
○…学校・学級を学びの共同体にしよう、と呼びかけている明石要一氏(千葉大)は、「学校・学級は学級崩壊、いじめ、不登校の子どもを抱え制度疲労を起こしている」とし「今や存在が問われている」と強調されています。さらに民間の学習機関の学習には、「学びの共同体」という発想はない。学習は相互に刺激し合ってするものという発想はない。学校・学級の学習は集団の中で共に学び合う学習スタイルなのだ。「子ども同士が教師の指示や示唆を受けて共に刺激し合い、助け合い、競い合う学習」なのだと強調されていました。「学びの共同体」づくりが学校・学級の再生の道だ、というわけです(『学級の集団的機能を見直す』より)。
○…貝塚茂樹氏(武蔵野大)は、「法・ルール・きまり」の基盤となる共同体意識について、互いに助け合って生きることが必要であると説き、「規範意識」を醸成するための前提となると強調されていました。
○…本号はそのために、改めて学級に必要なルールを考えてみたいと特集を組みました。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















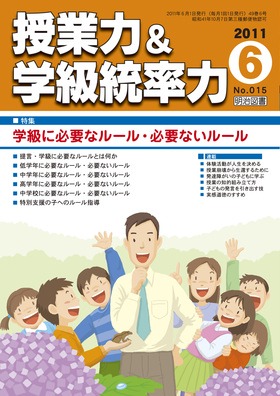
 PDF
PDF

