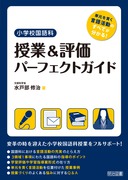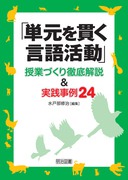水戸部先生に聞く!「単元を貫く言語活動」Q&A (1)
本単元で付けたい力を見極めよう!
2014/4/17 掲載
- 単元を貫く言語活動Q&A
- 国語
今年度から国語授業での「単元を貫く言語活動」に取り組むことになりました。これから本格的に授業がスタートしますが、まずはどのようなことから始めればいいでしょうか?
取り組んでみたい事例が見つかりました!
さっそく4月の単元でチャレンジしてみたいのですが、どんな点に気を付ければよいでしょうか?
さっそく目標が見つかりましたね。ここで大事なのは、その単元でどんな力を付けるのかをはっきりさせることです。その手がかりは2つあります。
1つは、学習指導要領の指導事項です。その単元で、どの指導事項を取り上げて指導するのかをまず確かめましょう。
2つめは、子供たちの実態です。例えば第3学年及び第4学年の「C読むこと」の指導事項には、「ウ 場面の移り変わりに注意しながら、登場人物の性格や気持ちの変化、情景などについて、叙述を基に想像して読むこと」があります。文学教材ならば、「場面の移り変わり」や「登場人物の性格」「気持ちの変化」「情景」などが巧みに描かれていますが、これらをすべて取り上げようとすると盛りだくさんになりがちです。例えば子供たちが前単元までに、「登場人物の性格」や「情景」が読めてきたけれど、「場面の移り変わり」や「気持ちの変化」にはまだ十分には着目できていなかった、といった実態があれば、そこに重点を置いて指導目標を設定することとなります。
ここをチェック!授業改善のためのポイント
本単元で付けたい力を見極めるためのチェックポイントは、以下になります。
- 当該単元で取り上げる指導事項は明確か?
- 単元の指導目標には、その指導事項の内容がきちんと位置付いているか?
- 指導のねらいは、子供たちの実態を踏まえて把握しているか?
(構成:木山)
コメントの受付は終了しました。