
- チームリーダーの仕事術
- 学校経営
1 飲み会に参加しない理由
言葉はその時代に合わせて変化するというが、「飲(の)みニケーション」という言葉もその1つだ。かつては頻繁に使われていたが、勤務後の時間をある意味拘束することを避けるようになり、ほとんど耳にしなくなった。
また、最近よく耳にするボヤキが、「会を設けても参加者が少ない。かつては学校全体や学年で旅行も企画できたのに、みんなと交わろうとする若者が特に少ない」というものだ。多くの都道府県では、職場に中間層が少なく、ベテランと若い教師で構成されている場合が多い。若い教師の立場に立てば、職場を離れてまで、ベテランとともにいるのはかなわないという思いにも一理ある。立場を変えて考えてみると、その気持ちがわかるわけだ。
2 若い教師に企画してもらう
しかし、だれもが自覚していると思うが、職場を離れた場でのコミュニケーションでは、心の開放も手伝って、いわゆる本音が出る。したがって、リーダーであれば、ときには懇親会や飲み会をセッティングしたい。
参加しにくいと感じている人への配慮もしたうえで、全員が参加でき、満足する懇親会や飲み会をすることはできないものだろうか。日ごろ苦労しているのに、ここまで気を遣うのか…と思うリーダーもいるだろう。こういうときこそ、適材適所だ。何も自分が企画する必要はない。若い教師に企画をしてもらえばよい。
新任から3年間勤めた学校は、一番若い教師が学校の懇親会運営者の1人になるというルールがあった。私は3年間にわたって懇親会を企画し、飲み会では司会まで仰せつかった。今思うと、大学生気分で企画していたが、それがかえってよかったように思う。懇親会の余興で、校長に寸劇に出てもらったり、いわゆるおばちゃん先生に、嫌がられながらもその当時のアイドルのものまねをやっていただいたりした。もちろん大ウケだ。懇親会後も話題となることがあり、職員室には笑いが再び起こっていた。
「日常から離れ、みんなでバカになる」というキャッチフレーズをつくり、行きのバスから大盛り上がりしたこともあった。数十年経っても、そのときの光景が目に浮かぶのだから、相当なインパクトがあったわけだ。
3 全員が楽しめる企画
このような大がかりなことではなく、ちょっとした工夫で全員が楽しめる企画はある。
例えば、学年のだれかが研究授業を終えたときなどには、ご苦労さん会を兼ねて、勤務時間後、学校で各種ケーキなどを人数分買ってきて、ミニパーティを開いたらどうだろうか。わざわざすべて違うケーキを買ってくるのが、盛り上げのコツだ。ケーキを前にして、選ぶ順番から決めればいい。他愛もないことだからこそおもしろい。研究授業を終えた同僚に敬意を表して、優先して選んでもらうことがほとんどだろうが、その後の順番決めに日ごろのかかわり方が反映されて興味深い。リーダーもこうした雰囲気を楽しめばよい。あるケーキを選ぶと、特別プレゼントがもらえるという仕込みをしておいてもいいだろう。
ときにはプレゼント交換をしても楽しい。我が校では、各自で千円程度の品物を買って、持ち寄るという企画が恒例となっている。そして、くじによってプレゼントを選ぶ順番を決め、ずらりと並んでいるプレゼントを、触ることなく見て選ぶという演出だ。プレゼントを選ぶ楽しみ、開けてみる楽しみ、それを見ての一言コメントを聞く楽しみがある。何事もアイデア次第だ。
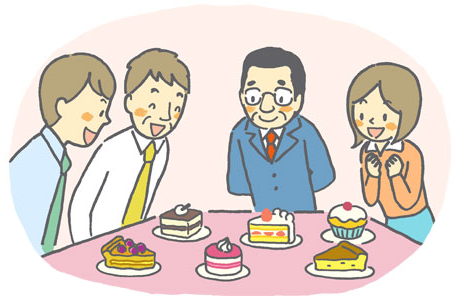
今回のPoint!
若い教師に主導してもらったり、他愛もないことをしたりして、だれもが満足できる懇親会にする。
