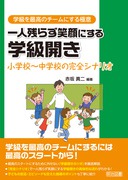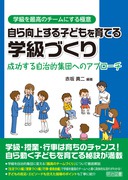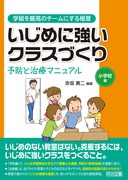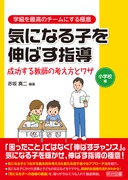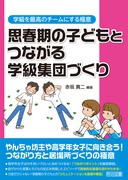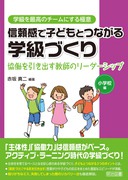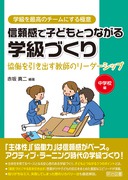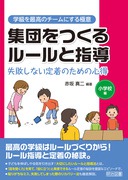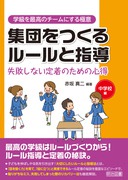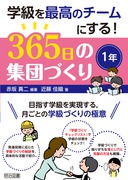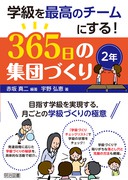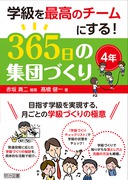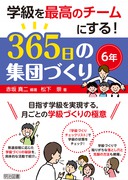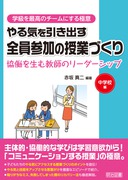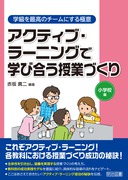- 赤坂真二直伝!教師のリーダーシップ
- 学級経営
部分最適と全体最適
現在の学校教育において、アクティブ・ラーニングの浸透や発展を阻害する要因があるとしたらそれは、学校教育がもつ部分最適に偏りがちな体質だと考えています。部分最適とは、企業を例にして言えば、その方針、人、組織、仕組み、システムなどの中で、それぞれの要素や部署の機能の最適化を図ることです。企業には、製品の開発や製品の生産、販売、その材料の調達、また、人材確保、人材育成などの様々な部署があります。それぞれの機能の生産性を高め、機能を向上させることです。
しかし、部分最適には落とし穴があります。これがバラバラな形で進行すると、企業体全体に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、優秀な人材を確保したいと考えて従業員の給料を上げます。優秀な人材が集まり、従業員のモチベーションが上がるという最適化の効果が現れる一方で、当然、人件費の高騰は、経営を圧迫します。長期的には、極度の合理化、人員のカットなどの労働環境を悪化させ、結果的に企業の存続自体も脅かすことになってしまいます。どんなに開発が優れていても営業をしなくては製品は売れません。また、どんなに営業を一生懸命やろうとも肝心の製品が今ひとつだったらこれも収益が上がらないわけです。
それで企業経営には全体最適という発想が必要になってきます。全体最適とは、システムや組織全体の最適化を図って目的を達成しようとするものです。今の学校教育のあり方を見ていると、この全体最適の発想に欠ける事例をしばしば目にします。今、学校教育が窮地に立たされているとしたら、この部分最適体質がその一つの要因になっていると考えています。
 図1 学級経営の構成要素
図1 学級経営の構成要素暴走する部分最適体質
部分最適のもっとも象徴的なものは、過剰な授業、とりわけ教科指導に対する重み付けです。図1をみればわかるように学級経営だけを見ても、これだけの業務が想定されます。
学校が多大なエネルギーをかけて取り組む研究のほとんどは、授業研究であり教科指導の研究です。また、教師は、教科や領域の専門性を自分のアイデンティティとする傾向があります。教師が、教科の専門性にプライドを持ち、そこを高めようとすることはとても結構なことですが、教師の仕事はそれだけではありません。中学校や高校の教師が、「私は〇〇(教科)教師です」と言うのはわからないでもありません。教員免許状に示してありますから。しかし、「国語教師」が、生徒指導や道徳教育をしなくていいわけではありません。また、小学校の教師までがそうした発言をすることに違和感を感じることがあります。小学校の教員免許状には、どこにも教科名や領域名は書いてありません。
ただ、一方で、教師が特定の教科・領域をアイデンティティにするのもわかります。教員免許を取得する教員養成課程がそうなっているからです。教員養成系の大学では専門課程に入ると、専門性をもった指導教員につきます。そのゼミが教科・領域の専門だとやはりその教師が自分の専門をそれであると自覚するのは自然なことです。将来的には、生徒指導やその他の教科外指導もやらなくてはならないのにもかかわらず特定の教科・領域に関する知識のみを蓄えていくことになります。そして、現場に行って驚くのです。「授業以前にやるべきことがこんなにあるのか」と。
この構造は、現職になっても大きく変わりません。多くの自治体には、教育研究会のようなその地域の教員で構成される研修団体があります。その部会も教科・領域に分かれています。定期的に集まり(集められ)、教科・領域に関する公開授業や研修会を開きます。しかし、そこでは、生徒指導の困難校の教師であるにもかかわらず教科指導をひたすら勉強したり、学校課題とは全く違った内容の勉強をしたりすることがあります。勤務校のニーズとは異なっている研究会の論理で学びを蓄積することになります。また、そこで評価されることは、地域の教師としてのステイタスを上げることになります。すると周囲からも「〇〇(教科・領域名)の△△先生」と呼ばれます。当初は疑問を感じて参加していた教師もやがて「そういうものか」とそこに身を委ねるようになります。ここら辺の事情は、読者のみなさんの方がよくご存知のことでしょう。
全体最適の発想に立った学校教育を
このように授業、とりわけ教科指導に飛び抜けたコストがかけられているバランスを欠いた構造は学校教育のそこかしこに見られます。また、ここに研究会が重なると、学校はさらなる悲劇に襲われます。教師の関心が、ごっそりそっちに持って行かれ、子どもたちの成長のために紡がれていた時間が、見世物としての色合いを濃くしていきます。授業、それも、教科指導、ならびに研究会を大事にすることにはなんの異論もありません。ただ、そこにあまりにもコストがかけられすぎていることが問題だと指摘しているのです。ただでさえ忙しい学校現場が、一部分だけを磨き上げることで疲弊していることが問題だと言っているのです。
しかし、ことの本質はそこではなくて、部分最適に陥りがちな学校教育の体質です。教科の壁を取り払うことが期待された総合的な学習ですら、実践が進むに連れ、独特の枠に囲まれて行ったように感じます。総合的な学習という新しい枠組みをつくってしまったのです。全ての教育活動で行うはずだった道徳も教科化されることになりました。学校教育は、制度やシステムがもつ意図とは裏腹に、そこに生まれる文化は、とにかく分断することが好きなようです。
これまで学校教育が経験してきた、体験主義か系統主義か、ゆとり教育か学力向上か、授業づくりか学級づくりかなどの極端な議論も、こうした部分最適体質と無縁ではないと思います。子どもたちは、国語だけでも、算数だけでも、道徳だけでも、特別活動だけでも、また、部活動だけでも人格を完成するわけではありません。しかし、学校教育は、その人格の完成という目的が極めて曖昧であるために、全体最適に必要な目的を見据えるということがとても苦手です。企業の場合は、消費者が評価者です。したがって、消費者のニーズが評価のものさしです。ところが学校は子どもたちは評価者ではありません。したがって、研究会や教師という業界の価値観がものさしになり、そこでどう評価されるかが重要な関心事になります。学校教育における部分最適の問題は、学習指導要領の理念の実現といった公のねらいとは別なところで、教師のアイデンティティや自己実現の問題といった私の願いが絡み、更に進行していきそうです。
職業人の専門性は世の中の発展のためには大事なことです。しかし、組織体としてはあまり専門化しない方がいいのです。専門性が組織体としての即応力や柔軟性を削いでしまうのです。学校教育、特に義務教育の段階はほどほど未分化だからいいのです。未分化だから、多様な可能性を育てることができるのです。わが国の学校教育は、まだまだ本当の意味で子どもたちのものになっていないと思います。学校教育を大人の自己実現の道具にしてはいけないのです。
次期学習指導要領は、激変が予想されるこれからの社会においてよりよい人生と社会を築くための初等中等教育における役割を示したものです。ひたすらに腕力を付ければ健康になるというものではありません。また、休養だけしても健康になれません。子どもたちの社会人として生きる力を見据えることなくして、一部分の能力だけを磨き上げることは、健康を考えずひたすら筋トレをするようなものです。子どもたちを本当に幸せにしようと思うなら、学校教育も全体最適の発想に立つべきです。
次年度の集団づくり戦略計画の作成はお進みですか。
心強い味方として「学級を最高のチームにする極意シリーズ」があります。私が基本的な考え方を示した理論編と、全国の気鋭の実践が実践編を書きました。実践家の皆さんには、その実践を支える考え方と失敗しそうなポイントとそのリカバリー法も示していただきました。従って、「その人だからできる」という域を超えて広く汎用性があることでしょう。
本シリーズのラインナップは、集団のセオリーに則って構成されています。皆さんのニーズのどこかにヒットすることでしょう。
学級集団は、どんなに良好な状態であろうともその殆どが4月後半から6月にかけて最初の危機を迎えます。
子どもたちがいろいろなメッセージを発してくる頃です。それを如何にうけとめてそれを彼らの成長につなげるかが危機を回避し、学級を機能させるポイントです。
最初の危機を乗り越え、2学期以降の経営が安定するためは、教師と子どもたちの個人的信頼関係を如何に築くかにかかっています。メンバーとの個人的信頼関係の強さが、リーダーの指導力の源泉となります。リーダーとの強い絆が、子ども同士の積極的な協働のエネルギーとなります。技術論だけでは、子どもたちは主体的に行動しないのです。子どもたちのやる気に火を付けるのは、個人的信頼関係の構築にかかっています。
学級はルールから崩れます。また、子どもたちのやる気に満ちた集団は、教師のパフォーマンスでも声の大きさでもなく、ルールの定着度によります。良い学級には、良いルールがあります。そのルールの具体と指導法がギッシリです。
本シリーズは、学級集団づくりの1年間の実践をまるごと見渡すことができます。しかも、理想像から始まるという極めて戦略的な構成になっています。さらに、学級づくりの定期点検ができるチェックリストがついて、定常的に同じ観点で振り返りができるようになっています。
クラスでは目立った問題が起きないけれども、仲もそれほど悪くないようだけれど
も、授業に活気が感じられない、素直に学習しているけれども、やる気があるように
は見えないというクラスが増えています。そこには、授業者である教師が見落としが
ちな問題が潜んでいることがあります。子どもたちのやる気を引き出し全員参加の授
業を実現するにはどうしたらいいのでしょうか。そのためのアイディアが満載となっ
ています。
アクティブ・ラーニングは,単なるペアがグループを活用した交流型の学習ではありません。そして,ただ学習内容に深く触れればいいわけではありません。そこには子どもたちの主体的に学び合う姿が必要なのです。子どもたちが,生き生きとかかわりながら学ぶ授業づくりの具体例を豊富に示しました。