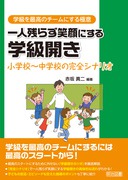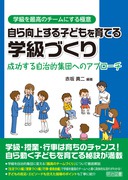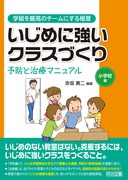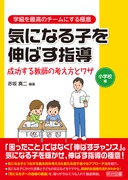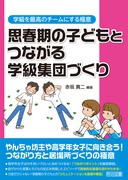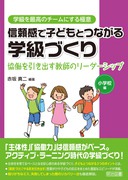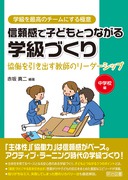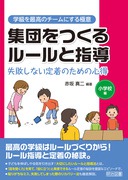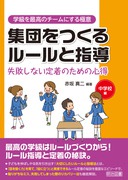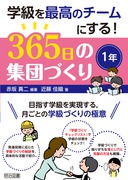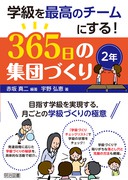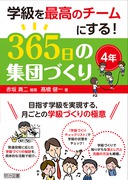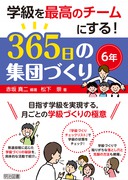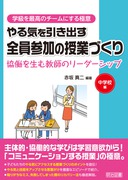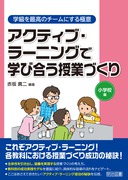- 赤坂真二直伝!教師のリーダーシップ
- 学級経営
これからの教師の必須能力
アクティブ・ラーニングを実現するときに、子どもたちの学習意欲、つまり学習に対するやる気の引き出しが重要なポイントになります。しかし、真面目、勤勉を美徳とする日本人は、他者のやる気を引き出すことが苦手な人が多いようです。言われたことを言われたようにやることが大事な文化では、やる気を高めることなど考えなくても、ことが進みます。近年はその構造がだいぶ変わってきたといいながらも、これまで学校教育は、子どもたちが教師の言うことを聞くという構造の上になり立ってきました。子どもたちのやる気を高めるということについて、本気で考える必要のない文化をもっているといえます。
熱心な先生方は「いや、そんなことはない。一時間一時間の授業で、子どもたちのやる気を高めるための工夫をしてきた」と仰るかもしれません。それは紛れもない事実だと思います。しかし、次期学習指導要領でねらう学習への主体性や、学びに向かう力は、そうした一時間、一単元レベル、そして個々の教師の達成レベルのやる気を問題にしているのではなく、継続的で持続的なやる気のことをいっているのです。これを各教室、各教師といったレベルではなく、学年、学校、地域というようなマクロなレベルで実現できていたら、学習意欲に関して、もう少し違う結果が出ているのではないでしょうか。
ただ、これまでの学校教育を批判したいわけではありません。この構造は、少数の教師が多数の子どもたちを相手に、一定の質の教育を保証するためには必要な仕組みだったと思います。しかし、一律の品質保証をする「工場モデル」の変換を促しているのが、アクティブ・ラーニングの視点による授業の改善です。ただ、次期学習指導要領は、指導時数や指導内容を減らさず、むしろ、増やす方向でつくられます。しかも、学びの質の向上を求め、一方的な教え込みや知識を注入するような授業は、改めて行かねば成りません。普通に考えれば、かなり無茶なハードルを乗り越えて、これからの先生方は、子どもたちのやる気を高めることが求められているのです。
厳しい審判と緩い審判
そこで、まず考えたいことは、子どもたちのやる気を高めることは、誰の役割かということです。企業の経営、つまり、マネジメントでは、モチベーションの管理は、管理者、つまり、マネージャーの仕事です。ドラッカーもマネージャーの5つの役割の一つとして明言しています。マネージャーが仕事を無理矢理させたらメンバーはやる気を失います。やる気を失うと生産性が落ちます。だから、結果に責任をもつマネージャーにとって、メンバーのモチベーション管理は重要な業務なのです。
学校教育も同じ構造であることがおわかりでしょう。どんなに教師ができようが、運動ができようが重要ではありません。教育は、子どもたちが変容して初めて評価される仕事です。一定の成果を上げたいからといって教師が勉強をやらせたら、子どもたちはやる気を失うことでしょう。「そんなことするわけないじゃないか」とおっしゃる方もいるかもしれません。しかし、子どもたちのやる気は多様です。
 熱心に学習している傍らで、ひたすら流れ作業をするように授業を受けている子もいると想定されます。一部の子が朗々としゃべっているそばで、うつろな目をして佇んでいる授業をどれだけ見たことでしょうか。ただ、「全員にやる気をもたせよ」、「それができない教師は無能だ」と言っているわけではありません。教材や教え方に関心を払うことと同等か、それ以上に関心を払うべきだと言っているのです。
熱心に学習している傍らで、ひたすら流れ作業をするように授業を受けている子もいると想定されます。一部の子が朗々としゃべっているそばで、うつろな目をして佇んでいる授業をどれだけ見たことでしょうか。ただ、「全員にやる気をもたせよ」、「それができない教師は無能だ」と言っているわけではありません。教材や教え方に関心を払うことと同等か、それ以上に関心を払うべきだと言っているのです。
では、子どもたちのやる気を引き出すためには何をしたらいいのでしょうか。アクティブ・ラーニングは、協働による問題解決であり、チームスポーツに例えられることがあります。そこで、スポーツを例に話をしてみたいと思います。活動性の高い授業は、選手の全力プレーが繰り広げられる試合のようなものです。選手の活動性が高くなるほど、審判の力量が問われます。きわどいプレーが増えますから。そのときに、選手のモチベーションを上げるのは、ルールの適用が厳しい審判でしょうか、叙情酌量をしてくれる緩い審判でしょうか。答えは明らかですね。厳しい審判です。緩い審判は、一見、優しくていいように思えますが、利害がぶつかる試合では、その時々でジャッジの基準が変わることは、不公平感を生じさせます。不公平感を持つと不利益を被った側は当然やる気を失います。片方の無気力は相手にも伝染し、試合全体のパフォーマンスを落とします。その状態では、勝った方も負けた方もよい結果をチームにもたらしません。
試合において厳格なジャッジが意味するものは、厳しさとか公平性というものだけではありません。試合における厳格で公平なジャッジは、審判に対する信頼を生みます。信頼とは、相手に対する期待が、正当に応えられたときに生じるものです。教室における動機付けの研究では、教師に対する信頼が、子供たちのやる気を高めると結論づけています。教師に対する信頼は、安心を生みます。安心が挑戦への意欲を高め、パフォーマンスを高めるという流れです。
社会を機能させる装置としての信頼
子どもたちのやる気と信頼関係が強く結びついていることを自覚している教師は少なくないことでしょう。しかし、信頼関係と仲良くなることや親しみのある関係になることが区別されていないことがあるようです。両者は似ているようで明確に区別されます。親しみは、家族などの信じることが前提の関係性のなかで生じるもので、信頼という概念を必要としないものです。お母さんが「私は娘を信頼しています」と言ったら、少し、距離を感じませんか。一方で、子どもが「僕は、先生を信頼している」と言ったらなんの違和感もないのではないでしょうか。親しみは、過去から現在を経て、未来までその関係性は大きく変動することなく、リスクがほとんどありません。親子関係が昨日から今日、そして、今日から明日にかけて何か特別な事件でもない限り、大きく変わることはないでしょう。
しかし、教師と子供の関係はそうではありません。教師の何気ない言動が、子供の心を深く傷つけ、明日から教師の顔を見たくないなんていうことが起こり得るのが現代の教師と子供たちの関係性です。身内ではない外側の存在に位置する教師とかかわることは子供にとってリスクです。また、社会の高学歴化による教師の社会的ステイタスの低下や日常的に報道される教師の不祥事が、そのリスクを増幅している可能性があります。こうした構造は現代の世の中には其処此処にあって、世の中が複雑化すればするほど、そこと関係をもつことはリスクを伴うわけです。
買い物をすること、医者に行くこと、政治家に投票することすべてにそうした構造が見られます。そうした状況を乗り越えるためには、リスクを下げる必要があります。つまり、自分の知っているいくつかの体験や認識から、この人なら、この店なら、この医者なら、この政治家なら…といろいろと考えなくてはならないことを単純化する認識をもちます。これが信頼です。人は、信頼という装置を使って、リスクのある世界と関わっていくことが可能になります。信頼という概念は、こうして作り出されてきたと考えられます。
教育は信頼と切っても切れない関係のように認識されています。それは誤りではありませんが、教師は信頼されるべきだ、信頼された方がいい、といった努力目標レベルの話ではないのです。信頼は、教育などの制度が整えられるなど、社会の仕組みが複雑化してくる過程においてそれが機能するため社会的装置ですから、必須なのです。つまり、教育を機能させるのは信頼なのです。そして、社会はこれからさらに複雑化することが予想されますから、信頼の重要度は更に増すわけです。
今見てきたように、信頼と親しみは区別されるべきものです。教師と子どもの関係は、親しみといったもので説明できず、教師という未知な存在に対して、これからに向かって起こるリスクを超えるだけの安心感を予期させるだけのものでなくてはならないということです。つまり、この先生なら、きっとこの先も大丈夫と思わせるような関係性がないと教育は成り立たないということです。信頼を獲得しないところで、教育をやろうとすると、やはり、そこに力づくや強制による指導が入り込んでくることでしょう。
そして、もう一つ大事なことがあります。それは、親しみの段階を経ないと信頼は生まれてこないということです。当然のことですが、なんのコストもかけずに子どもたちは教師を信頼しません。未来への安心を予期させるだけの親しみに満ちた時間が必要なのです。笑顔でたたずみ、朗らからに笑い、あたたかな声をかける。大事なことを真剣に伝え、馬鹿話で笑い合う。派手でなくていいから、丁寧なあたたかな楽しい授業を繰り返す。そんな今日の親しみに満ちた時間が、明日からのリスク予期を低減させるのです。そうした日常がつくり出す信頼が、子どもたちのやる気を引き出す力を与えます。
次年度の集団づくり戦略計画の作成はお進みですか。
心強い味方として「学級を最高のチームにする極意シリーズ」があります。私が基本的な考え方を示した理論編と、全国の気鋭の実践が実践編を書きました。実践家の皆さんには、その実践を支える考え方と失敗しそうなポイントとそのリカバリー法も示していただきました。従って、「その人だからできる」という域を超えて広く汎用性があることでしょう。
本シリーズのラインナップは、集団のセオリーに則って構成されています。皆さんのニーズのどこかにヒットすることでしょう。
学級集団は、どんなに良好な状態であろうともその殆どが4月後半から6月にかけて最初の危機を迎えます。
子どもたちがいろいろなメッセージを発してくる頃です。それを如何にうけとめてそれを彼らの成長につなげるかが危機を回避し、学級を機能させるポイントです。
最初の危機を乗り越え、2学期以降の経営が安定するためは、教師と子どもたちの個人的信頼関係を如何に築くかにかかっています。メンバーとの個人的信頼関係の強さが、リーダーの指導力の源泉となります。リーダーとの強い絆が、子ども同士の積極的な協働のエネルギーとなります。技術論だけでは、子どもたちは主体的に行動しないのです。子どもたちのやる気に火を付けるのは、個人的信頼関係の構築にかかっています。
学級はルールから崩れます。また、子どもたちのやる気に満ちた集団は、教師のパフォーマンスでも声の大きさでもなく、ルールの定着度によります。良い学級には、良いルールがあります。そのルールの具体と指導法がギッシリです。
本シリーズは、学級集団づくりの1年間の実践をまるごと見渡すことができます。しかも、理想像から始まるという極めて戦略的な構成になっています。さらに、学級づくりの定期点検ができるチェックリストがついて、定常的に同じ観点で振り返りができるようになっています。
クラスでは目立った問題が起きないけれども、仲もそれほど悪くないようだけれど
も、授業に活気が感じられない、素直に学習しているけれども、やる気があるように
は見えないというクラスが増えています。そこには、授業者である教師が見落としが
ちな問題が潜んでいることがあります。子どもたちのやる気を引き出し全員参加の授
業を実現するにはどうしたらいいのでしょうか。そのためのアイディアが満載となっ
ています。
アクティブ・ラーニングは,単なるペアがグループを活用した交流型の学習ではありません。そして,ただ学習内容に深く触れればいいわけではありません。そこには子どもたちの主体的に学び合う姿が必要なのです。子どもたちが,生き生きとかかわりながら学ぶ授業づくりの具体例を豊富に示しました。