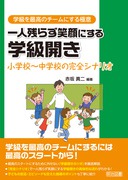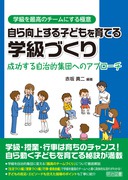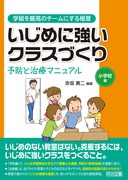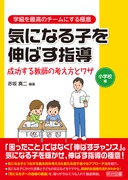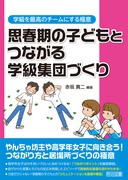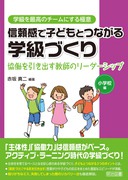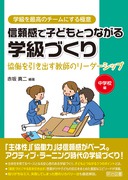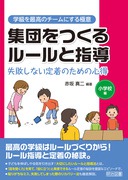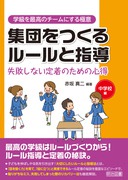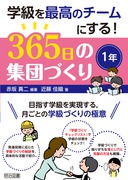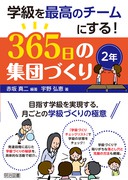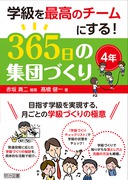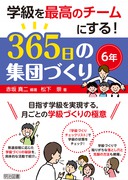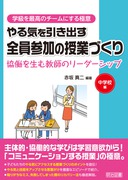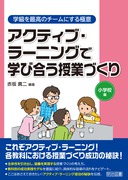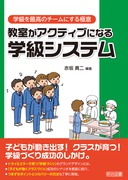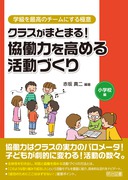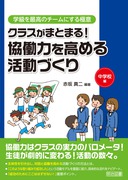- �ԍ�^�`�I���t�̃��[�_�[�V�b�v
- �w���o�c
�@���s�̊w�K�w���v�̂Ɍ�����w�͂̎O�v�f�́A���X�����܂ł��Ȃ��A
�P�@��b�I�E��{�I�Ȓm���E�Z�\�̏K��
�Q�@�m���E�Z�\�����p���ĉۑ���������邽�߂ɕK�v�Ȏv�l�́E���f�́E�\���͓�
�R�@�w�K�ӗ~
�ł��B
�@����́A�ǂ����痈�Ă��邩�Ƃ����ƁA����19�N6���Ɍ��z���ꂽ�w�Z����@�̈ꕔ�����ɂ���āA���E���E�����w�Z���ɂ����āu���U�ɂ킽��w�K�����Ղ��|����悤�A��b�I�Ȓm���y�ыZ�\���K��������ƂƂ��ɁA���������p���ĉۑ���������邽�߂ɕK�v�Ȏv�l�́A���f�́A�\���͂��̑��̔\�͂��͂����݁A��̓I�Ɋw�K�Ɏ��g�ޑԓx��{�����ƂɁA���Ɉӂ�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƒ�߂�ꂽ���Ƃɂ��܂��B����܂łڂ��肵�Ă���������͂��������m�ɂȂ����ƌ����܂��B���������u������́v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂ł��傤���B
�@�������w�Z�̋��t�ɂȂ����A�������N�i1989�N�j���́A���ɂ͂����������t�����Ƃ͂���܂���ł����B�������A1996�N�ɕ����ȁi���݂̕����Ȋw�ȁj�̒�������R�c��u21���I��W�]�����䂪���̋���݂̍���ɂ��āv�Ƃ�������ɑ����1�����\�̒��ŁA
�u��X�͂��ꂩ��̎q�������ɕK�v�ƂȂ�̂́A�����ɎЉ�ω����悤�ƁA�����ʼnۑ�������A����w�сA����l���A��̓I�ɔ��f���A�s�����A���悭�����������鎑����\�͂ł���A�܂��A����𗥂��A���l�ƂƂ��ɋ������C���l���v�����S�⊴������S�ȂǁA�L���Ȑl�Ԑ��ł���ƍl�����B�����܂��������邽�߂̌��N��̗͂��s���ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B��X�́A��������������\�͂��A�ω��̌��������ꂩ��̎Љ���m������́n�Ə̂��邱�ƂƂ��A�������o�����X�悭�͂�����ł������Ƃ��d�v�ł���ƍl�����B�v
�Ǝ����ꂽ���Ƃ���A����E�̐V���ȓ��B�_�Ƃ��Ĝa���̔@������܂����B
�@���̂��Ƃ���킩��悤�ɁA����2000�N���ȑO�ɁA���ł́A�ω��ւ̑Ή��͂�A��̓I�Ȕ��f�����������\���A���������҂Ƃ̋��������L���Ȑl�Ԑ��̈琬�Ƃ����������w�K�w���v�̂ł˂���Ă��鎑���E�\�͂��c�_����Ă������Ƃ��킩��܂��B
�@��������������āA��Ƃ苳��Ɉڍs���悤�Ƃ��Ă����킯�ł��B�������A�w�K�w���v�̂��������ꂽ���N��1999�N�����肩��A�w�͒ቺ�_���킫�N����A���̌�̂o�h�r�`2003�A2006�ɂ����鏇�ʂ̒ቺ�A�����u�o�h�r�`�V���b�N�v���ǂ��ł��������A���̐ӔC������`�ŁA��Ƃ苳��ɕ����]���������ꂽ�̂͊F�������m�̒ʂ�ł��B���ʂ̒ቺ���A�{���ɂ�Ƃ苳��̂������ǂ����́A�c�_���������Ƃ���ł��B
�@������������܂�����ŁA���߂Ď����w�K�w���v�̂ł˂炤�����E�\�͂����Ă݂܂��傤�B
�@����28�N12��21���ɒ�������R�c���o���ꂽ�u�c�t���A���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�y�ѓ��ʎx���w�Z�̊w�K�w���v�̓��̉��P�y�ѕK�v�ȕ������ɂ��āi���\�j�v�ɂ��A
�@�u���𗝉����Ă��邩�A�����ł��邩�i�����ē����u�m���E�Z�\�v�̏K���j�v
�A�u�������Ă��邱�ƁE�ł��邱�Ƃ��ǂ��g�����i���m�̏ɂ��Ή��ł���u�v�l�́E���f�́E�\���͓��v�̈琬�j�v
�B�u�ǂ̂悤�ɎЉ�E���E�Ɗւ��A���悢�l���𑗂邩�i�w�т�l����Љ�ɐ��������Ƃ���u�w�тɌ������́E�l�Ԑ����v�̟��{�j�v
�Ƃ���܂��B
�@���́A���̕\�L�͂������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�R�c�̗����m��Ȃ��l������������ǂނƁA���̎O���ɒB�����Ȃ��ĂȂ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�c�_�́A�i�ނɘA��āA�{���I�ȂƂ��납��}�����ꂵ�Ă����܂��B�}�t�ɖڂ�D����ƍ�����������Ă��܂��ł��傤�B�����k��ƁA�˂���Ă���w�̖͂{�����͂߂邱�Ƃł��傤�B
�@���̎O�ɂ͑��݂Ɋ֘A��������܂��B����28�N8��26���ɒ�������R�c����������番�ȉ��ے������o���ꂽ�u�����w�K�w���v�̓��Ɍ���������܂ł̐R�c�̂܂Ƃ߁i�j�v�ɂ́A���̂悤�ȕ\�L������܂��B�B�u�ǂ̂悤�ɎЉ�E���E�Ɗւ��A���悢�l���𑗂邩�i�w�т�l����Љ�ɐ��������Ƃ���u�w�тɌ������́E�l�Ԑ����v�̟�����{�j�v�ɂ��Ăł��B�u�O�q�̇@�y�чA�̎����E�\�͂��A�ǂ̂悤�ȕ������œ������Ă�����������t����d�v�ȗv�f�ł���v�Ƃ������̂ł��B�܂�A�u�m���E�Z�\�v��A�u�v�l�́E���f�́E�\���͓��v�́A�u�w�тɌ������́E�l�Ԑ����v�̟��{�̂��߂ɏ��������������Ƃ������Ƃł��B�����������Ɍ����Ă��炦��A���̂R���\��������A�����d�v�Ȃ̂��킩��܂��B�������A����ŁA�����A���p�͂̕����ŎO�̗͂����L����A������悭�킩��ɂ����悤�Ɏv���܂��B
�@���������k��A�w�͂̐��̂��͂����肷�邩������܂���B����27�N8��26���ɏo���ꂽ�������o���ꂽ�u����ے������ʕ���ɂ�����_�_�����ɂ��āi�j�v�ɂ��ƁA�v�l�́E���f�́E�\���͓��ɂ��Ď��̂悤�ȕ\�L������܂��B
�u�������A���̖����`�������̕����������肵�A�������@��T���Čv��𗧂āA���ʂ�\�����Ȃ�����s���A�v���Z�X��U��Ԃ��Ď��̖�蔭���E�����ɂȂ��Ă������Ɓi��蔭���E�����j��A���𑼎҂Ƌ��L���Ȃ���A�Θb��c�_��ʂ��Č݂��̑��l�ȍl�����̋��ʓ_�⑊��_�𗝉����A����̍l���ɋ��������葽�l�ȍl���������肵�āA���͂��Ȃ�������������Ă������Ɓi�����I�������j�̂��߂ɕK�v�Ȏv�l�́E���f�́E�\���͓��ł���B�v�Ƃ���܂��B���p�͂Ƃ́A�Y�o�������A�����I�����������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B
�@���̎����E�\�͂̊�Ղ́A�������琭�����������u21���I�^�\�́v�ł���A���̋c�_�̂��Ƃ́A�n�d�b�c�̃L�[�E�R���s�e���V�[�i��v�\�́j�ł��B�L�[�E�R���s�e���V�[�Ƃ́A�u1�@�l���̐�����Љ�̔��W�ɂƂ��ėL�v�A�Q�@���܂��܂ȕ����̒��ł��d�v�ȗv���i�ۑ�j�ɑΉ����邽�߂ɕK�v�A�R�@����̐��Ƃł͂Ȃ����ׂĂ̌l�ɂƂ��ďd�v�A�Ƃ��������������Ƃ��đI�����ꂽ���́v�ł���ƒ�`����Ă��܂��i�����Ȋw�Ȃg�o�u�n�d�b�c�ɂ�����u�L�[�E�R���s�e���V�[�v�ɂ��āv���j�B���������ƃL�[�E�R���s�e���V�[�̒��S�Ɉʒu���Ă���̂́A�K���Ȑl���̑n�����Љ�ւ̍v���Ɍ������������������Ӑ}���Ă��邱�Ƃ����������܂��B
�@���l�Ȑl���������l�Ȉӌ��������Ă���Ƌc�_���܂Ƃ܂�܂���B��������ƁA�Ë��_�͕���\�L�ł��B�݂�ȑ厖�Ȃ��Ƃ����ɁA���_�ɂȂ鍠�ɂ̓��U�C�N�̗l�ɂȂ��Ă��܂��āA�Ȃ��悭�킩��Ȃ��Ȃ�܂��B�������ċc�_�̗�������Ă���ƁA�S���҂݂̂Ȃ���̗l�X�Ȋ�������Ƃ肪���������Ƃ��ǂݎ��܂��B�������A������厖������厖�ł́A����͎̂q�ǂ������ł��B����W�҂ɂƂ��ċ���͎d���ł����Ă��A�q�ǂ������ɂ͐l���Ȃ̂ł��B
�@���̒����ω�����A����́A���̑�l�������\�z�̂ł��Ȃ��ω��ł��B�����ŗl�X�Ȗ�肪�N����A�������瑽���̉ۑ肪�h�����Ă��邱�Ƃł��傤�B�����̋�̂́A�͂����肵�܂��A��肪�N���邱�Ƃ����͂͂����肵�Ă���̂ł��B���t���w�͂̎p�������ĉE���������Ă�����A�q�ǂ�������H���ɖ��킹�邱�ƂɂȂ�܂��B���{�̊w�͂̎p�́A����������₱�����Ǝv���܂��B�w�͂̒��j�́A�������\���ƌ������Ă��܂����炢�����ł��傤���B���̖����A��l�ʼn�������ɂׂ͉��d��������̂ƂȂ�͂��ł��B�����ŕK�v�ɂȂ��Ă���̂́A�͂����킹�ĖړI��B�����鋦�����ł��B�������Ԃꂸ�Ɍ������Ă�������ƈ�Ă邱�Ƃ��ł��鋳�炪�A�q�ǂ������ɖ����������邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�@���N�x�̏W�c�Â���헪�v��̍쐬�͂��i�݂ł����B
�@�S���������Ƃ����u�w�����ō��̃`�[���ɂ���ɈӃV���[�Y�v������܂��B������{�I�ȍl���������������_�҂ƁA�S���̋C�s�̎��H�����H�҂������܂����B���H�Ƃ̊F����ɂ́A���̎��H���x����l�����Ǝ��s�������ȃ|�C���g�Ƃ��̃��J�o���[�@�������Ă��������܂����B�]���āA�u���̐l������ł���v�Ƃ�������čL���ėp�������邱�Ƃł��傤�B
�@�{�V���[�Y�̃��C���i�b�v�́A�W�c�̃Z�I���[�ɑ����č\������Ă��܂��B�F����̃j�[�Y�̂ǂ����Ƀq�b�g���邱�Ƃł��傤�B
�@�w���W�c�́A�ǂ�ȂɗǍD�ȏ�Ԃł��낤�Ƃ����̖w�ǂ�4���㔼����6���ɂ����čŏ��̊�@���}���܂��B
�@�q�ǂ����������낢��ȃ��b�Z�[�W���Ă��鍠�ł��B�����@���ɂ����Ƃ߂Ă����ނ�̐����ɂȂ��邩����@��������A�w�����@�\������|�C���g�ł��B
�@�ŏ��̊�@�����z���A2�w���ȍ~�̌o�c�����肷�邽�߂́A���t�Ǝq�ǂ������̌l�I�M���W��@���ɒz�����ɂ������Ă��܂��B�����o�[�Ƃ��l�I�M���W�̋������A���[�_�[�̎w���͂̌����ƂȂ�܂��B���[�_�[�Ƃ̋����J���A�q�ǂ����m�̐ϋɓI�ȋ����̃G�l���M�[�ƂȂ�܂��B�Z�p�_�����ł́A�q�ǂ������͎�̓I�ɍs�����Ȃ��̂ł��B�q�ǂ������̂��C�ɉ�t����̂́A�l�I�M���W�̍\�z�ɂ������Ă��܂��B
�@�w���̓��[���������܂��B�܂��A�q�ǂ������̂��C�ɖ������W�c�́A���t�̃p�t�H�[�}���X�ł����̑傫���ł��Ȃ��A���[���̒蒅�x�ɂ��܂��B�ǂ��w���ɂ́A�ǂ����[��������܂��B���̃��[���̋�̂Ǝw���@���M�b�V���ł��B
�@�{�V���[�Y�́A�w���W�c�Â���̂P�N�Ԃ̎��H���܂邲�����n�����Ƃ��ł��܂��B�������A���z������n�܂�Ƃ����ɂ߂Đ헪�I�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B����ɁA�w���Â���̒���_�����ł���`�F�b�N���X�g�����āA���I�ɓ����ϓ_�ŐU��Ԃ肪�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�N���X�ł͖ڗ�������肪�N���Ȃ�����ǂ��A��������قLj����Ȃ��悤�������
���A���ƂɊ��C���������Ȃ��A�f���Ɋw�K���Ă��邯��ǂ��A���C������悤��
�͌����Ȃ��Ƃ����N���X�������Ă��܂��B�����ɂ́A���Ǝ҂ł��鋳�t�������Ƃ���
���Ȗ��������ł��邱�Ƃ�����܂��B�q�ǂ������̂��C�������o���S���Q���̎�
�Ƃ����������ɂ͂ǂ������炢���̂ł��傤���B���̂��߂̃A�C�f�B�A�����ڂƂȂ�
�Ă��܂��B
�@�A�N�e�B�u�E���[�j���O�́C�P�Ȃ�y�A���O���[�v�����p�����𗬌^�̊w�K�ł͂���܂���B�����āC�����w�K���e�ɐ[���G�������킯�ł͂���܂���B�����ɂ͎q�ǂ���������̓I�Ɋw�э����p���K�v�Ȃ̂ł��B�q�ǂ��������C���������Ƃ������Ȃ���w�Ԏ��ƂÂ����̋�̗��L�x�Ɏ����܂����B
�@�N���X�́A�W�����ⓖ�Ԋ����Ȃǂ����ɓƗ����ċ@�\����킯�ł͂���܂���B���ꂼ��̊������A�����Ċw������Ă܂��B ���������Ƃ����������̍����w���W�c����Ă����߂ɂ́A�e�������Ӑ}�I�ɔz�u�����f�U�C���̎����グ�邱�Ƃ���ł��B�w���Ō��ʂ��グ�Ă�����ۂ̃V�X�e���Ƃ��̉^�p�̃|�C���g���L�x�ɏЉ��Ă��܂��B
�@�u�N���X���܂Ƃ܂�Ȃ��v�Ƃ����b���悭���ɂ��܂��B���̎���́A�܂Ƃ߂悤�Ƃ��Ă��܂Ƃ܂�܂���B�q�ǂ����������̘g�ɓ��ꍞ�ޔ��z�́A��������x��ł��B�q�ǂ�������l�ЂƂ�ɁA���͂��ĉۑ����������́A�܂�A�����͂���Ă�悤�ɂ��܂��B�q�ǂ������̂Ȃ���͂������o���w���̃X�e�b�v�Ɩ��͓I�Ȋ��������L�x�ɏЉ��Ă��܂��B