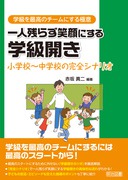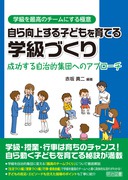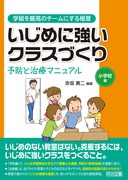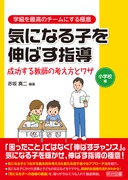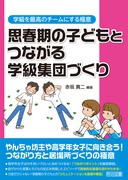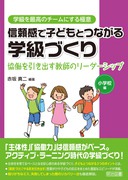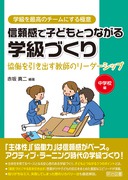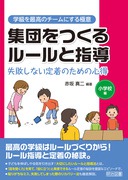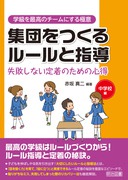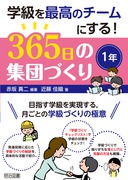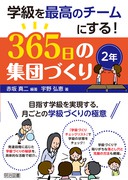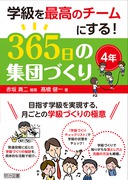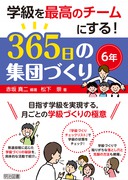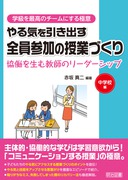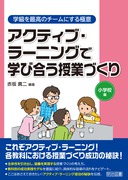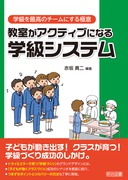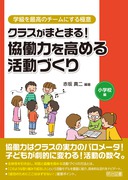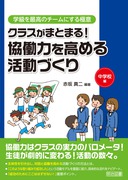1 教室における子どもたちの目的
「人間の行動には目的があり、従って子どもたちの問題行動にも目的がある」、目的論はこうした考え方に立ちます。そのように考えると、子どもたちの問題行動にも目的があるということになります。子どもたちの行動の目的を知ることによって、彼らの問題行動のメカニズムを知ることが可能になるでしょう。
私たちにとって感情は、人生を豊かにしてくれるとても大事なものです。しかし同時に、しばしば事実の認識を妨げてしまうことがあります。子どもたちの問題行動は、私たちの感情を揺さぶります。それは、「わからない」ことに起因することが多いように思います。しかし、それがどのようなプロセスや仕組みを経て生起されているかがわかれば、理解ができます。理解は私たちを冷静にしてくれます。冷静さは、問題行動を繰り返す子どもたちに寄り添おうという、教師としての使命感や人としての愛情を喚起してくれることでしょう。寄り添うためには、理解することが出発点になるのではないでしょうか。
では、
教室における子どもたちの目的とはなんでしょうか。
優等生的な答えは、勉強する、友だちに会いに来るなどでしょうか。先生に会いに来ると言ってくれたら教師にとっては嬉しいですね。哲学的な表現が好きな方は、成長しに来るなんて言い方もあるでしょう。研究会に来る先生方にお尋ねすると、給食を食べに来る、友だちと遊びに来る、なんていう答えが返ってくることがあります。
アドラー心理学的には次のように考えます。
みなさんは、電車に乗ったときにまず何をしますか。恐らく、真っ先に座席を探すことでしょう。もし満席だったら、立つ場所を探すことでしょう。つまり身の置き所を確保しようとすることでしょう。では、座席が確保されたら次にすることはどのようなことでしょうか。例えば、結婚式の披露宴などにお呼ばれをしたときのことを思い出してください。会場に着きました。宴の会場に入ると座席表を確認して、テーブルを探しそれが見つかると、名札を見つけてその席に着くことでしょう。その次は何をするでしょうか。恐らく、周囲を見渡して知り合いを探すことでしょう。そして、同じテーブル内で知り合いを見つければおしゃべりを始めることでしょう。テーブル外で旧知の方を見つければ、席を離れてその方の側に行き、懐かしい話を始めることでしょう。

2 「ジベタリアン」たちの優先事項
私たちは何をしているかというと、自分の身の置き所、つまり居場所を真っ先に確保するように行動しているわけです。電車の例では、物理的な居場所を探しています。披露宴の例では、社会的な居場所を確保しようとしています。恐らくそれは安全の確保と直結しているからだと思われます。私たちが生物である以上は安全の確保を最優先に行動せざるを得ません。一方で集団生活をする人間にとって、居場所は物理的なものだけでなく、社会的なものも生じます。物理的な居場所が、命の危険がある場合ではない限り、その重要度が逆転することもあるようです。
知らない町に一人で取り残されたら、私たちはとても不安になります。しかし、そこに親しい友人が現れたらどうでしょう。途端に楽しくなります。場合によっては、「ちょっと散策しようか」という冒険も始まるかもしれません。お化け屋敷にも友だちと一緒ならば入れます。お化け屋敷に入ろうとする人たちは、怖がっているようですが命まで取られることはないと確信しています。友だちという社会的居場所があるからこそ不安に耐え、それを喜びや楽しみにも転じることが可能なのです。

居場所を確保するときに、社会的文脈はとても重要です。
電車の例に話を戻すと、満席の場合でも通路が空いていることがあります。しかし、通路に腰掛ける方はいません。相当に疲労した方だって通路には腰掛けません。先日、ローカル線の電車の通路に腰を下ろしている女子高校生を見かけましたが、グループ数人で同じような行動をとっていました。こうした若者たちを、「ジベタリアン」と呼んだことがありました。一見、マナーを守ってないように見える行動ですが、ちゃんと彼女たちも社会的文脈を尊重しています。ただ、彼女たちにとって優先すべき社会とは、自分たちのグループです。恐らく一人ではしないはずです。
3 全ては適応行動?
こうして考えてくると子どもたちの教室における行動の目的が見えてきます。それは、
教室という社会で居場所を確保すること
です。学校においては、子どもたちには、座席という物理的居場所は確保されています。従って重要なのは、社会的居場所なのです。子どもたちは、教室で居場所を見つけるために様々な行動をします。ある子は、望ましい行動でそれをしようとします。例えば、教師の話をよく聞いたり、学習をがんばったり、何か役があると立候補したり、頼まれた仕事を引き受けたり、活動に協力をするなどのことです。また、ある子は、反対に望ましくない行動でそれをしようとします。例えば、教師の話を聞かなかったり、学習に集中しなかったり、仕事をさぼったり、ウケねらいの発言をしたり、無気力になったりすることです。
子どもたちが、なぜ望ましい行動をし、また、その逆の行動をしたくなるのか探りたくなりますよね。しかし、そう思ったあなたはもう原因論の罠にはまろうとしています。原因探しが無駄だとは言いません。しかし、教師がそれを知っても原因を取り去ることはかなり難しいことだとこれまでに述べました。大事なことは、「なんのために」子どもたちがそうした行動をしているのかという目的です。ただ、子どもたちの生育歴や家庭環境といった気になる行動や問題行動の原因と結びつきやすい要因を知ることは、彼らの目的を知る上では重要になることはあるでしょう。
教室を立ち歩いている子どもたちにも目的があります。すぐに私語をしてしまう子どもたちにも目的があります。また、あなたに反抗的な子どもたちにも目的があります。それらの行動は、教師にとっては困った行動かもしれません。しかし、それらは、子どもたちにとっては適応のための行動なのです。子どもたちは、教室という不安定な環境のなかで居場所を見つけるために必死なのです。
次年度の集団づくり戦略計画の作成はお進みですか。
心強い味方として「学級を最高のチームにする極意シリーズ」があります。私が基本的な考え方を示した理論編と、全国の気鋭の実践が実践編を書きました。実践家の皆さんには、その実践を支える考え方と失敗しそうなポイントとそのリカバリー法も示していただきました。従って、「その人だからできる」という域を超えて広く汎用性があることでしょう。
本シリーズのラインナップは、集団のセオリーに則って構成されています。皆さんのニーズのどこかにヒットすることでしょう。
学級集団は、どんなに良好な状態であろうともその殆どが4月後半から6月にかけて最初の危機を迎えます。
子どもたちがいろいろなメッセージを発してくる頃です。それを如何にうけとめてそれを彼らの成長につなげるかが危機を回避し、学級を機能させるポイントです。
最初の危機を乗り越え、2学期以降の経営が安定するためは、教師と子どもたちの個人的信頼関係を如何に築くかにかかっています。メンバーとの個人的信頼関係の強さが、リーダーの指導力の源泉となります。リーダーとの強い絆が、子ども同士の積極的な協働のエネルギーとなります。技術論だけでは、子どもたちは主体的に行動しないのです。子どもたちのやる気に火を付けるのは、個人的信頼関係の構築にかかっています。
学級はルールから崩れます。また、子どもたちのやる気に満ちた集団は、教師のパフォーマンスでも声の大きさでもなく、ルールの定着度によります。良い学級には、良いルールがあります。そのルールの具体と指導法がギッシリです。
本シリーズは、学級集団づくりの1年間の実践をまるごと見渡すことができます。しかも、理想像から始まるという極めて戦略的な構成になっています。さらに、学級づくりの定期点検ができるチェックリストがついて、定常的に同じ観点で振り返りができるようになっています。
クラスでは目立った問題が起きないけれども、仲もそれほど悪くないようだけれども、授業に活気が感じられない、素直に学習しているけれども、やる気があるようには見えないというクラスが増えています。そこには、授業者である教師が見落としがちな問題が潜んでいることがあります。子どもたちのやる気を引き出し全員参加の授業を実現するにはどうしたらいいのでしょうか。そのためのアイディアが満載となっています。
アクティブ・ラーニングは、単なるペアがグループを活用した交流型の学習ではありません。そして、ただ学習内容に深く触れればいいわけではありません。そこには子どもたちの主体的に学び合う姿が必要なのです。子どもたちが、生き生きとかかわりながら学ぶ授業づくりの具体例を豊富に示しました。
クラスは、係活動や当番活動などがばらばらに独立して機能するわけではありません。それぞれの活動が連動して学級を育てます。 いきいきとした活動性の高い学級集団を育てるためには、各活動を意図的に配置したデザインの質を上げることが大切です。学級で効果を上げている実際のシステムとその運用のポイントが豊富に紹介されています。
「クラスがまとまらない」という話をよく耳にします。今の時代は、まとめようとしてもまとまりません。子どもたちを一定の枠に入れ込む発想は、もう時代遅れです。子どもたち一人ひとりに、協力して課題を解決する力、つまり、協働力を育てるようにします。子どもたちのつながる力を引き出す指導のステップと魅力的な活動例が豊富に紹介されています。
-
- 1
- 新潟の教育者
- 2018/1/24 11:10:41
激しく共感いたしました。今からこの内容を実践してこようと思います。がんばります。いや、がんばるのは子どもたちか。。。